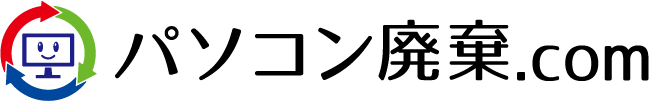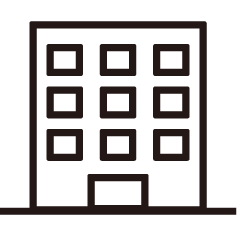404 Not Found
SONYが誇る大人気ゲーム機「PS4(PlayStation4)」。
高価なゲーム機であるため、どれぐらいの期間壊れずに動いてくれるのかと気になっている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、PS4で遊べる期間はどれくらいなのか、故障前の症状はどういったものなのか、延命するための対策法はあるのか、といった点について解説していきます。
【この記事でわかること】
- PS4の平均的な寿命
- PS4の寿命を縮めてしまう原因
- 故障前の症状
- 少しでも長くPS4を使うための対策
PS4(PlayStation4)の寿命は何年?

PS4の寿命がどれくらいなのかという点について、SONY公式の情報はないのですが、PS4を含む一般的な電化製品は最大で10年もつように設計されています。
従ってPS4も、使用方法に注意すれば10年は壊れずに動いてくれるということになります。
最大設計通りの年数まで使用するのは難しいにしても、日々寿命を延ばすための使用方法を心掛けていれば、1〜2年で壊れてしまうようなことはまずないでしょう。
PS4の寿命を延ばすための使用方法については後述します。
PS4の寿命を縮める原因

電化製品に限らずどんな製品にも言えることですが、使用方法が雑になると寿命を縮めてしまうことになります。
以下に、PS4における「寿命を縮める原因」について解説していきます。
踏みつけや落下物による物理的破損
据え置き型ゲーム機であるPS4の場合、誤って本体を落としてしまうというリスクは低いですが、PS4の上に何かを落としてしまったり、間違って踏みつけてしまうというリスクはあります。
こうした物理的な負荷をかけることで、基板の損傷やケーブル差込口の変形などを招いてしまいます。
多湿な環境
精密機械にとって、湿気というのは大敵です。
PS4は風呂場などの湿気の多い場所で使用することが想定されていないため、当然防水仕様にはなっていません。
- 風呂場の近くにPS4を保管する
- すぐそばに加湿器がある状況でプレイする
- 水やジュースを本体にこぼす
こういった行為は、PS4の寿命を大いに縮めてしまいます。
タバコによるヤニ
意外かもしれませんが、タバコの煙が原因でPS4本体にこびりつくヤニも、寿命を縮める原因となってしまいます。
タバコの煙が原因で通風孔が塞がってしまうことがあるからです。
そうなってしまうと、本体内に熱がこもりやすくなり、故障しやすくなることはもちろん火災の原因にもなり得ます。
通風孔に溜まったタバコの煙やヤニは、熱を逃がす役割を妨害することがある上、本体内の光ピックアップのレンズに悪影響を及ぼしてディスクが読み取れないといった故障原因にも繋がってしまいます。
ホコリの多い場所での保管
プレイする時の環境や保管場所が悪いことも、故障原因になってしまうことがあります。
まず、ホコリだらけの場所にPS4を保管してしまうと、PS4本体にホコリが吸着し、排熱能力を低下させてしまう原因になってしまいます。
また、ホコリは静電気をまといやすいです。
静電気は、予期せぬ不具合や故障を招きやすいので、出来る限り避けなければならないものとなっています。
プレイする時も同様で、ホコリが舞い散っているような不潔な環境で遊び続けていると、本体がどんどんホコリによって汚れてしまいます。
雑なケーブルの抜き差し
ケーブルの抜き差しを行う際、力任せにやっていると本体側もケーブル側もダメージを負うことがあります。
主なダメージは、「ケーブルの変形」や「ポートの破損」です。
一度変形や破損が発生してしまうと、修理に出す他なくなってしまいます。
スリープ設定の解除
PS4は、長時間プレイしたり電源をつけっぱなしにしていたりする場合の対策として、デフォルトで「3時間でスリープ状態になる」という設定になっています。
しかし、長時間プレイが常態化している人にとってはいちいちスリープ状態に入ってしまうことを鬱陶しく感じ、解除してしまうということが多発しています。
これにより、本体を長持ちさせるための設定であるスリープ機能が働かなくなり、本体が常に起動状態となることで熱がこもりやすくなってしまうのです。
虫の混入
据え置き型ゲームならではのトラブルなのですが、PS4は虫が好む「光」と「熱」を兼ね備えているため、それに吸い寄せられた小虫が本体内部に入り込んでしまうということもあります。
室内環境が清潔ならばそれほど心配はありませんが、あまり掃除をしておらず、コバエなどの小虫が飛んでいることが珍しくない不潔な環境の場合、虫の混入による故障リスクは軽視できません。
PS4にとって虫は異物ですので、当然故障の原因となります。
日本では稀ではありますが、小型のゴキブリの侵入例なども報告されています。
PS4が寿命を迎えそうな時に出やすい症状

PS4がそろそろ故障しそうな時に出やすい症状を列挙していきます。
突然電源が落ちる/うまく起動しない
PS4は、通気性の悪い場所で使用することによって本体に熱がこもると、冷却ファンが高速回転して本体内の温度を下げようとします。
しかし冷却が追いつかない場合は、自動で電源を切ってそれ以上熱がこもるのを防ごうとします。
稀にこういった症状が起きる程度ならば、単に一時的な長時間使用などによって熱がこもってしまったということが考えられますが、頻繁に電源が落ちるようになってしまうと、冷却ファンの劣化による症状という可能性が高まります。
また、電源が入らなくなってしまうと内部的な不具合が起きていることも疑われるため、PlayStation公式のオンライン修理受付サービスに連絡するようにしてください。
参考 : PlayStation®4の電源が勝手に落ちる / 電源が入らない場合のトラブルシューティング(日本) | PlayStation.com
ラグの多発
ラグとは、「タイムラグ」などの言葉にあるように「ズレ」のことです。
自分の操作が画面上に反映されるのが遅れることにより、自分のプレイに支障が出たり、オンラインで他のプレイヤーと遊んでいる時に迷惑をかけてしまう現象のことを指します。
ラグ発生の多くはネット環境が不安定なことに起因しますが、PS4本体の劣化が原因となる場合もあります。
ネット環境に問題がないのにラグが多発する場合は、本体の劣化を疑うべきでしょう。
熱暴走
PS4はパソコン同様、冷却ファンを使って熱を外に逃がしています。
熱がこもりすぎると、発熱が更なる発熱を招くことによって温度の制御ができなくなる、いわゆる「熱暴走」を引き起こし、不具合や部品破損といった事態を誘発してしまうからです。
冷却ファンが劣化している場合、この熱暴走が起こってしまう可能性があります。
熱暴走を起こすと、本体が異常なまでに熱くなってきます。
熱暴走防止機能として、温度が高くなりすぎると自動で電源が落ちるように設計されていますが、その機能が働かずにそのまま本体温度が上昇することもあります。
こうなるとかなり危険な状態なので、一刻も早く電源を落とすべきです。
BLODの発生
BLODとは、「ブルーライトデス(Blue Light of Death)」の略称で、PS4を起動した際に青いランプが一瞬つくだけで起動が出来なくなる、という不具合のことです。
ちなみにメーカー等が発表している正式名称ではなく、ユーザー間で使われている俗称です。
何が原因で発生するのかははっきりと特定されていませんが、本体基板のGPUの半田が割れたり、電源ユニットが異常をきたしていたりなど、内部的に何らかの不具合が発生している時に起きやすい現象とされています。
TVに出力できない
据え置き型のゲーム機からTV画面に出力するためには、HDMI端子というものを使用して出力します。
しかし、PS4側のHDMI端子に異常があると、TVと接続してもゲーム画面が映らないといった不具合が発生してしまいます。
PS4本体のランプの色が青色に点滅した状態が続いていると、HDMI端子による出力異常の可能性が高くなります。
PS4をできるだけ長く使用するための方法

高価なゲーム機であるPlayStation4ですから、できるだけ長く使用したいものです。
以下に、PS4を長持ちさせるための対策法について紹介していきます。
床に直置きしない
床に直置きしてしまうと、排熱がうまくいかなくなり本体に熱がこもってしまうことがあります。
そのため、PS4の下に「すのこ」などの通気性のよいものを敷くようにしてください。
通気性を良くすることで排熱されやすくなり、本体にかかる負荷を軽減することができます。
面倒だとは思いますが、こういった細かいケアを意識することでPS4の寿命は確実に延びます。
なお、PS4を縦置きするか横置きするかという論争もありますが、通気性の良いすのこなどを設置することで排熱に関しての問題がクリアされるため、横置きで問題ありません。
逆に縦置きにしてしまうと、PS4の転倒リスクが高まってしまいます。
精密機械に物理的な衝撃が加わってしまうことはマイナスでしかないので、なるべく避けるようにしましょう。
また、床に直置きしないことで虫が混入するリスクも低くなります。
湿気のある場所での使用・保管を避ける
風呂場の近くや加湿器の近くでPS4を使用したり、保管したりすることは避けてください。
すべての精密機器において、湿気は大敵です。
できるだけ乾燥した場所で使用・保管するようにしましょう。
ホコリに気を付ける
湿気同様、ホコリもPS4の寿命を縮めてしまいます。
本体にホコリが吸着してしまうことにより排熱効果が下がってしまい、熱がこもりやすくなることで本体内部に負荷をかけてしまうからです。
また、ホコリには帯電性があり、静電気をまとったままケーブル差込口などに付着してしまうと、故障の原因にもなってしまいます。
ホコリが舞い散るような環境でプレイするのではなく、部屋をできるだけ清潔な状態に保ち、ホコリによるダメージからPS4を守るようにしてください。
また保管する際も、ホコリまみれの場所は避けるようにしてください。
長時間のプレイを控える
面白いゲームに出会うとついつい長々とプレイしてしまいがちですが、5~10時間も続けて遊んでしまうのは考え物です。
電化製品であるPS4は消耗品であり、連続使用する時間が長いほど消耗度合いは増していきます。
健康のためにもPS4のためにも、適度なプレイ時間と適度な休憩を心掛けるべきでしょう。
そして休憩の際は、しっかり電源を落とすようにしてください。
スリープ設定を解除しない
PS4の場合、デフォルトで3時間経つとスリープ状態になるように設定されています。
しかし、ヘビーユーザーの場合はいちいちスリープ状態になることを面倒に感じ、この設定を外してしまうことがあります。
しかしスリープ設定を解除してしまうと、常に高い電力が供給されている状態が続いてしまい、本体内に熱がこもりやすくなってしまうのです。
PS4に熱による負荷をかけすぎないようにするためにも、多少面倒であろうとスリープ設定は解除しないようにしましょう。
PS4の近くでタバコを吸わない
PS4の近くでタバコを吸い続けると、PS4にヤニが付着し、通風孔を狭くしてしまったり塞いでしまったりする場合があります。
繰り返しお伝えしている通り、PS4を始めとする電化製品は熱に弱いもの。
ヤニによって通風孔が塞がれてしまうと通気性が低下し、本体内に熱がこもりやすくなってしまいます。
タバコを吸う時は一旦外に出るなどの工夫をして、PS4にヤニが付着してしまわないように注意してください。
直射日光に当てない
プレイ中も保管中も、直射日光に当たるような場所にPS4を置くのはやめましょう。
使用中でもないのに本体が熱くなってしまい、各パーツに負荷がかかってしまいます。
保管場所は、暗くて通気性がよく、ホコリの少ない場所がベストです。
適度なペースでのホコリ除去掃除
どんなに丁寧にPS4を扱い、保管場所などに気を配ったとしても、ホコリをまったく寄せ付けないということは不可能です。
従って、定期的にPS4のホコリ除去掃除を行なうようにしてください。
本体の掃除はそこまで頻繁にやる必要はなく、良い環境で使用・保管しているようならば、半年に一度程度のペースで充分でしょう。
なお掃除の際は、ハタキや掃除機を使ってホコリを除去するのがよいです。
特に通風孔や差込口といったあたりは念入りかつ丁寧に掃除してください。
こういった場所を掃除する時にウェットティッシュなどの湿気を帯びた紙や布を使用するのは厳禁ですので、注意が必要です。
こまめなシステムバージョンアップ
システムバージョンアップがある際は、速やかに行うようにしてください。
メーカーとしても、理由があるからバージョンアップを行なっているのですから、放置することは危険です。
例えば、システムの脆弱性を改善してセキュリティを強化したり、バグの改修をしたり、新たな機能を追加したり、といったバージョンアップが行われています。
常に最新のバージョンにアップデートして使うことで、予期せぬ不具合を回避できる可能性が高まります。
システムソフトウェアのバージョンについては、[設定]>[システム]>[システム情報]から確認できます。
参考 : PS4®の調子が悪い……困った時に試しておきたい改善策【知っトク! PlayStation®】
PS4が動かなくなってしまった時の対処法

PS4も消耗品であり、消耗品である以上はいずれ寿命が訪れます。
PS4が動かなくなってしまった場合には「修理する」という方法もありますが、一概に修理という方法がよいとも言えません。
PS4を修理する場合
以下がPS4の場合の修理費用です。
【オンライン修理の場合】
| 修理内容 | 費用 |
|---|---|
| ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)の交換 | 4,950円(税込) |
| 外装部品の交換 | 5,500円(税込) |
| 電源ブロックの交換 | 6,600円(税込) |
| メイン基板の交換 | 13,750円(税込) |
| ディスク読取、駆動ブロックの修理・交換 | 7,150円(税込) |
| ハードディスクの修理・交換 | 7,150円(税込) |
【オンライン修理以外の場合】
| 修理内容 | 費用 |
|---|---|
| ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)の交換 | 4,950円(税込) |
| 外装部品の交換 | 6,600円(税込) |
| 電源ブロックの交換 | 7,700円(税込) |
| メイン基板の交換 | 15,950円(税込) |
| ディスク読取、駆動ブロックの修理・交換 | 8,250円(税込) |
| ハードディスクの修理・交換 | 8,250円(税込) |
参考:オンライン修理受付サービス | PlayStation4
ご覧の通り、故障箇所によってはそこそこの費用がかかってしまう上、他のパーツの寿命も近いかもしれません。
一度修理したところで、すぐに別のパーツが壊れてまた修理に出す、といったパターンも考えられます。
PS4を買い替える場合
ある程度使用したPS4であれば、無理に修理しようとせず、いっそのこと買い替えてしまう方が結果的に安上がりとなる可能性も高いので、新品への買い替えも一つの手です。
なお、買い替える場合は古いPS4を捨てることになると思いますが、PS4を捨てる時には以下について忘れずに行なってください。
- 機能認証の解除
- データのバップアップ
- 本体の初期化
- アカウントの登録情報削除
参考:PlayStation機器を手放す / 廃棄するときの注意点 (日本)
PS4の初期化に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
PS4を売る前にはフル初期化!クイックとの違いや復元方法も解説>>
ただ、本体の初期化などが面倒だったり、やり方がわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そもそもPS4を捨てる場合は家庭ゴミとしては出せないので、基本的に有料となってしまいます。
しかしゲーム機処分.comならば、事前連絡などのやりとりが一切不要で、梱包して送るだけでOKです。
データ消去も処分もすべて行なってくれた上で、費用は一切かかりません。
まとめ:基本的なことに気を配るだけでPS4は長持ちする
10年設計となっている昨今の電化製品。
PS4も電化製品なので、使用方法や管理方法に気を配ることで長持ちさせることができます。
- ホコリだらけの場所や湿気の多い場所で遊んだり保管したりしない
- 床に直置きせずに「すのこ」などを敷く
- 定期的にPS4を掃除する
- 長時間プレイを避ける
- PS4の近くでタバコを吸わない
- こまめにバージョンアップする
こういった基本的なことを忘れずに行なうだけで、PS4の寿命は確実に延びていきます。
修理や買い替えが発生することなく10年もたせるためにも、面倒ではありますが上記のような対策を日々心掛けてください。
PlayStation(プレイステーション)を無料処分できます>>

監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
普段、電源ボタンを押せば当たり前のように起動していたパソコンが、突如正常に立ち上がらなくなってしまったという経験のある方も多いのではないでしょうか?
しかし、このような場合はしっかりと焦らずに対応することが重要です。
この記事では、もしそんな事態に陥ってしまっても焦らずに済むように、dynabookが突如起動しなくなった時の対処法や、立ち上がらない原因について紹介していきます。
【この記事でわかること】
- dynabookに不具合がある時にまず取るべき行動
- dynabookが起動しなくなる原因
- dynabookが起動しない場合の対処法

dynabookの故障が疑われる場合にまず取るべき行動

国内のノートパソコンの中で、いまだに高い人気を誇るブランド「dynabook」。
2018年までは東芝から販売されていたノートパソコンですが、東芝がパソコン事業から撤退することになり、事業のほとんどをシャープが受け継ぎました。
2020年には完全にシャープに株式を売却し、名実ともにシャープのブランドとなっています。
「起動しない」・「電源が入らない」といったdynabookブランドのノートパソコンに関する不具合については、まずDynabook株式会社の公式サイトのサポートページを開き、トラブル内容について調べてみてください。
FAQも充実していますし、過去のトラブルに関する回答を検索する機能もあるため、多くのトラブルは公式サイトを見ることで解決します。
参考 : dynabook サポート | dynabook(ダイナブック公式)
ただ、検索に慣れていない方や、パソコン初心者の方などには自己解決が難しい場合もありますので、以下にて、dynabookが起動しない原因や対処法について噛み砕いて解説していきます。
dynabookが起動しない主な原因

dynabookが起動しなくなる原因は、主に以下のようなものです。
HDDやSSDの寿命
HDDやSSDは無限に使用できるわけではありません。
HDDの場合は約3~4年、SSDの場合は約5年が平均寿命だと言われています。
この平均寿命は、あくまで一般的な使用方法だった時の話ですので、使い方が悪ければ当然HDDやSSDの寿命は短くなります。
高温多湿な環境でdynabookの使用を続けたり、常に電源をつけっぱなしにしていたり、ホコリ除去などのメンテナンスを怠っていたりすれば、平均寿命を遥かに下回る年数で故障してしまう可能性も充分にあります。
パソコンを起動させるためのシステムが入っているのもHDDやSSDですから、これらが寿命を迎えてしまえばパソコンは立ち上がらなくなってしまいます。
ハードディスクの寿命は3~4年!故障の前兆や症状、診断方法を解説>>
SSDの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
【SSDの寿命は5年】故障前のSSDの症状や延命方法を徹底解説>>
重要パーツの故障
電源ユニットやマザーボードといった重要パーツが故障してしまった場合も、dynabookが正常に起動しなくなる原因となります。
こうしたパーツも経年劣化する上、使用方法や環境が悪ければ劣化スピードも速まります。
マザーボード故障時の症状とは?4大原因と2つの調べ方を解説>>
また、ケーブルの断線や差込口の変形といった可能性も疑われます。
電源ケーブルは、重い物の下敷きになったり、力任せに挿しこんだりすることで断線や変形を招いてしまうことがあり、それが原因で正常な電力供給が行われなくなり、起動しなくなるというケースもあります。
ソフトウェアの障害
HDDやSSD、電源ユニットやマザーボードといったハードウェアに問題がなくとも、ソフトウェアに障害が発生していると、パソコンは正常に起動できなくなってしまいます。
一番多いのはOSの不具合です。
なんらかの原因でOSに障害が発生し、パソコンを起動させるためのプログラムが正しく動かなくなっている場合があります。
dynabookが起動しない時の症状別の対処法

dynabookが起動しない原因は多岐に渡ります。
以下に、症状別の対処法について解説していきます。
画面が真っ暗な場合
同じ「画面が真っ暗」という状態でも、電源ボタンを押した後のdynabookの挙動によって対処法が異なってきます。
まず、dynabookの側面部分にあるLEDランプを確認してください。
LEDランプが点灯していない
電源ボタンを押しても、電源が入っているかどうかを示すLEDランプが点灯しない場合は、電気系統のトラブルにより通電自体していないということになります。
考えられる原因は以下のようなものです。
- ケーブルがしっかりと挿さっていない
- 電源ユニットの故障
- マザーボードの故障
- ケーブルの断線
- バッテリーの異常
まず確認すべきは、電源ケーブルがしっかりと挿さっているかどうかです。
「そんな単純なことが原因のわけがない」という思い込みから、挿し込みが緩いという可能性を考慮せずに慌ててしまうパターンはありがちです。
ケーブルがしっかり挿さっているのにLEDランプが点灯しない、つまり通電しないという場合は、何かしらのパーツにて異常が発生している可能性が非常に高いです。
最もあり得るのは、バッテリーに異常が発生しているパターンです。
この場合は、まずdynabookに挿さっているケーブルをすべて外してから、パソコンを裏返してバッテリーを抜いてください。
それから、ACアダプターのみを接続して電源ボタンを押し、これで通電すればバッテリーに何らかの異常があるということになります。
これでも解決しない場合は、電源ユニットやマザーボードの故障、もしくはケーブルの断線が疑われるので、修理が必要となる場合があります。
パソコン初心者では難しい作業となるので、まずは公式サポートに相談してください。
参考 : dynabook サポート | dynabook(ダイナブック公式)
また、熱暴走によって電源が入らないという可能性もあります。
dynabook本体を触ってみて異常に熱いようならば、しばらく放置して熱が充分に下がったことを確認してから電源を入れてみてください。
LEDランプが点灯している
LEDランプが点灯していれば、通電はしているということになります。
通電しているのに起動しない原因の多くは、メモリが帯電してしまっていることです。
メモリの抜き差しをするだけで溜まっていた静電気が放電され、普通に立ち上がるようになることもありますので是非試してみてください。
また、メモリではなくdynabook本体に静電気が溜まっているケースもあります。
よって、dynabookからすべてのケーブルを抜き、10分ほど放置して放電を行なってから再度ケーブルを繋いで電源を入れると、問題なく起動することもあります。
例外パターンとして、内部的には正常なものの液晶が破損している、というケースもあります。
外付けのディスプレイがあれば、dynabookにディスプレイケーブルを挿し込んでから電源を入れてみてください。
外付けディスプレイの方で普通に起動できていれば、液晶の破損が原因だと特定できます。
上記の対策を施しても直らない場合は、メモリやマザーボードなどの重要パーツが故障している可能性が高いです。
dynabookのロゴが出たまま進まない場合
このケースも、「LEDランプが点灯している状態で画面が真っ暗」という場合と同じ対処方法となります。
通電はできているものの正常に起動しない、という状態ですので、原因は同じであることが多いです。
そのため、まずはバッテリーを外してACアダプターのみ接続してから電源を入れ、それでも電源が入らないようならdynabookの放電を行なってください。
これで直らなければ、重要パーツの故障が疑われます。
「自動修復を開始しています」のメッセージが出る場合
dynabookのロゴの下に「自動修復を開始しています」のメッセージが表示される場合は、とりあえずしばらく待ってみてください。
これは故障ではなく、停電や強制終了などの予期しないシャットダウンが原因で発生したシステムトラブルを、Windowsが自ら修復しようとする時に出るメッセージですので、待っていれば自動修復が完了し、普通に起動することも多いです。
待ち時間が長かったり、自動修復が繰り返されたりすることもありますが、我慢強く待ちましょう。
しかし、待った結果「PCを修復できませんでした」・「PCが正常に起動しませんでした」といったメッセージが出た場合は、システムの復元が必要です。
システムの復元方法は、使用しているWindowsのバージョンによって異なります。
Windows 10
- 自動修復失敗画面に表示されている「詳細オプション」ボタンをクリック
- 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」ボタンをクリック
- トラブルシューティングから「詳細オプション」⇒「システムの復元」を選択
- 該当するアカウントを選択してからパスワードを入力
- 「システムファイルと設定の復元」画面へ遷移したら「次へ」をクリック
- 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します」の画面で、復元したい日付を選択し、「次へ」をクリック
- 「復元ポイントの確認」画面で復元ポイントを確認し、OKなら「完了」をクリック
- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」のメッセージに対して「はい」をクリック
- システム復元が完了するまで待ち、完了後に「再起動」のボタンをクリック
これでWindows10におけるシステムの復元は完了です。
完了するまでかなり長い時間がかかる場合もありますが、復元中は下手にパソコンをいじらず、ひたすら待ちましょう。
Windows 8.1
Windows8.1の自動修復は、一度電源を落とすところから始めます。
- 電源を落とす
- 電源を入れ、すぐにキーボードの「0」キー(かな入力の「わ」キー)を連打する。パスワードの入力を求められた場合はパスワードを入力する
- 「HDDリカバリーをスタートします」のメッセージが表示されたら[はい]を選択してENTERキーを押す(このメッセージが表示されない場合もある)
- 「オプションの選択」画面がから「トラブルシューティング」をクリック
- 「トラブルシューティング」画面の「詳細オプション」をクリック
- 「詳細オプション」画面の「システムの復元」をクリック
- 「システムの復元」画面で、該当するアカウントを選択してからパスワードを入力
- 「システムファイルと設定の復元」画面で「次へ」をクリック
- 復元したい状態の復元ポイントをクリックし、「次へ」をクリック
- 「復元ポイントの確認」画面で「完了」をクリック
- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」のメッセージに対して「はい」をクリック
- システム復元が完了するまで待ち、完了後に「再起動」のボタンをクリック
参考:「システムの復元」「トラブルシューティング」からコンピューターを以前の状態に復元する方法<Windows 8.1>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)
Windows 7
Windows7の自動修復も、まずは電源を落とします。
- 電源を落とす
- 電源を入れた直後、Windowsのロゴが表示される前にキーボードのF8キーを連打
- 「詳細ブートオプション」画面が表示されれば成功。キーボードの矢印キーを使って「コンピューターの修復」を選択し、ENTERキーを押す
- しばらくすると「システム回復オプション」画面が表示されるので、キーボード入力方式を「日本語」にして「次へ」をクリック
- 「回復オプションにアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンしてください。コマンドプロンプトにアクセスするには、管理者アカウントでログオンしてください」というメッセージが表示されるので、「ユーザー名」のところにある「▼」をクリックして自分のアカウントを選択し、パスワードを入力
- 「回復ツール選択画面」で「システムの復元」をクリック
- 「システムの復元」画面が表示されるので、画面の指示に従って「次へ」をクリックしていくと復元が始まる
- 復元完了後は自動で再起動が行われる
参考:「コンピューターの修復」を使用して「システムの復元」を起動する方法<Windows(R)7>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)
ブルースクリーンになってしまう場合
パソコンの画面が真っ青になり、その青い画面に白い文字が表示されて操作不能となってしまう恐怖の現象、ブルースクリーン。
発生原因は、重要パーツの故障やソフトウェアトラブル、ウイルス感染など多岐に渡り、ブルースクリーンが出現しただけでは不具合のある場所はわかりません。
ブルースクリーン状態となった場合は何も操作ができないので、とりあえず電源ボタンを長押しして強制終了するしかありません。
その後もう一度電源を入れると普通に立ち上がることもありますが、何かしらのトラブルが発生している可能性が高く、いつdynabookが動かなくなるかわからないので必ずバックアップを取っておきましょう。
「ブルースクリーン出現後にバックアップを取った」、もしくは「何度起動してもブルースクリーンになってしまう」という場合には、リカバリを試みてください。
リカバリとは、パソコンを初期状態に戻すことです。
つまり、パソコン内にあるデータはすべて消去されてしまいますのでご注意ください。
以下、Windows10におけるリカバリ手順について掲載します。
- タスクバーの「スタート」をクリックしてから、「設定(歯車マーク)」ボタンをクリック
- 設定画面にある「更新とセキュリティ」をクリック
- 更新とセキュリティ画面の「回復」をクリック
- 回復画面の「このPCを初期状態に戻す」のところにある「開始する」をクリック
- 「オプションを選んでください」と表示されている画面で、「すべて削除する」をクリック
- 「ドライブのクリーニングも実行しますか?」と表示されている画面で、「ファイルの削除のみ行う」をクリック
- Windows10が最新バージョンの場合は、「警告!このPCは最近Windows 10にアップグレードされました。このPCを初期状態に戻しても、アップグレードを取り消してWindowsの以前のバージョンに戻すことはできません」のメッセージが表示されるので、「次へ」をクリック
- 「準備しています」の画面がしばらく続いた後、「このPCを初期状態に戻す準備ができました」と表示されるので、「初期状態に戻す」をクリック
- 自動的に再起動され、パソコンの初期化が行われる
- 初期化完了後は自動でWindows10の再インストールが始まる
- 再インストール完了後、画面の指示に従って進んでいけば完了
参考:このPCを初期状態に戻す”機能を使用してWindowsを再インストールする方法<Windows 10>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)
ブルースクリーンに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法>>
真っ暗な画面に白文字が表示される場合
画面がただ真っ暗なだけでなく、黒い画面に白文字が表示されたまま正常に起動しないというケースもあります。
表示される白文字は以下のようなものです。
- Press F1 to Resume
- Strike the F1 Key to continue
- Boot Failure
- Fan Error
この白文字は、エラーの原因が表示されていたり、どのような行動を取ればいいのかを指示していたりします。
例えば上記の1.と2.の「Press F1 to Resume」や「Strike the F1 Key to continue」ならば、どちらも「F1キーを押してください」というような意味なので、指示された通りF1キーを押すだけで正常に起動することがほとんどです。
また、3.の「Boot Failure」ならば単に「起動に失敗した」ということを表しており、4.の「Fan Error」ならば「冷却ファンに異常がある」ということを表しています。
エラー箇所が指摘されている場合は、エラーメッセージをメモしてから一旦再起動してみましょう。
再起動するだけで問題なく動作することもあります。
再起動しても同じエラーが出たり、うまく起動しなかったりする場合は、エラー箇所の点検を行なってください。
まとめ:不具合発生時は、まずdynabook公式サポートへ

起動しないという不具合だけでなく、dynabookに何かしらのトラブルが発生した場合は、まず公式のサポートページを参照すべきです。
参考 : dynabook サポート | dynabook(ダイナブック公式)
dynabookに関するトラブル解決のためのFAQや、ユーザーから寄せられた過去の不具合に対する公式回答が大量にログとして残っているため、非常に情報量が豊富です。
公式サポートサイトをじっくり確認するだけで、抱えている問題が解決することも珍しくありません。
とはいえ、パソコンは消耗品です。
何年も使っていれば、自分で対処できるレベルの不具合ではなく、専門業者へ有料で依頼しなければ直らないような故障である可能性も高くなってきます。
そして使用年数が長いほど各パーツの消耗も激しく、修理費用は高くなりやすい上、修理直後にまた別の箇所が故障した、というようなパターンも多いです。
従って、ある程度の年数を使っている場合は、いっそのことパソコンを買い替えてしまう方が長い目で見ると安上がりかもしれません。
なお不要になったパソコンを廃棄する際は、「パソコン廃棄.com」を利用すると便利です。
費用が一切かからない上、事前のやり取りも一切不要。
ただ壊れたパソコンを梱包してパソコン廃棄.comに送るだけでOKとなっています。


監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
マザーボードは、多くのパーツが接続されたパソコンの土台のようなもので、寿命が来るとパソコンは正常に動作しません。
しかしパソコンの不具合は、複数のパーツの故障が原因となり、マザーボードの寿命を見極めるのは難しいことです。
そこでこの記事では、マザーボードの寿命の年数や症状、診断方法などを解説します。寿命を迎えた際の交換方法も解説しますので、参考にしてください。
この記事でわかること
- マザーボードの寿命は3~5年
- マザーボードの寿命を診断するには最小構成で起動を試す
- マザーボードの電池交換の方法
- マザーボードの寿命を延ばすためには定期的にメンテナンスが大切
- マザーボードの交換方法

マザーボードはパソコンに必須の部品

マザーボードは、どんなパソコンにも必ず搭載されている大きな基盤のことで、メインボードやシステムボードとも言います。
マザーボードには電源やCPU、メモリー、その他周辺機器などが接続されており、パソコンの土台となる部品です。
その役割は、各部品に電源を供給したり、部品同士の情報の伝達を手助けし、各部品を管理することです。
寿命が来ると接続しているCPUやメモリー、マウス、キーボードなどの周辺機器は機能できなくなります。
マザーボードの寿命は何年?

3~5年程度と言われています。
寿命が来るとパソコンが急に起動できなくなり、データの復元が簡単にはできなくなる可能性もあります。寿命を迎える前に対処できるように、寿命の時期や原因を知っておくことも大切です。
コンデンサの寿命
マザーボードの寿命に関係が深い部品が電解コンデンサです。
電解コンデンサは、マザーボードに付属している部品で、パソコンが安定して動作するための蓄電池の役割をします。電源出力のわずかな乱れを調整し、ノイズの発生を抑えます。
寿命が来るとコンデンサが膨らみ、一見してわかるようになります。そのまま放置して使用し続けるとコンデンサの中の電解液が洩れ、異臭や発煙の原因となります。
電解コンデンサの寿命は、温度を65℃として32,000時間でパソコンを24時間稼働させた場合3. 5年です。電解コンデンサの寿命はマザーボードの寿命と同じと言われるほど重要な部品です。
電池の寿命
マザーボードの中には、ボタン電池が入っています。
電池ですから、もちろん寿命があり電池切れすると不具合が起こります。電池の寿命は使い方にもよりますが、約3年程度です。
マザーボードの電池は、BIOSの電源として使用されます。BIOSは、パソコンに接続された周辺機器を制御するためのソフトで、電源によって記録されている情報を保持しています。
電池が切れるとBIOSへの電源供給ができなくなり、保持された情報が失われます。そのため、起動しない、フリーズするなどの症状が起こります。
パソコンの使用時間にも関係する
マザーボードの寿命は、パソコンの使用環境や使用時間によって変動します。
電解コンデンサの寿命は、約32,000時間。毎日24時間、ハードにパソコンを使用する人は3. 5年で寿命を迎えます。
しかし、その半分の12時間毎日パソコンを使う人なら7年間、毎日6時間パソコンを使う人は15年で寿命を迎える計算になります。使用環境によって異なるため、定期的に状態をチェックしましょう。
パソコンの寿命に関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
パソコンの平均寿命を解説!寿命がきたときの症状と長持ちのコツ>>
マザーボードが寿命を迎えると起こる症状

マザーボードが寿命を迎えると、パソコンに不調が起こります。ここでは、寿命を迎えた場合に起こりやすい症状を紹介します。
ただし、パソコンの不調は1つのパーツだけに起因するものではありません。マザーボード以外の故障でも、下記の不具合が起こることもあります。たとえば、パソコンのフリーズはハードディスクやウイルスが原因となっている可能性も。
他の原因に心当たりがない場合は、マザーボードを調べてみましょう。
電源が入らない
最も多い症状はパソコンの電源が入らなくなることです。電源スイッチを押しても電源が入らない場合は、マザーボードの寿命かもしれません。
また電源ランプが点灯しても起動しない、一瞬だけランプがついて電源が切れるなどもよくある症状です。
これらの症状はある日突然起こることもありますが、徐々に症状が悪化することもあります。最終的には何も反応しなくなるので、症状が現れたら早めに対処しましょう。
電源が入らない場合は、電源ユニットの故障も考えられるので同時に調べてみましょう。
パソコンの電源が入らないことに関しては、こちらでも詳しく紹介しています。
パソコンの電源がつかない原因は?ランプはつくなど症状別の対処法を紹介>>
頻繁にフリーズする
パソコンが頻繁にフリーズする場合は、マザーボードの寿命かもしれません。
ただし、パソコンのフリーズは、特有の症状ではありません。ハードディスクの故障やウイルスなどの原因もあるため、ハードディスクの確認やウイルスチェックも行いましょう。
パソコンのフリーズに関しては、こちらのの記事でも詳しく紹介しています。
パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>
電源が落ちる
電解コンデンサが故障すると、突然電源が落ちることがあります。
CPUの温度上昇で電源が落ちる場合は、パソコンに負荷がかかると電源が落ちるなどのある程度の法則がありますが、マザーボードの寿命が原因の場合、予期せず突然電源が落ちることが多くなります。
電源が落ちる不具合は、CPUの温度上昇や電源ユニットの故障、電力の共有不足などの原因も考えられます。それぞれ確認しましょう。
ビープ音が鳴る
ビープ音とは、パソコンから鳴る「ピー、ピー」という機械音。たとえば、dell製のノートパソコンでは、ビープ音が1回鳴るとマザーボードやBIOSの故障の可能性があります。
ビープ音はマザーボードが不具合を感知して鳴らすものなので、逆にビープ音が一切ならない場合もマザーボードの寿命の可能性が。
ただしビープ音は、他の部品の故障でも鳴ります。ビープ音の鳴り方をよく聞いて、故障の原因を見つけましょう。
焦げ臭いにおいがする
基盤周辺にホコリが溜まる、水分を含むなどでショートして、周辺パーツが焼き付き焦げ臭いにおいが発生します。
また、電解コンデンサが破裂や液漏れした場合、電源の安定化ができなくなり発火することもあります。電解コンデンサの液漏れでは、酸っぱい異臭が、破裂した場合は破裂音や焦げ臭いにおいがします。
焦げ臭いにおいは、マザーボード周辺が異常に高温になっている証拠です。メモリやCPU、CPUクーラーなどが故障して発熱している可能性もあるため、パソコン内をよく確認しましょう。
ディスプレイが映らない、乱れる
電解コンデンサは電源を蓄電して出力をコントロールしています。電源の出力のわずかな乱れをコントロールして、画面の乱れを抑えます。
ディスプレイが映らないのは、配線の不備や、モニター、グラフィックボードの故障が原因のことも多いのですが、マザーボードの寿命が原因のこともあります。
マザーボードにはパソコンの起動を制御するBIOSが搭載されています。寿命を迎えると、BIOSが正常に動作しないため画面の表示ができなくなります。
電源を入れた後に画面が乱れる、画面が乱れた後に電源が切れるなどの症状がある場合は、マザーボードの寿命を疑いましょう。
パソコンの時計がずれる
パソコンの時計はBIOSによって制御されています。電池の寿命によってBIOSへの電力が絶たれた場合、時間や年月日が初期設定にリセットされます。
パソコンを再起動しても時計のズレが改善しない場合は、電源を切りしばらく放置してから再び電源をつけましょう。時計の設定を手動で直しても、直らない場合はマザーボードの電池切れの可能性が高いでしょう。
マザーボードの寿命の診断方法
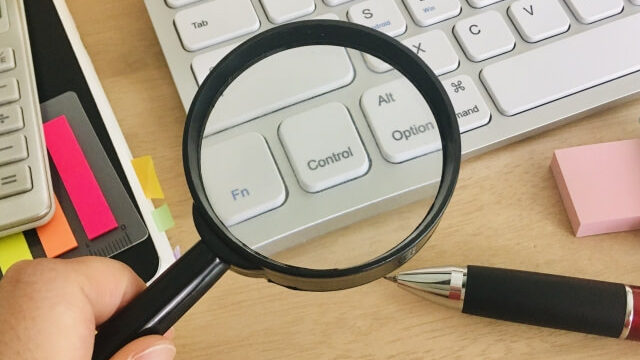
パソコンの不具合の原因は1つではありません。原因を特定するためには、それぞれのパーツを確認する必要があります。
ここでは、マザーボードの寿命を診断する方法を紹介します。
最小構成で起動してみる
パソコンの不具合の原因を特定するには、パソコンを最小構成で起動することが有効です。
最小構成は、マザーボード、メモリ、CPUで、パソコンを起動させるために最低限必要な構成です。
マザーボードが故障していれば、パソコンは起動しません。最小構成で起動した場合は、最小構成以外のパーツの故障が原因の可能性が高いでしょう。
コンデンサをチェックしてみる
最小構成でエラーが出たら、マザーボードの寿命を疑いましょう。
寿命を診断するためには、パソコンの蓋を開けてマザーボードを目視して、電解コンデンサの状態を確認します。
電解コンデンサが、変色する、膨らむ、破裂して液漏れするなどの異常があればマザーボードの寿命です。コンデンサの電解液が液漏れしていると、マザーボードが腐食していることもあります。
マザーボードの電池を交換する方法

マザーボードの電池は、「BIOS」や「UEFI」の情報を保つために大切なパーツ。電池からの電源供給によって、パソコンの電源を切ってもBIOSなどに設定された情報が保持できます。
BIOSやUEFIは、起動直後に立ち上がりOSを読み込みます。そのため、電池が寿命を迎えると、OSが起動しないなどの不具合が発生します。
電池が寿命を迎えても、交換することによって不具合を改善可能。
電池寿命が来たときの交換方法を紹介します。
電池交換の方法
マザーボードの電池は、自分で交換可能です。
しかし、パソコンを解体してマザーボードの電池を探す必要があるため、故障のリスクもあります。電池交換に自信がない場合は、業者に依頼するのも1つです。
電池交換に必要なものは次の4点。
- 電池残量測定器
- 交換する電池
- マイナスドライバー
- 静電気防止手袋(必要であれば)
交換する電池は、パソコンを開けて電池の型番を確認してから購入しましょう。多くの場合はボタン電池ですが、間違った電池を取り付けると故障の原因になります。
電池交換の手順
- パソコンの電源を切りコンセントを抜く
- カバーを取り外す
- 電池の型番を確認して交換
マザーボードの電池交換の注意点
パソコンは精密機械のため、慎重に扱う必要があります。電池交換の際には他のパーツに触れないように細心の注意を払いましょう。
その他、注意することを紹介します。
電源を必ず切る
電源が入ったまま作業すると、感電やマザーボードの破損のリスクがあります。
念のため、接続している周辺機器も取り外してから作業しましょう。
静電気対策
マザーボードは静電気に弱く、少しの静電気でも悪影響を与えることもあります。メモリなどは少しの静電気で使いものにならなくなることも。
静電気防止手袋を使う、事前に金属に触れて静電気を逃してから作業するなど、静電気対策をしましょう。
マザーボードは慎重に扱う
電池交換の際にマザーボードを傷つけると、電源が入らないなど不具合が起こる可能性があるため慎重に扱いましょう。
電池交換の際には、電池の向きや型番などをしっかり確認しましょう。異なる種類の電池を取り付けようとして無理に押し込むと破損する可能性もあります。
パソコンが作動しない場合はCMOSクリアを実行する
CMOSには、BIOSやUEFIの情報が保存されています。CMOSクリアを実行すると、BIOSの設定情報が初期化され、OSが起動しない、フリーズするなどの問題も解決できます。
CMOSクリアを実行するには、マザーボードの電池を外して15分程度放置するだけです。機種によっては1時間程度放置が必要な場合があるため、1時間放置すれば安心です。
CMOSクリアを実行するとパソコンによっては、BIOSの再設定が必要な場合があります。BIOSの初期設定の詳細が必要になるため、CMOSクリア前にメモしておきましょう。
CMOSクリアで、BIOSやUEFIを初期化するとパソコンがうまく作動しないリスクもあるため、慎重に行いましょう。
マザーボードの寿命を延ばす方法

マザーボードの寿命には幅があり、パソコンを使用する環境に左右されます。
マザーボードの寿命を延ばすための方法を紹介します。
室内環境を整える
急激な温度差や湿度は、パソコンの大敵です。
直射日光が当たる窓際などにパソコンを放置すると、パソコン内の温度が上昇します。とくに電解コンデンサは温度が10℃上がると寿命が半分になるとも言われています。反対に、温度が10℃下がると寿命は2倍に。
また湿度が高い場所も要注意。急激な温度差がある場所も、パソコン内に結露が発生するため注意が必要です。パソコンは水分に弱く湿気や結露によって、マザーボードが腐食する原因にもなります。
室内環境を整え、高温・多湿の場所でのパソコンの使用を避けることで、マザーボードの寿命が延びます。
パソコン内のホコリを掃除する
パソコン内にホコリが溜まると、パソコン内に熱がこもり熱暴走を起こす原因になります。ホコリが原因でマザーボードがショートする危険もあります。
パソコンの故障の原因の多くはホコリが関係しています。とくにホコリが溜まりやすいのは、電源やファンの周りです。エアダスターなどでホコリをきれいに掃除しましょう。
パソコン内部だけでなく、ファンの換気口なども定期的に掃除してパソコンの冷却効果を保ちましょう。
なるべく衝撃を与えない
パソコンは精密機械のため、衝撃にはとても敏感です。
パソコンを落とす、壁にぶつけるなどの衝撃を与えると、マザーボードが破損、接続しているパーツが外れることがあります。
また雷が落ちたり、水をこぼしたりなどでマザーボードがショートし焼け焦げることもあります。ノートパソコンを持って移動する際には、保護ケースに入れるなど衝撃を与えないように工夫しましょう。
定期的にメンテナンスする
パソコンのメンテナンスをする頻度を決めておいて、定期的にメンテナンスすることも大切です。
メンテナンスの方法
- パソコンの電源を切り放電する
- ホコリを掃除する
- 「ディスククリーンアップ」で不要なファイルの削除
- 「チェックディスク」で問題を特定しファイルを修復をする
- 「ディスクデフラグ」をして保存しているデータの整理とドライブの最適化
上記のメンテナンスを定期的に行うことで、マザーボードだけでなく、パソコン全体の寿命を延ばすことが可能です。
質の良い電解コンデンサのマザーボードを選ぶ
電解コンデンサの質が良いとマザーボードは長持ちします。
電解コンデンサには耐久温度があり、高いものの方が高品質。たとえば、耐久温度が85℃の電解コンデンサよりも105℃のものの方が高品質で耐久性も高くなります。
電解コンデンサの質は、マザーボードの寿命に直結します。マザーボードの寿命をできるだけ延ばしたいなら、電解コンデンサの質に注目してマザーボードを選びましょう。
マザーボード交換費用の相場
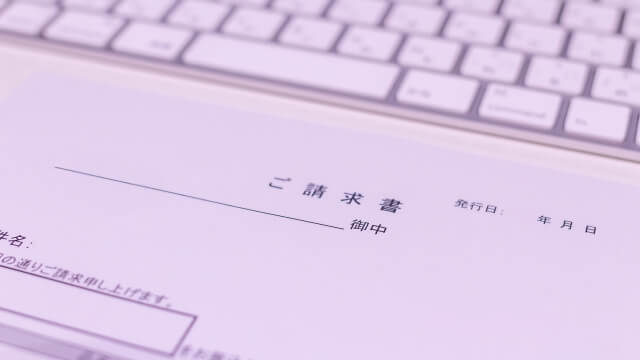
自分でマザーボードを交換する場合にかかる費用は、マザーボードの購入費用だけです。マザーボードの費用はスペックによって差があり、数千円で購入できるものから5万円程度のものもあります。
しかし、マザーボードの交換はパソコンを解体する必要があり、初心者の方には難しい場合も。
マザーボード交換は、パソコンメーカーやパソコン修理業者で交換できます。
そこでパソコン修理業者でマザーボードを交換した場合の費用の相場を紹介します。
パソコンメーカーの例
| パソコンメーカー | 修理費用 |
|---|---|
| 富士通 | 51,700円~57,420円 |
| NEC | 58,960円~62,260円 |
| dynabook | 47,700円~ |
参考:富士通 概算修理料金表
パソコン修理業者の例
| パソコン修理業者 | 修理費用 |
|---|---|
| A社 | 12,100円 |
| B社 | 11,000円 |
| C社 | 6,600円~ |
パソコンメーカーは、作業費+パーツ代の合計です。パソコン修理業者は、作業費のみでパーツ代が別途必要です。
パソコンメーカーでマザーボード交換する場合の費用の相場は、4万円から6万円程度。パソコン修理業者では、6,000円から1万円程度とマザーボードの費用がかかります。
【Windows10】マザーボードを交換する方法
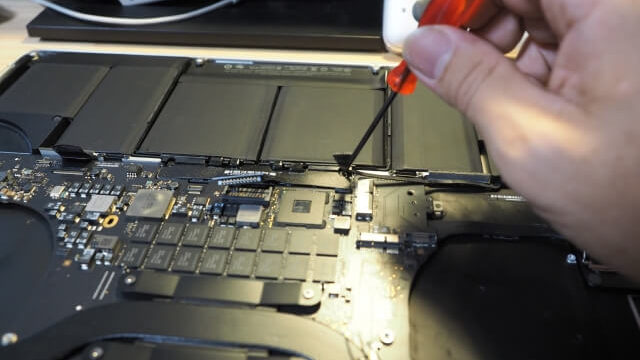
マザーボードは自分で交換も可能です。ここからは、マザーボードの交換手順や事前準備について紹介します。
交換前の事前準備
交換作業をはじめる前に、必ずしておくことがマイクロソフトアカウントとWindows10を紐づけることです。
Windows10以前のパソコンでは、OSなどのハードディスクの中身をそのままの状態でマザーボードなどのハードウェアを変更すると、起動できなくなる場合がありました。
しかし、Windows10では紐づけすることによって、マザーボード交換後も以前と同じように使用できます。マイクロソフトアカウントは無料で発行可能、持っていない場合は発行しましょう。
下記の手順でアカウントを紐づけましょう。
- 「スタート」から「設定」を開き、「アカウント」の項目を選択
- 「ユーザーの情報」画面を開き、「Microsoftアカウントでのサインインに切り替える」を選択
- マイクロソフトアカウントのメールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリック
- ローカルアカウントのパスワードを入力し(設定していない場合は空欄)次に進む
- PINを入力(設定しない場合はこの手順をスキップ)をクリックして紐づけ作業完了
- ライセンス認証部分が「Windows は、Microsoft アカウントにリンクされたデジタルライセンスによってライセンス認証されています」に変わる
- パソコンを再起動するとMicrosoftアカウントでのサインインに切り替えが完了
参考:Microsoftサポート ハードウェア構成の変更後に Windows のライセンス認証をもう一度行う
マザーボード交換で必要なもの
- 新しいマザーボード
- 静電気防止手袋(軍手)
- シリコングリス
- ライト
- プラスドライバー
- マイナスドライバー
シリコングリスはCPUクーラーとCPUの接地面に塗り、放熱の手助けをするものです。塗り替えするとCPUが長持ちします。
他にも、ピンセットや小皿があれば、落ちたネジを拾う、外したネジを入れるために便利です。
マザーボードを交換する手順
マザーボードを交換する手順は次の通りです。
マザーボードは繊細な機器のため、慎重に作業しましょう。
- パソコンの電源を切り、静電気を逃す
- 故障したマザーボードを取り外す
- I/Oシールドを取り替える
- マザーボードから順番にパーツを取り外す
- メモリを取り外す
- CPUとCPUクーラーを取り外す
- CPUクーラーにグリスを塗る
- 新しいマザーボードにパーツを取り付ける
- CPUとCPUクーラーを取り付ける
- 新しいマザーボードを取り付ける
- メモリ・ケーブルを取り付ける
- パソコンの電源を入れる
パソコンが起動したら、一度パソコンの電源を切り再び電源を入れ「F2」もしくは「DEL」キーを押し「BIOS」を呼び出しそのまま終了します。
BIOSが起動すれば、マザーボードの交換は無事完了です。交換後はWindowsを再認証しましょう。
Windows10の再認証の方法
- 設定>更新とセキュリティ>ライセンス認証に進む
- 「トラブルシューティング」をクリック
- 「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」を選択
- マイクロソフトアカウントとパスワードを入力
- サインインが完了するとリンクされているデバイスの一覧が表示される
- 「現在使用中のデバイスは、これです」にチェックを入れ「ライセンス認証」をクリック
以上で、Windows10の再認証完了です。
マザーボードを交換するときの注意点

パソコンは精密機械。マザーボードの交換は慎重に作業する必要があります。マザーボードを交換する際の注意点を紹介します。
パソコンの電源を切る
感電を防ぐために、パソコンの電源を切りコンセントも抜きましょう。電源を切ったら、パソコンのランプがすべて消えていることを確認してください。ランプがついている間は、ハードディスクなどが動作している可能性があります。
すべてのランプが消えていることを確認してから作業しましょう。マザーボードの電解コンデンサには大量の電気が蓄電されているため、できるだけ作業の2時間以上前に電源を切ると安心です。
物理破損に注意する
マザーボードには細かいパーツが多く付属しています。落とさないために十分注意が必要ですが、洋服をひっかけただけでも破損する可能性もあります。
少し触っただけでコンデンサが取れてしまうこともあるため、マザーボードの取り扱いは慎重に行いましょう。
静電気に注意する
マザーボードを交換する際には、必ず直前に静電気を逃しましょう。体や衣服などに溜まった静電気がパソコンの電子部品を故障させてしまいます。
静電気を逃す方法は、ドアノブなどの鉄製品を触る、水道水で手を洗う、帯電しやすい衣服を脱ぐなどがあります。
バックアップを取る
マザーボードを交換する前には、システムドライブのバックアップを取りましょう。マザーボードを交換するとドライバを入れ直す必要があり、システムに変更が加わります。
交換作業が失敗して元に戻すことも考慮しバックアップを必ず取っておきましょう。
システムドライブのバックアップデータがあれば、簡単に元の環境に戻せるため、安心して作業できます。
マザーボードが寿命を迎えたときの対処方法

マザーボードの寿命が来たら、マザーボードを交換する、修理する、パソコンを買い替えるなどの対処方法があります。
パソコンの状態やかかる費用などを考慮して最善の方法を選びましょう。
マザーボードを交換する
マザーボードに寿命が来ても他のパーツが問題ない場合は、マザーボードを交換することで症状が改善する可能性があります。
しかし、マザーボードが寿命の場合は、他のパーツにも不具合がある可能性もあり、マザーボードだけの故障であるかを見極める必要があります。
不要になったマザーボードは処分しましょう。
パソコン修理業者・メーカーに修理を依頼する
自分でマザーボードの交換ができない場合は、パソコン修理業者やメーカーに修理も依頼する方法もあります。
パソコン修理業者やメーカーでは、パソコン全体の不具合を診断してくれることもあるため、マザーボードだけが原因と特定できない場合も有効です。
ただし、数万円程度の費用がかかることがデメリットです。
パソコンを買い替える
マザーボードの寿命を迎えたパソコンは電源が入らないことも多く、下取りできないケースもあります。
修理に出すと高額な費用がかかることから、パソコンの買い替えを検討するのもいいでしょう。
パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>


監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
SSDとは、Solid State Drive(ソリッド・ステート・ドライブ)の略のことで、HDDよりも遥かに早い読み書きができる記憶装置のことです。
衝撃による故障リスクが低く壊れにくいため、長年使用できるという特徴があります。
ただ、壊れにくいとはいえ機械は機械。
いずれは寿命を迎えてしまいます。
この記事では、SSDの寿命や、寿命が近づいてきた時の症状、少しでも長くSSDを使用するための方法などについて解説していきます。
【この記事でわかること】
- SSDの寿命は約5年
- SSDの寿命が近づいてきた時に起こりやすい症状
- SSDの状態を調べる方法
- SSDの寿命を長持ちさせるコツ

SSDの寿命は5年ほど

SSDを一般的な形で使用した場合の寿命は、5年程度と言われています。
もちろん、使用頻度や使用環境などによって寿命は変わってきますが、大体の目安として一応覚えておくとよいでしょう。
SSDとHDDの違い
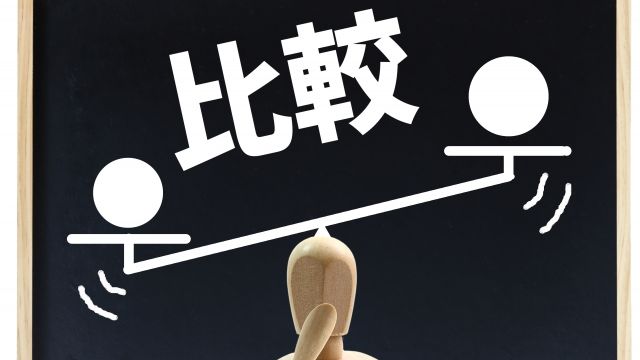
SSDとHDDには、それぞれメリットとデメリットが存在します。
一概に「処理速度の速いSSDの方が優れている」とは言えないので、メリットとデメリットを考慮しつつ、用途に合わせてSSDを使うのかHDDを使うのかを判断していくべきです。
SSDのメリット・デメリット
【SSDのメリット】
- 読み書きの処理速度が速い
- 振動や衝撃に強く壊れにくい
- 作動音があまりせず静か
- 消費する電力が少ない
- 小型で軽量
【SSDのデメリット】
- 容量が少ない
- 故障した場合のデータ復旧が困難
- 購入単価が高い
SSDは、内臓されているメモリーチップを使ってデータの読み書きを行っているため、非常に処理速度が速いです。
従って、ゲームや動画編集といった、一度に大量のメモリを要求される作業をこなすのに向いています。
ただ、HDDと比べると容量が少なく、いざ故障してしまった時のデータ復旧も難しいため、サイズの大きいデータや大事なデータを長期保存する、といった用途には向いていません。
HDDのメリット・デメリット
【HDDのメリット】
- 容量が大きいため大量のデータを保存できる
- 購入単価が安い
【HDDのデメリット】
- 読み書きの処理速度が遅い
- 振動や衝撃を受けた時に壊れやすい
- 消費電力が多い
- 作動音が大きい
- 大型で重量
HDDは、回転する円盤型の記憶装置に対して磁気データの読み書きを行うという構造になっており、SSDと比べるとデータの読み書きが遅めです。
そのため、ゲームや動画編集といった大量のメモリを要する作業には不向きです。
また、円盤は常に回転しているため音が大きく、消費電力も多くなってしまいます。
しかし、安価で容量の大きいものが手に入るため、サイズの重い動画や写真を大量に保存する、といった用途には適しています。
SSDの寿命が近づいた時の症状

SSDが登場して間もない頃は、なんの前兆もなく突然動かなくなるといった事態も珍しくありませんでしたが、現在では性能が上がり、SSDが突然寿命を迎えることは珍しくなりました。
大抵の場合は、「そろそろ限界が近い」ということを示す症状が出ます。
以下にて、SSDの寿命が近づいてきた時に起こりがちな症状を紹介していきます。
処理速度が低下して動きが遅くなる
SSDは、データの書き込みを繰り返していくことで劣化し、徐々に処理速度が遅くなっていきます。
- パソコンの起動に時間がかかる
- ファイルがなかなか開かない
- ファイルの保存が遅い
こういった症状が現れると、SSDの劣化が進んでいるサインです。
処理に耐えられずフリーズしてしまうという症状まで出てくると、寿命を迎えるのも時間の問題なので、早めにデータのバックアップを取っておくべきでしょう。
いきなり電源が落ちる
パソコン使用中に突如電源が落ちる、という症状が出始めた場合も危険です。
フリーズと同じく、SSDが処理に耐えられなくなっている証なので、いつ故障してもいいように準備をしておきましょう。
「ブートデバイスが見つかりません(Boot Device Not Found)」のエラーが発生
パソコン起動時に、真っ黒な画面に白文字で「Boot Device Not Found」という文字が表示されることがあります。
これは、SSDやHDDの起動デバイスを認識できていない、ということを表すエラーです。
何度パソコンを立ち上げようとしてもこの症状が出てしまう場合、寿命が近いというよりも、すでに寿命を迎えてしまった可能性が高いです。
ブルースクリーンの多発
ブルースクリーンとは、青い画面に白文字でエラーメッセージが表示された状態のことで、OSに何らかのトラブルが発生したことを表しています。
ブルースクリーンが発生する原因は様々ですが、その原因の一つに「SSDの不調」があります。
本来ならば滅多に発生しないブルースクリーンが頻発するようになってきたら、SSDがそろそろ限界である可能性を疑うべきでしょう。
ブルースクリーンに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法>>
SSDの寿命が縮まる原因

SSDの寿命は一定ではなく、パソコンの使用方法によって大きく変わってきます。
SSDの寿命に影響を与えるのは、主に以下のような要素です。
SSDの空き容量が少ない
SSDの空き容量が少ないと、データを整理するための処理量が無駄に増えてしまい、SSDへの負荷がかかりやすくなってしまいます。
なぜ空き容量が少ないと無駄な処理が増えてしまうのかというと、SSDが持つ「データの上書きができない」という特性のためです。
SSDの場合、パソコンを操作する人がファイルの上書きを行っても、内部的には直接上書きされるのではなく、空いている領域にデータの新規書き込みが行われます。
これを繰り返すといずれ空き容量が減っていくわけですが、その場合には、過去に上書きされたデータや削除されたデータを消去して空き領域を作り、データの書き込みを行うという処理をするようになります。
容量に余裕があれば「新規書き込みを行う」だけで済むところを、容量が乏しいと「一旦不要なデータを消去して空き領域を作ってから、その空いた領域に書き込みを行う」という処理をしなくてはならなくなり、SSDに余計な負荷をかけるようになってしまうのです。
負荷がかかるほどSSDは劣化しやすくなりますので、寿命を縮めてしまう大きな原因となります。
データの書き込み量が多い
SSDは、製品ごとに「トータルでどれくらいの書き込みが可能か」という総書き込み量があらかじめ決まっています。
決められた総書き込み量に到達してしまうと、それ以上の書き込みができなくなってしまいます。
書き込み可能な総量のことをTBW(Total Byte Written)といい、TBWに達するまでは製品を保証するというメーカーが多いです。
一例として、サムスンのSSDの製品を挙げてみます。
| 製品名 | 容量 | 保証期間/保証TBW |
|---|---|---|
| 970 PRO | 512GB | 5年または600TB TBW |
参考:サムスンSSD Limited Warranty Japanese
この製品の場合、トータルで600TBの書き込みまでは保証する、ということになります。
なお、製品ごとに決められているTBWに到達してしまうと、それ以上は書き込みができなくなってしまうのでSSDとしての役割を果たせなくなりますが、TBWはかなり余裕を持って設定されているため、よほど変わった使い方をしない限りTBWに到達することはまず考えられません。
しかしTBWに到達しなくとも、書き込みを行えば行うほど劣化が進み処理速度も落ちるので、SSDを快適に使用できる期間を判断する大きな要素であることは間違いないです。
使用環境が劣悪
パソコンのような精密機械は、以下のような環境に弱いです。
- 高温
- 湿気が多い
- ほこりだらけ
- 静電気が発生しやすい
こうした劣悪な環境で使用し続けることにより、SSDがダメージを受けやすくなってしまいます。
使用時間が長い
使用時間、すなわちパソコンに電源が入っている時間が長いほど、SSDにも負荷がかかります。
何も作業をしていなくとも、通電中はバックグラウンドで常に動作していることもあり、それだけSSDの劣化も進んでしまうのです。
SSDのスペックが低い
SSDのスペックも、耐久性に大きく関わってきます。
まず、現行のSSDタイプは以下の4種類となります。
- SLC(シングルレベルセル)
- MLC(マルチレベルセル)
- TLC(トリプルレベルセル)
- QLC(クアッドレベルセル)
SSDには無数のセルが搭載されていますが、どのタイプのSSDかによって各セルに保存できるデータ量が異なり、1つのセルに保存可能なデータ量が多いほど耐久性が向上します。
なお、上記4タイプをスペック順に並べると「SLC > MLC > TLC > QLC」となり、SLCが最も耐久性に優れていることになります。
【SSDの故障原因や症状とは?】壊れた時の復旧方法についても解説>>
SSDの寿命を予測する3つの要素

SSDの寿命が残りどれくらいかを推測するのに、以下の3要素が役立ちます。
TBW(Total Byte Written)
TBWとは、SSDへの書き込み可能な総データ量のことで、SSDの寿命を予測するための最も重要な要素となります。
TBWの数値が大きいほど耐久性に優れており、長持ちしやすいです。
多くのメーカーが自社製品のTBWを公開しているので、耐久性を把握するためにもパソコン購入時には必ず確認すべきでしょう。
MTBF(Mean Time Between Failures)
MTBFとは、平均故障間隔のことで、一度修理してから次に故障するまでどれくらい時間がかかるか、についての平均を表す指標です。
どれくらいの期間に渡って正常に使用できるかがわかるので、MTBFの時間が多いほど耐久性に優れているということになります。
MTTF(Mean Time To Failure)
MTTFは、SSDを使用し始めてから故障するまでの平均時間のことです。
MTBFとほとんど同じ意味・役割ですが、MTBFが「故障したシステムを修復して使用することが前提」であるのに対し、MTTFは「修復不可能なシステムであり、修復しないことが前提」なので、「MTTF = 製品寿命」と言い換えることもできます。
SSDの寿命を診断する方法

SSDの寿命予測に役立つ要素については理解できても、具体的にどのように活用すればいいかわからないという方も多いでしょう。
主な診断方法としては、以下の2つになります。
フリーソフトを使って診断する
フリーソフトを使用して、SSDの状態を診断することができます。
SSDの寿命を予測するために重要なTBWについても確認できます。
SSDの診断には、以下のようなフリーソフトがおすすめです。
■CrystalDiskInfo
SSDの健康状態などを監視できるソフト。
型番や容量やバッファサイズといった基本情報はもちろん、TBW、電源投入回数、使用時間などの情報も一覧で確認することが可能。
■SSDLife Free
SSDの状態診断や寿命予測、SMART情報の確認などが可能なSSD専用のユーティリティ。
パソコン修理業者へ診断を依頼する
フリーソフトを使っての個人的なSSD診断は、あくまでも簡易的なものです。
本格的な診断を望む場合は、パソコン修理を生業としている専門業者へ依頼するのが確実です。
専用のツール等を使用して、個人では難しいような精度の高い寿命診断をしてくれます。
しかし、診断だけでも費用がかかってしまう場合や、無理やり修理する方向へ持っていき修理費用を取ろうとする業者も存在するため、特別な理由でもない限りはフリーソフトでの自己診断で問題ないでしょう。
SSDの寿命を延ばすためにできること

使用方法に気を配ることで、SSDの寿命を延ばすことも可能です。
少しでもSSDを長持ちさせるために、できる限り以下の点に気を付けながらパソコンを使用してください。
外付けHDDやオンラインストレージを使ってSSDの空き容量を確保する
SSDは、空き容量が少なくなると負荷がかかりやすくなってしまい、寿命を縮めることになります。
空き容量は多ければ多いほどよいので、普段使わないデータや、サイズの大きい動画や画像などはSSDに保存しないようにしましょう。
データの保存に関しては、HDDの方が向いています。
従って、大容量の外付けHDDを購入し、データに関してはできるだけHDDで保存するようにしてください。
また、オンラインストレージを利用してクラウド上にデータをアップロードするという手もあります。
無料で利用できるサービスが多く、自動バックアップ機能が搭載されているサービスも多いため、非常に便利です。
無駄なデータ書き込みを減らす
書き込みを繰り返すほど、SSDは少しずつ劣化していきます。
製品ごとにTBW(書き込みの総量)が決まっており、その決められたTBWに近づくほどSSDの寿命にも近づいてしまうため、必要のないファイルコピーなどの無駄な書き込み処理はできるだけ避けるようにして延命を図りましょう。
パソコンの電源を入れっぱなしにしない
毎日電源を切ることを面倒くさがり、四六時中パソコンの電源が入りっぱなしの状態になっている、という方は要注意です。
使用していない状態であろうと、通電しているのならばパソコンはバックグラウンドで動いています。
消耗品であるSSDが動いている以上、ほんの少しずつとはいえ地味に劣化が進んでいるのです。
あまり頻繁に電源を入れたり切ったりするのもよくないですが、せめて寝る前には必ず電源を落とすようにすべきです。
スリープ状態でも通電しているので、面倒くさがらずしっかりと電源を切るようにしてください。
高温多湿な環境を避ける
精密機械であるSSDにとって、高温や湿気は大敵です。
直射日光の当たる場所や、風呂場などの湿気のもとになるような場所の近くでパソコンを使用するのは控えてください。
その他、パソコンの周辺がほこりまみれというのもNGですので注意が必要です。
ほこりは帯電しやすく、パソコンの故障原因となる静電気をまとったままパソコン内部に侵入してしまうので、パソコン周辺はこまめに掃除するようにしてください。
SSDのデフラグ
デフラグとは、簡単に言ってしまうと「パソコン内部を整理整頓すること」です。
以前までは「デフラグによって書き込み回数を消費してしまい、逆に寿命を縮めるのでSSDにデフラグは無意味」という論調が強かったのですが、現在はこういった意見が減ってきています。
SSDへのデフラグ不要論が減ってきた理由は、主に以下の2点。
- TBWはかなり余裕を持って設定されていることがほとんどのため、多少デフラグの頻度が多いくらいでは影響がないこと
- SSD専用のデフラグツールを使ってデータの断片化を改善することは処理速度向上に繋がるため、決してマイナスではないこと
従って、SSDであろうと適度な回数のデフラグならば行った方がよいと言えるでしょう。
パソコンの使用時間や作業内容によって、どのくらいのペースでデフラグを行うのが「適度」なのかは変わってきますが、概ね1~2週間に一度程度を目安に行うのがおすすめです。
なお、SSDのデフラグを行うソフトとしては以下のフリーソフトが有名です。
寿命を迎える以外にSSDが動かなくなるパターン

SSDの劣化以外にも、SSDが動かなくなってしまうパターンがあります。
OSの故障
SSDに問題がなくとも、パソコンを正常に動作させるためのシステムであるOSに不具合が発生してしまっては、SSD自体が認識されなくなってしまうので動きようがありません。
パソコンが正常に立ち上がらなくなったら、何らかの理由でOSに不具合が発生している可能性を考慮し、まずはセーフモードでパソコンを起動してください。
それからデータのバックアップを行い、OSの再インストールをしてみましょう。
これで動けば、SSDには問題がなかったということになります。
SSDの物理的破損
SSDは振動や衝撃に強いですが、当然ながら「何をやっても壊れない」というわけではありません。
限界を超える強い力が加われば、SSDと言えど破損してしまいます。
機械である以上、そうした物理的な破損が発生してしまえばもう使用することはできません。
そもそも、振動や衝撃に強いというのも、あくまでHDDと比較した場合の話。
踏みつけや落下などについては細心の注意を払うようにしましょう。
SSD故障に備えたバックアップに最適なオンラインストレージ5選

どんなに気を付けてSSDを使用しても、いつかは寿命を迎えてしまいます。
その時に備えて、日々データをバックアップしておくことは非常に重要です。
データのバックアップには、外付けHDDの他にも「オンランストレージを利用する」という手があります。
オンラインストレージには、
- 自動でバックアップを行ってくれる
- 無料で利用できる
- ネットが繋がっていればどこからでもデータ保存ができる
といったメリットがあります。
デメリットとしては、オンラインストレージサービスを提供している会社サーバーに障害が発生するとデータが取り出せなくなることや、データ流出の懸念などがありますが、滅多にあることではないのであまり心配することはないでしょう。
以下に、おすすめのオンラインストレージサービスを5つ紹介します。
Google Drive
Google Driveとは、Googleが提供するオンラインストレージで、GmailやGoogle MeetなどのGoogleが提供するサービスと連携しながら使うことができます。
また、WordやExcelとも互換性があり、クラウド上で直接操作できるのも魅力の一つです。
多機能な上にセキュリティも高いため、オンラインストレージを利用するならばまず候補に挙がるサービスと言えるでしょう。
OneDrive
OneDriveとは、Microsoftが提供するオンラインストレージで、Microsoftアカウントを持っていれば誰でも利用可能となっています。
クラウド上にアップしたファイルは、スマホやタブレットからでも閲覧・編集が可能となっています。
Microsoftが運営しているだけあり、Google Drive同様にセキュリティ面も安心です。
Dropbox
Dropboxとは、ログイン不要で使用できるオンラインストレージです。
ファイル共有のしやすさが特徴で、共同で作業する場合などに向いています。
なお、無料版の容量は2GBと少ないですが、知り合いを紹介するなどの方法で容量を増やすことが可能です。
firestorage
firestorageとは、日本の会社が運営する、会員登録なしで気軽に利用できるオンラインストレージです。
無料版の場合、利用できる容量が250MBとやや寂しいですが、クラウド上でのちょっとしたファイルの受け渡しには非常に便利です。
box
boxとは、無料で10GBまで使える、世界最大規模のオンラインストレージです。
セキュリティ面で高い評価を得ているため、日本を含む世界中の企業が有料プランを利用していますが、個人がデータのバックアップのために利用するだけならば無料版でも機能的に充分です。
■box
SSDが寿命を迎えた場合の対処法

もしデータのバックアップを取っていない状態でSSDが寿命を迎えてしまった場合は、専門業者に修理を依頼するという手もあります。
ただし、SSDはHDDよりも復旧難易度が高いため、高額な費用が必要となる上、データの復旧が必ず成功するとも限りません。
まとめ:普段の使用方法に気を付けることで、SSDの寿命は延ばせる!
以上、SSDの寿命が5年程度であることや、寿命を迎えそうな時の症状、長持ちさせるためのコツなどについて解説しました。
SSD搭載のパソコンは高価なので、できるだけ長く使っていきたいものです。
パソコンを使うたびにいちいち、
「無駄なファイルコピーはやめよう…」
「空き容量確保のためにデータを移動させなきゃ…」
「しばらく使わないからちゃんと電源落とさないと…」
と気を配るのは面倒ですが、そうした努力を積み重ねることで、少しでも長く快適にSSDを使用することができるようになりますので、無駄な費用をかけないためにも、面倒くさがらず是非実行してみてください。


監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
パソコンにおける「電源」とは、「電源ユニット」のことを指します。
電力を管理するパソコンの根幹部分であり、電源ユニットが寿命を迎えたり故障したりすると、必要な電力が供給されなくなりパソコンは動かなくなってしまいます。
この記事では、電源ユニットの寿命についてや、寿命を迎える前に発生しがちな症状、電源を長持ちさせるための方法などについて解説していきます。
【この記事でわかること】
- パソコンの電源ユニットの寿命
- パソコンの電源ユニットの役割や規格
- 電源ユニットが寿命に近い時の症状
- 電源ユニットを長持ちさせるためのコツ

パソコンの電源ユニットとは?

パソコンの電源ユニットとは、電力を必要とするパソコン内の各部品へ安定的に電力を供給するためのパーツのことです。
「電源ボックス」と呼ぶこともありますし、単に「電源」と呼ぶこともあります。
電源ユニットの役割や規格は以下の通りです。
電源ユニットの役割
電気のロスを防ぎつつ、発電所から各家庭までの長い距離を無駄なく送電するのに「交流」は最適のため、家庭用コンセントから流れてくる電流はすべて「交流」となっています。
ですが、多くの電化製品で使用される電流は「直流」です。
そのため、コンセントから流れてくる交流電気でパソコンを動かすためには、交流から直流に変換する必要があります。
この役割を、電源ユニットが担っています。
その他、コンデンサという部品に電力を蓄えておいたり、電圧や電流のムラをなくすよう調整したりして、パソコンへ安定的に電力を供給するのも電源ユニットの役目です。
電源ユニットの規格とサイズ
電源ユニットの規格はいくつも存在しますが、主流となっているのは以下の3つです。
ATX
ATXは、大型であるフルタワーから小型であるミニタワーまで、ほとんどのデスクトップPCで採用されている規格です。
電源ユニットの中でも一番製品数が多い規格となっており、価格・容量・静音などのモデルに関して幅広く存在するため、自分の好みや用途に合わせて自由に選ぶことができます。
サイズは、150mm(幅)×86mm(高さ)×140~180mm(奥行)となっています。
SFX
SFXは、ATXが強化された規格で、主にサーバーPCに用いられます。
それだけ、電源ユニットとしての性能が高いと言えます。
サイズはATX同様、150mm(幅)×86mm(高さ)×140~180mm(奥行)となっています。
EPS
EPSは、小型PCに特化した規格です。
製品数自体は少ないのですが、サイズのバリエーションは豊富で、最も小さいもので100mm(幅)×50mm(高さ)×125mm(奥行)、大きなもので125mm(幅)×63.5mm(高さ)×130mm(奥行)となっています。
パソコンの電源の寿命は2~5年
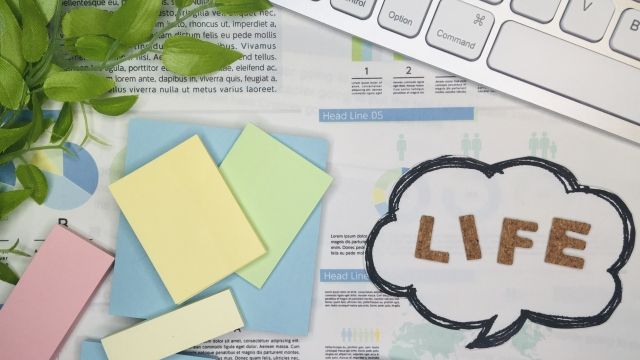
電化製品である以上、電源にも寿命はあります。
パソコンの使用方法や使用頻度によって大きく変わってきますが、概ね2~5年というのが一般的な電源の寿命となります。
電源に負荷をかけない使い方を心掛けることで、5年以上の使用も可能となります。
パソコンの電源の寿命が近いサイン
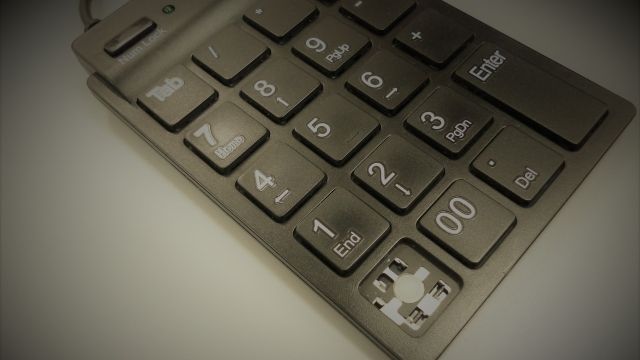
電源ユニットが劣化し寿命が近づいてくると、以下のような症状が出やすくなります。
電源ボタンを押しても起動・終了しない
電源の寿命が近づいてきた時に最も出やすい症状が、電源ボタンを押しても起動しない時がある、というものです。
何回か電源ボタンを押せば電源が入るということもあるかもしれませんが、一度の押下で反応しないというのは電源ユニット自体がかなり疲弊している証です。
また、電源ボタンを長押しして強制終了しようとしてもできない、という症状も電源ユニットに問題がある可能性が高いです。
これらは、電源ユニットのコンデンサが劣化したことによって起こりやすい現象です。
パソコンが起動しないことに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
パソコンが立ち上がらない!起動しない原因と黒い画面になった時の対処法>>
ファンからの異音発生
電源ユニット内に熱がこもらないよう、必ず搭載されているパーツである小さな扇風機「ファン」。
電源を入れると同時にファンも回転を始めますが、通常ならば気になるほどの音は聞こえません。
熱がこもってくると「ブーン」という回転音が聞こえることもありますが、ここまでならば何も心配はありません。
しかし、ファンの羽に大量のほこりがこびりついたり、経年使用によってベアリングが劣化したりすることで、「カラカラカラ…」という異音が聞こえることがあります。
こういった異音が聞こえるということは、まともにファンが機能しておらず放熱できていないため、電源ユニットの劣化が急速に進んでしまいます。
ファンから異音が聞こえ始めたら、そろそろ寿命なのだなと覚悟した方がよいでしょう。
突然電源が落ちる
電源ユニットの不調で安定した電力供給が行われなくなってくると、突然パソコンの電源が落ちる、という現象が頻発するようになります。
ただ、突然電源が落ちるのは電源ユニット以外の要因も考えられます。
例えば、以下のようなものです。
- OSの不具合
- 一時的に高負荷な作業を行っていた
- 熱暴走
- SSDやHDDの劣化
- ウイルス感染
不意に電源が落ちてしまうという症状だけでなく、「電源が入らない時がある」・「ファンから変な音が聞こえる」といった症状と併せて考慮し、電源ユニットに問題があるのか、その他のパーツに問題があるのかを判断してください。
フリーズの頻発
パソコン自体の寿命が近い時も出やすい症状ですが、電源ユニットの不調もフリーズ発生の原因となります。
特にパソコン起動中のフリーズは、電源ユニットの寿命が近いことを示唆しています。
パソコンは起動時に最も電力を消費するため、その起動に耐えうる電力を供給できないほど劣化が進んでいる可能性が高くなります。
パソコンのフリーズに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>
スタンバイ・スリープから復帰しない
起動時ほどではありませんが、スタンバイやスリープから復帰する際にもそれなりの電力が必要となります。
従って、電源ユニットの劣化が進んでしまうと復帰に時間がかかったり、最悪の場合は復帰できずに電源が落ちるといった現象が発生します。
USB接続した機器が動かない
外付けハードディスクなどをUSBケーブルで接続した時、接続した機器になんの反応もない場合は、電力不足により動くことができない、というパターンが考えられます。
つまり、電源ユニットが寿命に近づいていることで、正常な電力供給ができなくなっているかもしれない、ということです。
USBケーブルの異常も考えられるので、試しに違うケーブルを使ってみるとよいでしょう。
それでも電力がいかないようであれば、電源ユニットに問題がある可能性が高くなります。
故障原因が電源なのかを確認する方法

「突然電源が落ちる」「フリーズする」といった現象は、電源ユニットの不調に限らず、様々な要因で発生する不具合です。
故障原因が本当に電源ユニットにあるのかどうか、下記の方法で一つ一つ可能性を潰していき、原因を特定しましょう。
電源ケーブルがしっかり挿さっているかなどの基本的な確認
電源が入らないという時、「ただ電源ケーブルがうまくコンセントに挿さっていなかっただけ」というケースが多々あります。
特にパソコン初心者の方にはありがちなミスです。
まさかそんな単純なことが原因なわけがないだろうという思い込みが盲点となり、確認を怠りがちなのです。
まずは、コンセント側、パソコン側、双方にしっかり電源ケーブルが挿さっているかを確認してください。
その他、パソコン全体を目視して何らかの物理的な破損や異常がないかについても確認を行ってください。
不要なUSBケーブルを外す
電源ユニットの劣化によってパソコン内の電力が不安定になっている場合、外部機器への電力供給によって更なる電力不足を引き起こし、起動時のフリーズや突然電源が落ちるなどといった異変が発生しやすくなってしまいます。
電源の劣化が原因と思われる異変が続くようならば、一度USBなどで接続している不要な機器をすべて外してみてください。
外付けハードディスクやスマホの充電ケーブル、フラッシュメモリなどです。
こういったデバイスを外した結果、パソコンの動きが安定するようならば、電源の寿命が近い可能性が非常に高くなります。
電源ユニット周辺の温度調節
精密機械は熱に弱いものですが、電源ユニットの電力供給を管理しているコンデンサは、低温すぎても動かなくなってしまいます。
冬の寒冷地で室温が氷点下になってしまうような場合は、特に要注意です。
電源ユニット周辺が低温すぎてコンデンサが正常に動いていない可能性もあるので、寒すぎる時は暖房を使ってじっくりと部屋を暖めてみてください。
なお、一気に暖めようとして電源ユニット部分にドライヤーを使うという行為はNGです。
寒い状況でいきなり急激に暖めると、内部で結露が発生してしまい故障の原因となります。
暖房を使ってゆっくりと部屋全体を温めるようにしてください。
部屋を暖めることで電源が問題なく入り、その後も普通にパソコンを使用できれば、「寒すぎたことによる一時的な不良」ということが判明します。
電源の寿命を延ばすための方法

パソコンを動かすための根源である電源。
そんな電源の寿命を延ばすための方法を紹介します。
電源をつけっぱなしにしない
機械である以上電源ユニットも消耗品であり、使えば使うほど劣化していきます。
電源をつけっぱなしにしてしまうと、ファンは常に動いていますし、安定的な電力供給を行うコンデンサもダメージを蓄積していきます。
起動を待つのが面倒という理由で、寝る前にパソコンの電源を落とさない方もいらっしゃると思いますが、ちょっとした手間を惜しまず、寝る前は毎日電源を落とすようにして電源ユニットの負荷を減らすようにしてください。
電源ユニットの掃除
定期的な電源ユニットの掃除も、延命に繋がります。
掃除の目的は、ほこりの除去。
静電気を帯電しやすいほこりは精密機械にとって大敵ですし、ほこりが大量にまとわりつくことでファンの動作もおかしくなり、正常な放熱ができなくなります。
電源ユニットを開いて綺麗に掃除するのは大変ですが、せめてパソコン周辺にあるほこりを取り除くくらいの作業はこまめに行うべきでしょう。
可能ならば、電源ユニット内のほこり除去も数か月に一度程度は行ってください。
電源ユニット内の適切な温度管理
電源ユニットを始めとする精密機器は、熱に弱いという特徴がありますので、直射日光の当たる場所にパソコンを置かないようにしたり、高温多湿となるような環境でパソコンを使用しないようにすることが電源の延命に繋がります。
ただ、寒すぎるのもマイナスに働いてしまうので注意が必要です。
常に氷点下となるような場所で放置すると、コンデンサが正常に機能しなくなる可能性があります。
「熱すぎず寒すぎず」という環境を用意することが、電源ユニットをはじめパソコンの各パーツを長持ちさせるコツです。
バッテリーの劣化を防ぐ
特にノートパソコンに言えることですが、バッテリーを空の状態にしたり、満タンの状態にするのは避けましょう。
- 電力がない状態が長い
- 過充電
どちらも、電源と深い関係にあるバッテリーの劣化を招きます。
ノートパソコンのバッテリーの交換時期は?交換方法や寿命を伸ばす方法も紹介>>
放電する
パソコンを使用していると、知らず知らずのうちに静電気が内部に溜まっていきます。
静電気はパソコンの各パーツにダメージを与える要因になってしまうため、定期的に放電して静電気を除去すべきです。
放電方法は簡単で、電源ケーブルを抜くだけ。
ノートパソコンの場合は、バッテリーも外してください。
この状態で5分程度放置すれば、放電は完了します。
ケーブルを抜くのは、コンセント側でもパソコン側でも、どちらでも構いません。
手軽で効果がある方法なので、是非実践してみてください。
電源に負荷をかけすぎない
一度に大量の電力を消費すると、電源ユニットはダメージを受けます。
例えば、パソコンの起動。
パソコンを立ち上げる際には多くの電力を要するため、一日に何度もパソコンを起動するようなことは避けましょう。
日中に連続してパソコンを使用する予定があるのならば、その間はつけっぱなしにし、夜寝る前に電源を落とす方が電源ユニットへのダメージを軽減できます。
また、スペックに見合わない処理をパソコンに求めるのもよくありません。
HDDのみを搭載しているパソコンで、「動画編集」や「大量のメモリを必要とするオンラインゲーム」をやってしまうと、電源に大きな負荷がかかります。
動画編集やオンラインゲームは、本来SSDを搭載したパソコンで行なうもの。
HDDで処理するには厳しい作業なのです。
こういったスペックに合わない作業をパソコンに強要するのも、電源ユニットを始めとする各パーツへダメージを与える行為となります。
動画編集に必要なパソコンのスペックからおすすめの購入先を紹介>>
電源ユニットが故障した場合

電源ユニットが故障した場合は、「電源ユニットの交換」か「パソコンの買い替え」の二択となります。
電源ユニットを交換する
オーソドックスな方法としては、電源ユニットに異常を感じたら交換する、という方法です。
異常個所が本当に電源ユニットのみの場合は、これでパソコンは復活します。
なお、パソコンに詳しい方は自分で交換作業をやってしまっても問題ありませんが、自信の無い方は業者に依頼すべきです。
知識がないままなんとなく電源ユニットの交換作業をしてしまうと、パソコン内部に残っていた電流による感電や、作業ミスによるパーツ破損といったリスクがあります。
自分の知識や力量を考慮した上で、業者に依頼するかどうかを判断してください。
不要になった電源の交換方法はこちらで解説しています。
パソコンごと買い替える
電源ユニットの交換にはそれなりの費用もかかりますし、電源ユニットが故障したということは、他のパーツも寿命が近いという可能性があり、またすぐに電源以外のどこかが故障してしまうかもしれません。
購入してからそれほど日が経っていない状態で電源に異常が発生してしまった、というような初期不良のケースならば別ですが、数年ほど使用した結果電源が寿命を迎えてしまったのならば、いっそのこと買い替えてしまった方がよいでしょう。
数年も経っていれば、パソコンの性能は飛躍的に向上していますし、電源ユニットの耐久性も上がっていますので、買い替えた方がメリットが大きいです。
まとめ:「こまめな掃除」と「電源をつけっぱなしにしない」ことが特に重要
他のパーツ同様、電源も消耗品であり、使えば使うほど劣化していきます。
従って、電源をつけっぱなしにするというのは電源の寿命を削るために行なうような行為といっても過言ではないでしょう。
面倒であろうと、長時間使用しない時は都度パソコンの電源を落とすべきです。
特に、寝る前には必ず電源を落とすということを癖付けましょう。
また、パソコンにとって害となる静電気をまとう「ほこり」も大敵です。
パソコンの周辺のほこりはこまめに除去するようにし、数か月に一度は電源ユニット内のほこりも掃除するようにすれば、電源の寿命を延ばすことができます。


監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
任天堂が誇る、世界で9,000万台以上も売れている大人気ゲーム機「Switch」。
据え置き型としても携帯型としても楽しめるフレキシブルな部分も人気の一因となっています。
そんなSwitchですが、高価なゲーム機であるため可能な限り長持ちさせたいものの、電化製品というのはすべて消耗品ですのでいつかは寿命を迎えてしまいます。
この記事では、Switchの寿命がどれくらいなのかや、できるだけSwitchの寿命を延ばすための方法などについて解説していきます。
【この記事でわかること】
- Switchの寿命
- Switchが故障する原因
- Switchの寿命が近い時に出やすい症状
- Switchを長持ちさせるためのコツ
任天堂Switchの寿命は何年?

Switch本体の寿命は、使用頻度や扱い方など個人個人のケースによってバラバラですが、一つの目安になるのが「バッテリーの寿命」です。
バッテリーが劣化してしまうと、安定的な電力供給が行なわれなくなり、Switch本体へ負荷をかけやすくなってしまうため、故障する可能性も高まっていきます。
バッテリーの劣化については、任天堂の公式ページにて以下のように説明されています。
内蔵バッテリーは特性上、充放電を繰り返すと、満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
各機器の目安は、次のとおりです。
■Nintendo Switch本体(従来モデル・有機ELモデル共通)
約800回繰り返して充電した場合、新品購入時の約80%となります。
■Nintendo Switch Lite本体
約800回繰り返して充電した場合、新品購入時の約80%となります。
■Joy-Con
約500回繰り返して充電した場合、新品購入時の約80%となります。
■Nintendo Switch Proコントローラー
約500回繰り返して充電した場合、新品購入時の約70%となります。
引用:【Switch】本体やコントローラーの内蔵バッテリーの寿命はどれくらいですか? | Nintendo
上記の通り、充電を繰り返すほどバッテリーは劣化していき、いずれ寿命を迎えて充電ができなくなります。
バッテリーが何年もつのかについては充電頻度によって大きく異なりますが、毎日のようにプレイする場合は2~3年がバッテリー交換の目安となります。
Switchが動かなくなってしまう原因

バッテリーの劣化によってSwitchが使えなくなってしまっても、バッテリーを交換すればまた使用できるようになります。
ただ、本体が寿命を迎えてしまうと修理しない限り使えるようにはなりません。
では、バッテリー以外ではどういった要因でSwitchが動かなくなってしまうのでしょうか。
以下にて解説していきます。
落下や踏みつけによる物理的ダメージ
最も多いのが、落下や踏みつけといった物理的な衝撃が加わることによる故障です。
携帯して外で遊ぶこともできる上、子供が使用する場合も多いため、誤って落としてしまったり、踏んでしまったりということは珍しくありません。
そこで液晶が割れればおしまいですし、液晶が無事でも内部機器が損傷を受けてしまう可能性も高いです。
水に濡らしてしまう
据え置き型のゲーム機ならばあまり心配のいらない水没ですが、携帯型でもあるSwitchには水没の危険があります。
例えば、以下のようなパターンです。
- トイレに落とす
- 洗濯機の中に落とす
- 水やジュースをこぼす
- 風呂場に近いところでSwitchを使用する
当然、精密機器にとって水は大敵です。
Switch本体や付属品であるJoy-Conなどには防水機能が搭載されていないため、水没の際の故障リスクが非常に高いです。
また、水没とまでいかなくとも、湿気の多い場所で使用するだけでもダメージを受けてしまう可能性が高いので、風呂場や加湿器の近くで使用するだけでも故障リスクが伴います。
水没した場合は、適切な対処法を行えば直る可能性があります。間違った対処法をすると、より悪化させてしまうため注意してください。詳しい対処方法については、下記の記事を参考にしてください。
switchが水没したときの対処法!やってしまいがちなNG行為についても徹底解説 | パソコン廃棄.comお役立ち情報
ゲーム時の力の入れすぎ
Joy-Con(コントローラー)で操作する際に必要以上に強い力を加えてしまうと、ボタンのへこみなどのトラブルが発生してしまうことがあります。
SwitchのJoy-Conの作りはお世辞にも頑丈とは言えず、「ゲームに熱中して力を入れすぎてしまう」という状態が長く続くと、操作した通りに動かなくなるという不具合が発生しやすくなります。
具体的には、
- 何も操作していないのにキャラが勝手に動いてしまう
- 狙った場所に攻撃を当てることができない
といった不具合です。
強引なケーブルの抜き差し
充電などの目的でケーブルの抜き差しをする際に力任せに行ってしまうと、端子が曲がったり壊れたりしてしまうことがあります。
そうなると充電ができなくなったり、必要な付属品を接続することができなくなるので、修理に出さなければならなくなります。
ホコリの多い環境での使用が多い
ホコリが多い環境でSwitchを保管したりプレイしたりすると、充電や付属品の接続のための差し込み口にホコリが詰まりやすくなり、差し込まれたケーブルが認識されづらくなってしまいます。
また、排気口や吸気口にホコリが詰まるとうまく排熱ができなくなり、本体に熱がこもってしまい、基板などの各パーツの劣化を招きます。
Switchの寿命が近づくと出やすい症状
Switchが限界を迎えそうな時に出やすい症状について紹介していきます。
Switch本体の寿命が近い時
まず、本体が異常に熱いと感じた時は要注意です。
本体を冷やすためのファンが壊れていて、正常に冷却できていない可能性が高くなります。
症状が悪化すると、熱暴走により電源が落ちてしまうといった現象も発生します。
こういった症状を気にせずSwitchを使用し続けると、Switch本体の命ともいえる基板の損傷にも繋がってしまうので要注意です。
詳しい対処方法は、下記の記事を参考にしてください。
Switchが熱い原因とは?対処方法や修理方法を紹介 | パソコン廃棄.comお役立ち情報
また、ホコリの詰まりや、経年劣化による差込口の認識不良によってソフトを読み込めないといったトラブルが発生した時も、放置せずに対処すべきです。
バッテリーの寿命が近い時
バッテリーは、充放電を繰り返すほどに充電できる容量が減っていきます。
満充電になったはずなのに、少し遊んだところで充電切れになってしまう、といった症状が出ると、バッテリーの寿命が近いサインです。
Joy-Con(ジョイコン)の寿命が近い時
意図した操作通りの動きにならなかったり、何も操作していないのにキャラが動いたりしたら、Joy-Conのボタンやキーに不具合が生じている可能性が高く、修理するか買い替える必要があります。
なお修理する場合は、Joy-Con1本につき2,200円(税込)の費用がかかります。
つまり、2本ならば4,400円(税込)です。
参考:修理の参考価格 Nintendo Switch|サポート情報|Nintendo
しかし、修理したJoy-Conと新品のJoy-Conとでは耐久性が違い、言うまでもなく新品の方が長持ちしやすいです。
新規購入費用が左右セットで8,228円(税込)であることを考慮すると、修理するのか新規購入するのか、どちらがよいとは一概に言えません。
「今後も長くSwitchで遊び続ける」という方は新品を購入し、「とにかく安い方法で」という方は修理を選ぶ、というように、自分の状況や考えに合わせて選択していくとよいでしょう。
Switchを長持ちさせるためのコツ
高価なSwitchですから、誰しもが「できるだけ長持ちさせたい」と考えていると思われます。
そこで、Switchの寿命を延ばすためのコツについて紹介していきます。
本体を丁寧に扱う
Switchは持ち歩くことも多いゲーム機なので、据え置き型のゲーム機に比べて落下リスクが高いです。
精密機械にとって落下による衝撃は大敵であり、もしアスファルトの上にでも落としてしまえば、高確率で液晶が割れるなどの致命的なダメージを受けてしまいます。
持ち運ぶ際は、細心の注意を払うようにしてください。
お子様が外へ持ち出そうとした時は、Switchをむき出しで持たせず、仮に落としてもダメージを軽減できそうな厚手の布バッグなどに入れて持たせるようにしてください。
また、誤って踏みつけてしまわないように、Switchを使用したら必ずすぐに片付けるように癖付けることも大事です。
やりっぱなしで放置しておけば、それだけ踏みつけリスクも高くなりますので。
こうして、日々Switchを大事に扱うことで物理的な破損を避けることができ、Switchの延命に繋がります。
充電しながら遊ばない
充電中は本体が熱を持つため、充電しながらのプレイは避けましょう。
熱による負荷で、本体やバッテリーの劣化を早めてしまいます。
過放電を防ぐ
過放電の期間が長く続いてしまうと、電源が入らなくなってしまうことがあります。
過放電とは、長期間使用せず電力がゼロの状態が続くことです。
Switchで遊ばない期間が長く続いている場合でも、半年に一度程度は充電をしておきましょう。
なお、充電する際は5℃~35℃の環境で行ってください。
参考:充電のしかた(充電時のご注意)|Nintendo Switch サポート情報|Nintendo
接触不良時に叩かない
昔の悪習から、「調子の悪い機械は叩けば直ることがある」と信じている方がいまだに一定数いらっしゃいますが、精密機械を叩くことはデメリットしかありません。
叩いて直ることはなく、逆に悪化してしまうことすらあります。
接触が悪い時は、丁寧なケーブルの抜き差しを繰り返してみてください。
何度試しても接触不良の状態が続く場合は、ケーブルかSwitch本体が寿命を迎えている可能性があります。
湿気の多いところを避ける
精密機械は漏れなく湿気に弱いものです。
当然Switchも湿気には弱いので、湿気の多い風呂場や加湿器の近くでプレイしたり保管したりすることは避けるようにしてください。
ホコリの多い場所で保管しない
ホコリだらけの場所でSwitchを保管してしまうと、ケーブルの差込口などにホコリが溜まりやすくなってしまいます。
なるべく清潔な環境で保管するように心掛けてください。
定期的なホコリ除去
保管場所に気を配っていたとしても、完全にホコリを寄せ付けないようにするのは難しいです。
Switchの各部にホコリが詰まってしまうと、ファンの故障に繋がったり、接触不良を起こしたり、本体に熱がこもりやすくなってしまいますので、Switch本体の状態を確認してホコリが溜まっているようならばすみやかに掃除をしてください。
特に大事なのは以下の部分です。
- ケーブルの差込口
- 上部にある排気口
- 裏面にある吸気口
差込口のホコリは、接触不良や静電気による内部パーツへのダメージの原因となります。
排気口と吸気口のホコリは、ファンの故障を誘発してしまいます。
冷却ファンが機能しなくなるとうまく排熱できなくなり、本体が熱を持ちやすくなってしまい、Switch本体に負荷をかけてしまう原因となります。
参考:【Switch】本体が熱くなります。故障でしょうか? | Nintendo
機器の消毒や掃除は正しく行う
Switch本体やJoy-Conを消毒したり、気になる汚れを掃除したりする場合は、以下の方法で行ってください。
【機器の消毒】
- アルコール濃度70%程度の市販の消毒液を、柔らかくて清潔な布に軽く含ませて優しく拭く
- アルコール以外の消毒液や溶剤は絶対に使用しない
- 消毒後は、完全に乾いたことを確認してから使用する
【汚れ掃除】
- 水で濡らして固く絞った、柔らかくて清潔な布で優しく拭く
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しない
参考:機器のお手入れについて|Nintendo Switch サポート情報|Nintendo
充電器は純正のものを使用する
充電器などの付属品は、任天堂が販売している純正品を使用するようにしてください。
非純正品は値段が安いものの、安全性の面で不安が残ります。
安いものを使用した結果Switchの寿命を縮めてしまった、というケースもありますので、目先の安さに惹かれず、純正品のみを使うべきです。
数年ごとにバッテリーを交換
バッテリーが劣化すると、電力の供給が不安定になり、Switch本体にもダメージを与えてしまう場合があります。
使用頻度にもよりますが、一般的な遊び方をしている場合は2~3年を目安にバッテリー交換を行うようにしてください。
Switchが完全に故障してしまった場合
バッテリーが寿命を迎えただけならばバッテリー交換で解決しますが、その他のトラブルが原因でSwitchが故障した場合は本体の修理が必要になってしまいます。
なお、修理箇所・交換箇所による修理代は以下の通りです。
【Nintendo Switch本体(有機ELモデル)[HEG-001]の場合】
| 症状 | 修理・交換箇所 | 価格 |
|---|---|---|
| 電源が入らない 画面が止まる 充電ができない など | CPU基板 | 15,400円 |
| 画面の割れ・ヒビ 画面の映像が正常に出ない 画面タッチスクリーンが反応しない 電源が入らない など | 有機ELディスプレイ | 11,000円 |
| ゲームが読み込まない SDカードが読み込まない イヤホンをさしても聞こえない 充電差込口の不具合 スタンドの破損 バッテリー交換 など | CPU基板、有機ELディスプレイ以外の部品 | 4,950円 |
参考:修理の参考価格 Nintendo Switch|サポート情報|Nintendo
ご覧の通り、それぞれそこそこの修理費がかかる上、内部的な不具合が発生しているということは経年劣化が進んでいる可能性も高いです。
修理したもののまたすぐに壊れてしまい、結局新品を購入することになった、というようなケースも考えられることから、無理に修理しようとせずに思い切って新品に買い替えてしまうという方が結果的に安上がりかもしれません。
まとめ:Switchで遊ぶ時は慎重に

持ち歩けるというメリットが仇となり、硬いアスファルトの上に誤って落下させてしまった場合には購入初日に壊れてしまう可能性もある任天堂Switch。
少しでも長くSwitchの寿命を延ばすために、まずは落下や踏みつけといった物理的な破損には細心の注意を払ってください。
その上で、こまめなホコリの除去を心掛け、湿気の少ない場所でプレイ・保管をしたりすることで長持ちさせることができます。
日々の手入れは面倒ではありますが、高価なSwitchの寿命が少しでも長くなるように労わりながら使用していきましょう。

監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
いつものようにiPhoneの充電をしようとしたのに、全く充電できない、もしくは思うように充電が進まない、ということがあると思います。
しかし、iPhoneが充電できない理由は充電器だけでなく本体やバッテリーの可能性もあります。
また、その対処法も充電できない原因によっても異なります。
この記事では、iPhoneで充電できない原因とその対処法について、詳しく解説していきます。
【この記事でわかること】
- iPhoneが充電できない場合の症状
- iPhoneで充電ができなくなる原因
- iPhoneで充電できない時の対処法
- 何をしても駄目な時にはどうすべきか
- 充電できない時にやってはいけない行動
iPhoneが充電できない場合の症状

iPhoneが充電できない場合に見られる症状は、次の2つです。
- 充電マークが表示されている
- 充電マークがすぐ消えて接続音がなる
ここでは、それぞれの症状を詳しくみていきましょう。
充電マークが表示されている
充電器を接続して充電マークが表示されているにもかかわらず、充電が増えない症状です。
正常なiPhoneでもゲームをプレイしていて充電が溜まらないケースはありますが、この場合は放置しても充電が溜まりません。
ただし充電が80%から溜まらない場合は、iOS13以降の機能である「バッテリー充電の最適化」がONになっていないか確認してみましょう。
「バッテリー充電の最適化」はバッテリー劣化を防ぐため、起床時間に合わせてバッテリーを100%にする機能です。
オフにすることによって、改善される可能性があります。
充電マークがすぐ消えて接続音がなる
iPhoneを充電すると充電マークになって接続音がなりますが、この接続音が何度もなります。
接続音はなっているものの、正常に充電はできていません。
充電器のケーブルの破損、もしくは差込口が壊れている可能性があります。
iPhoneで充電できない原因

iPhoneが充電できない原因は多岐にわたります。
この項目では、「充電器側」「iPhone側」「バッテリー側」に分けて、iPhoneが充電できなくなる原因を解説していきます。
充電器側の原因
充電器側の問題で充電できない場合は、主に以下の7つが原因となります。
ケーブルがしっかりと挿さっていない
意外と多いのが、単に充電器やiPhone本体にケーブルがうまく挿さっていないため充電できていない、というケアレスミスです。
充電できないという状態に慌てず、まずはケーブルがしっかりと挿さっているかを確認してみましょう。
ただ、ケーブル等の劣化によって、一見しっかりと挿さっているように見えても充電できていない、というパターンもあります。
充電ケーブルの断線
充電ケーブルが断線していると、当然充電はできません。
何度挿し直してみても充電されないという時は、断線の可能性があります。
特に純正品以外のケーブルを使っていると、断線トラブルが起こりやすいです。
純正品であっても、ケーブルの上に何か重いものを載せてしまったり、強く引っ張ったりした場合に断線を起こすことは珍しくありません。
また、適切に使用していた場合でも、経年劣化により断線を起こすことがあります。
こうした破損したアクセサリを使用すると、iPhone本体にもダメージを与える可能性がありますのでご注意ください。
ワイヤレス充電のやり方を間違っている
iPhone8以降のモデルでは、直接ケーブルを挿して充電する以外に、ワイヤレスでの充電も可能となりました。
比較的歴史の浅い充電方法のため、「充電できない!」と焦る方が多いようです。
ワイヤレス充電がうまくいかない時の原因は、主に以下の4つです。
- ワイヤレス充電器の上に正しくiPhoneを置いていない
- スマホカバーが充電の邪魔をしている
- iOSの不具合
- ワイヤレス充電器の故障
ケーブルが非純正品
iPhoneのライトニングUSBケーブルには、以下の3つが存在します。
- 純正品
- MFI認証品
- 非純正品
純正品ケーブルとは、Appleが製造しているケーブルで、最も安全性が高いものとなっています。
MFI認証ケーブルとは、Appleが自社製品との互換性を保証しているケーブルで、純正品同様問題なく使用できます。
そして、純正品でもMFI認証品でもないケーブルが、非純正品となります。
非純正品の場合は品質がバラバラであり、粗悪品を掴んでしまうと「突如充電できなくなる」「iPhone本体にダメージを与える」といった事態に陥ることがあります。
なお、一見MFI認証のケーブルのように見えても油断は禁物です。
無許可でMFI認証マークを使っていたり、認証機能をコピーしたりしている非純正品も存在するため、MFI認証のケーブルと見せかけて実はただの粗悪品、ということもあります。
ケーブルやアダプタの端子が曲がっている
アダプタをコンセントに挿す時や、ケーブルを充電器やiPhoneに挿す時に、変な方向に強い力が加わってしまい端子が曲がることがあります。
端子が曲がってしまうと、正しく充電できなくなることが多いです。
パソコンがスリープモードになっている
USBケーブルを使ってパソコンで充電をしている場合、パソコンの設定によっては、スリープモードになってしまうと充電できません。
モバイルバッテリーが寿命を迎えている
モバイルバッテリー利用時に、バッテリー切れでもないのに充電できないという場合は、モバイルバッテリーが寿命を迎えている可能性があります。
モバイルバッテリーに使用されているリチウムイオン電池は、無限に使えるものではありません。
充電をするたびに劣化していき、いつかは使えなくなってしまいます。
iPhone本体の原因
iPhone本体側の問題で充電できない場合は、主に以下の6つが原因となります。
iPhoneの充電ポートの故障や異物の詰まり
iPhoneの充電ポートに埃などの異物が詰まっている場合、うまく充電できないことがあります。
また、充電ポートの機能に不具合が生じ、ライトニングケーブルの端子を認識しないというケースも考えられます。
iPhone内部で熱暴走を起こしている
iPhoneが、熱くて持っていられないくらいの熱を帯びたら要注意。
熱暴走を起こしている可能性があります。
熱暴走とは、
- 直射日光を当て続けた
- 高温な状況で放置
- 多くのアプリを同時並行して使うなどCPUに負荷をかけすぎた
といった時に起こる可能性があり、熱暴走が発生すると様々な不具合が生じます。
その不具合の一つに、「充電ができなくなる」というものがあります。
iPhoneの水没
iPhone7以降は防水機能が搭載されましたが、水に弱い精密機械であることは変わらないため、水没は充電不良の大きな原因となります。
また、防水機能は経年劣化もするため、年数の経ったiPhoneの場合は完全な水没でなくとも充電できなくなる可能性があります。
iOSの不具合
長期間に渡ってiOSのアップデートを行なっていなかったり、何らかの理由でiOSに不具合が発生していると、充電不良の原因となる場合があります。
「最適化されたバッテリー充電」の設定が有効になっている
80%以上の充電ができない、もしくはなかなか充電が進まない場合は、「最適化されたバッテリー充電」の設定が有効になっているからです。
iOS13以降に搭載された機能で、バッテリーを長持ちさせるための設定ですので、故障ではありません。
電池残量がほとんどない
電池残量がゼロ、またはゼロに近い状態で充電した場合、画面には電池マークが表示されるだけで、充電が進んでいるのかどうかわからないことがあります。
しかしこれは、起動に必要な充電がないために起こる現象なので心配は不要です。
そのまま10分から20分ほど待っていれば、使用できる状態になります。
バッテリーの原因
充電できない理由がバッテリーにある場合は、以下のような現象が起こっている可能性が高いです。
バッテリーの劣化
iPhoneのバッテリーにはリチウムイオン電池が使用されていますが、充電池は、使用すればするほど劣化していくのが宿命です。
Apple公式サイトでも、以下のように書かれています。
バッテリーの化学的経年劣化が進むと
充電式バッテリーはすべて消耗品で、化学的経年劣化が進むにつれて性能が低下します。
リチウムイオンバッテリーの化学的経年劣化が進むと充電可能な容量が低下し、その結果、再充電が必要になるまでの時間が短くなっていきます。
~中略~
このような状況と化学的経年劣化が重なると、インピーダンスの増加はさらに顕著になります。こうしたバッテリーの化学的特性は、業界全体に普及しているリチウムイオンバッテリーすべてに共通するものです。
要は、iPhoneに限らず、リチウムイオン電池を使っているバッテリーはすべて消耗品であり、充放電を繰り返すことによる経年劣化は避けられない、ということが説明されています。
iPhoneのバッテリー寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。
iPhoneバッテリーの寿命の目安は何年?確認方法や長持ちさせるコツも解説>>
iPhoneで充電できない時の対処法

iPhoneの充電ができない場合の対処法を原因別にまとめましたので、是非参考にしてみてください。
充電器が原因の場合の対処法
充電器が原因と思われる場合の対処法は以下の通りです。
ケーブルが正しく挿さっているか確認する
充電ケーブルがうまく挿しこまれていない可能性を考慮し、何度か抜き差しを繰り返してみてください。
力任せに挿すと状況の悪化を招く場合がありますので、丁寧に作業してください。
純正品のケーブルを使用する
非純正品のケーブルを使用している場合は、純正品のケーブルを購入して試してみてください。
非純正品は安いですが、その分粗悪なものもありますので、最初から充電できなかったり、故障しやすかったりします。
また、一見普通に使用できているように見えても、純正品以外のケーブルの場合ですと供給できる電圧にばらつきがあるため、iPhone本体へダメージを与える可能性があります。
純正品以外でも優秀なケーブルはありますが、その見極めは難しいので、必ず純正品を使用するようにしてください。
USBアダプタを変えてみる
ケーブルに異常がない場合、次に疑われるのはUSBアダプタの異常です。
端子の曲がりや何らかの不具合によって正常に機能しなくなっている可能性があるので、一度Appleストアへ相談した上で、純正品のアダプタを検討してください。
ワイヤレス充電がうまくいかない場合
前述の通り、ワイヤレス充電がうまくいかない時の原因は、主に以下の4つです。
- ワイヤレス充電器の上に正しくiPhoneを置いていない
- スマホカバーが充電を邪魔をしている
- iOSの不具合
- ワイヤレス充電器の故障
まずはスマホカバーを外し、それからワイヤレス充電器の上にiPhoneを正しく載せてみてください。
これで解決しない場合は、iOSの不具合が考えられますので、再起動やアップデートを行なうことで解決することがあります。
ここまでやっても駄目な場合は、ワイヤレス充電器の故障が疑われますので、新しいワイヤレス充電器を購入するか、ケーブルでの充電に切り替えるかを検討してみてください。
iPhone本体が原因の場合の対処法
iPhone本体が原因と思われる場合の対処法は以下の通りです。
まずは低電力モードにする
充電できない状態のiPhoneでいろいろな操作を試すと、さらに電力を消費してしまいます。
電池残量がゼロになってしまうと何もできなくなるので、それを避けるためにも、まずはiPhoneを低電力モードに切り替えてから作業を行なうようにしましょう。
低電力モードへ切り替えるには、まず設定画面を開き、「バッテリー」の項目をタップします。
すると、バッテリーの設定画面が開くので、画面上部にある「低電力モード」をONにします。
上記画像ではOFFになっていますが、赤枠の右部分をタップしてONにすれば、低電力モードに切り替わります。
iPhoneを再起動する
ソフト面で何らかの不具合が起こっている場合は、再起動するだけで解決することもあります。
充電できないというトラブルに限らず、不具合発生時はとりあえず再起動してみるのがよいでしょう。
iPhoneの充電ポートを掃除する
iPhoneの充電ポートを覗き込んでみて、埃などの異物が詰まっていないかを確認してください。
何か詰まっているようならば、以下の手順でポートの掃除を行なってください。
- 掃除前に電源を落とす
- 爪楊枝でやさしく異物を取り去る
- 薄手の布でポートの細かい汚れを拭き取る
注意点として、爪楊枝を使う際にはガリガリと力任せにポートをほじくらないことです。
また、爪楊枝がないからといって、安全ピンなどの金属製のものを使用するのもやめてください。
ポートの中の金属を傷つけてしまう可能性があります。
綿棒やティッシュで掃除をしようとする方も多いようですが、得策ではありません。
掃除をしたつもりが、綿棒やティッシュの繊維がポート内に残ってしまい、新たなゴミとなって充電を邪魔する要因になってしまいますので。
最後に、薄手の布での掃除について。
仕上げとばかりに、「フッ!」と息を吹きかけたくなりますが、その時に唾が飛んでしまうと湿気の原因となってしまいますので避けてください。
当然、ウェットティッシュなどの濡れた素材を使用するのも駄目です。
iPhoneを冷却する
水だけでなく、精密機械は熱にも弱いもの。
従って、iPhoneが異常に熱く、熱暴走が疑われる場合には、「涼しい場所に放置する」・「扇風機で冷やす」といった対応を取ってください。
パソコンにファンが搭載されているように、ただ風を送るだけでも冷却効果は大きいです。
これで熱暴走が止めば、再び充電できるようになる場合もあります。
気を付けていただきたいのが、「冷やせるならば何をしてもいい」ということではないことです。
「iPhone7以降は防水機能があるから冷水で冷やそう」
「保冷剤をiPhoneの上に載せよう」
こういった対策は厳禁です。
防水機能があるとはいえ、精密機械が水に弱いことには変わりありません。
また、冷蔵庫で冷やすといった行為もNGです。
急速に冷やされたことでiPhone内部に結露が発生し、湿気を帯びてしまう可能性がありますので。
あくまで、自然な形での冷却を試みてください。
iOSのアップデートを行なう
iOSのアップデートを行なうだけで、充電が可能になることもあります。
iOSは、常に最新バージョンにしておきましょう。
水没時は電源を切って放置
iPhoneの水没時には、誰しも「一刻も早く乾かさないと!」という焦りが生じることでしょう。
ただしその際、ドライヤーの熱風で乾かすのはNGです。
精密機械は熱に弱いため、熱風を当て続けてしまうと基盤の故障などに繋がってしまいます。
水没した際は変に何かしようとせず、電源を切り、風通しの良い涼しい場所に放置してください。
運が良ければ、これだけでiPhoneが復活することもあります。
充電が80%で止まる場合は「最適化されたバッテリー充電」の設定を変更する
充電が80%で止まってしまう場合は、「設定」⇒「バッテリー」⇒「バッテリーの状態」とタップしていくと出てくる以下の画面にて、「バッテリー充電の最適化」をオフにすれば設定が変更されます。
参考: 「iPhone や iPod touch が充電されない場合 – Apple サポート(日本)」
バッテリーが原因の場合の対処法
バッテリーが原因と思われる場合の対処法は以下の通りです。
バッテリーの劣化状況を確認
「設定」⇒「バッテリー」⇒「バッテリーの状態」とタップし、「最大容量」を確認します。
上記の赤枠の部分です。
こちらのバッテリーの最大容量が「80%」を下回った時は、バッテリー交換の目安となります。
その他のiPhoneの充電に関するトラブルの対処法
スリープモードでも充電できるように設定する
パソコンを一定時間操作しないとスリープモードとなることがありますが、このスリープモード中は電力消費を抑えるために充電できなくなる設定になっていることが多いです。
しかしWindowsの場合は、パソコンの設定を変更することでスリープモード中でも充電可能となります。
手順としては、まずコントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」をクリックします。
その後、「システム」をクリックして設定画面を開き、以下の流れで進んでいきます。
①「電源とスリープ」を選択
②「電源の追加設定」を選択
③「プラン設定の変更」を選択
④「詳細な電源設定の変更」を選択
そして最後に、「USB設定」の項目にある「USBのセレクティブ サスペンドの設定」を「有効」に切り替えると、スリープ状態でもiPhoneの充電ができるようになります。
「アクセサリはサポートされていません」いう警告が出る場合
iPhoneで「アクセサリはサポートされていません」という警告が出る場合は、以下のような対処法を試してみてください。
- 何度か挿し直す
- ケーブルの破損を確認する
- ケーブルを純正品にする
- iOSをアップデートする
- iPhoneの充電ポートを掃除する
何をやっても充電できない場合

上記の対処法をすべて試しても駄目な場合は、それ以上自分で何かをしようとせず、下記内容を参考に行動してください。
Appleへ問い合わせ
いろいろ試した結果解決しなければ、Appleストアへの問い合わせを行ないましょう。
iPhoneに詳しいスタッフが、問題解決のために回答してくれます。
店舗へ修理を依頼
修理するしかないとわかった場合は、Appleの正規店、もしくは信用できる非正規店へ修理を依頼してください。
決して、自分で修理しようとはしないでください。
※信頼できる非正規店の選び方は後述します
iPhoneを買い替える
それなりの年数に渡ってiPhoneを使用している場合は、いっそのこと買い替えるというのも手です。
すべてのiPhoneには1年間の保証期間がついていますが、保証期間を大幅に過ぎ、何年にも渡って使用している場合、仮に故障個所を直したとしてもまた新たな故障が発生することも充分考えられます。
その都度修理費用がかかっていては、コストパフォーマンスが良くありません。
故障が発生するということは、iPhone本体が悲鳴を上げ始めているサインでもあるため、買い替えを検討するのもアリでしょう。
いらなくなったiPhoneは携帯処分.comで無料処分できます。
送料やデータ処分の費用も一切かかりません。
充電できないiPhoneの修理方法

ここでは、充電できないiPhoneの修理方法を次の4店舗に分けて紹介します。
- アップル
- ソフトバンク
- ドコモ
- au
iPhoneが壊れてしまい修理に出すことを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
アップル
アップルは下記の2つの方法で修理を行うことができます。
- 持ち込み修理
Apple 正規サービスプロバイダや Apple Store に製品を持ち込んで修理(来店予約が必要)
- 配送修理
Apple 指定の配送業者が自宅に製品を取りに行き、Appleへ配送
直接Appleに修理してもらう場合は、iPhoneの修理サービスより見積もりが可能です。
持ち込み修理は即日修理もしくはその日に済むケースもありますが、状況によっては受け取りまで数日から10日以上かかる場合もあります。
一方の配送修理は、端末が手元に届くまで10日から2週間程度です。
参照:iPhone の修理サービス – Apple サポート (日本)
ソフトバンク
ソフトバンクで修理をする場合は、次の3つの方法があります。
- ショップ修理
- 配送修理
- 配送交換
ソフトバンクは店頭修理サービス(※ソフトバンク表参道、ソフトバンク銀座、ソフトバンクグランフロント大阪、ソフトバンク名古屋、ソフトバンク仙台クリスロード)と修理取次サービスを行っていますが、どちらも一部店舗のみ、予約は必須となっています。
配送修理の場合は、Apple社 で提供している配送修理を利用します。
あんしん保証パック(i)あんしん保証パック(i)プラス、あんしん保証パック with AppleCare Servicesの場合は配送交換が利用でき、2週間程度で端末が手元に届きます。
参照:修理のお申し込み | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
ドコモ
ドコモでの修理は次の2種類があります。
- 即日修理:店内にて当日修理※
- お預かり修理:Apple修理センターへ取り次ぎ1週間~10日にて修理
即日修理も可能ですが、「DS丸の内店iPhone/iPad」「iPhone/iPadリペアコーナー 名古屋」のみでの受付となっており、状況によっては4〜7日の修理期間を要することもあります。
お預かり修理の場合は1週間から10日ほどかかります。
金額は保証サービスに応じて変わるため、事前に確認するようにしてください。
参照:iPhoneリペアコーナー | お客様サポート | iPhone | NTTドコモ
参照:iPhone修理取次(1週間~10日お預かり) | お客様サポート | iPhone | NTTドコモ
au
auは一部店舗のみで「iPhone・iPad 店頭修理サービス」を行っています。
「同日修理」に対応している店舗と「預かり修理」店舗があり、それぞれの店舗は下記のとおりです。
| 同日修理対応店 | 預かり修理対応店 |
| au Style SHINJUKU、au Style SENDAI、au Style みなとみらい、au Style NAGOYA、au Style OSAKA、au Style FUKUOKA、au Style 渋谷スクランブルスクエアやApple正規サービスプロバイダが対象 | 一部のau Style/auショップが対象です。 |
ただし、同日修理対応であっても、状況によっては数日かかることもあります。
参照:iPhone・iPad 店頭修理サービス | スマートフォン・携帯電話をご利用の方 | au
充電できないiPhoneの修理にかかる費用

充電できないiPhoneは充電口を修理する必要がありますが、費用は保証サービスに入っているか、いないかで異なります。
保証サービスに入っている場合の費用は定価の3分の1程度で済みますが、加入していない場合は3万円〜6万円程度かかります。
機種によって費用は大きく超えるものの、数万円は確実であり高額です。
iPhoneが充電できない時に注意すべき行動

急にiPhoneの充電ができなくなれば、少なからず焦りが生じるかと思われます。
ですが、焦りに任せて以下のような行動を取るのは避けてください。
むやみに衝撃を与えない
衝撃は、精密機械にとって害でしかありません。
昔は、映りの悪くなったテレビを叩いて直すといった手荒いやり方が巷で流行っていましたが、iPhoneのような精密機械に対してそんなことをしても、症状が悪化することこそあっても改善することはありません。
衝撃を与えれば直るかもしれないと考え、叩いたり落としたりするのは絶対にやめてください。
適当な店に修理を依頼しない
iPhoneの修理を依頼する場合は、「正規店」か「非正規店」かの二択となります。
正規店とは「Appleの認証を受けている店」のことで、非正規店は「Appleの認証を受けていない店」のことです。
これだけを見ると、誰が考えても正規店に依頼した方がよさそうに思えますが、必ずしもそうとは言えません。
正規店は、普段から非常に混雑しています。
その上、データが初期化されるため事前にバックアップを取る必要があったり、故障具合によっては何日も待たないといけないこともあります。
ところが、非正規店ではそういった面倒がありません。
もちろん非正規店の利用には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
【非正規店を利用するメリット】
■早めに対応してもらえる
■データが初期化されない
■正規店よりは費用を抑えられることがある
【非正規店を利用するデメリット】
■メーカー保証から外れてしまう可能性がある
■粗悪店にあたってしまうと、症状の再発や新たな不具合が発生してしまうことがある
■修理部品が純正品ではないため、下取りに出せなくなることがある
どれだけ待ってでも、バックアップの手間があっても、安心安全の正規店で修理したいのか?
メーカー保証がなくなっても、下取りに出せなくなっても、すぐに対応してくれる上に費用も抑えられる非正規店で修理したいのか?
ここは、価値観によって分かれるところです。
正規か非正規、どちらを選ぶべきかよく考え、自己責任で判断してください。
ただし、「修理なんてどこでもいいや」と適当な店に入って修理を依頼するのは厳禁。
同じ非正規店でも修理技術がピンキリですので、非正規店を利用する場合は以下の点に注意して慎重に店を選んでください。
- ネット上の評判が良い
- 周囲の友人や知人が問題なく利用している
- iPhoneの修理実績が豊富
- 修理費が安すぎない
特に修理費用については要注意です。
極端に修理費用が安いような店は、使用する修理部品も粗悪なものである可能性が高くなりますので敬遠するようにしてください。
独断で行動しない
「以前にこんな方法を試して直ったことがあるから、またやってみよう」
「ネット上でiPhoneを分解して修理してる動画やサイトがたくさんあるから、それを見ながら自分で修理してみよう」
こういった独断での行動は、症状が悪化する可能性が高いので絶対に避けてください。
特に分解行為は非常に危険です。
高度な知識を持っている人ならば別ですが、素人がネット上の情報を頼りに見様見真似で修理したところで、失敗に終わる可能性が高いです。
修理すると決めた場合は、勝手なことはせず、素直に専門店へ依頼しましょう。
まとめ:まずは自己解決を目指し、無理ならばAppleストアへ相談しよう
以上、iPhoneで充電できなくなる原因と、その対処法についてご紹介しました。
ご紹介した対処法をすべて試し、それでも駄目な場合はAppleストアに相談してみましょう。
ストアにいるのはiPhoneに詳しいスタッフばかりですから、自分が見落としていた意外な落とし穴を指摘してくれてあっさり解決するかもしれませんし、自己解決の次元ではないトラブルであるとわかることもあります。
なお、相談したからといって、そのままAppleストアで修理を依頼しないといけないわけではありません。
すでにAppleの保証から外れている場合や、何年も使っていて下取りにも出せないようなiPhoneの場合は、非正規店にて割安で修理してもらうという手もあります。
残っている保証期間や、少しでも早く直したいといった個人的都合などを鑑み、どう対応するのかを判断するのがよいでしょう。本体の故障で使えなくなってしまったiPhoneは携帯処分.comで無料処分できます。

監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。