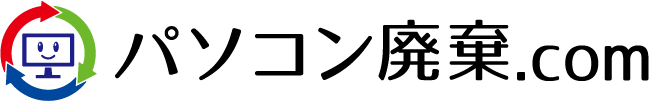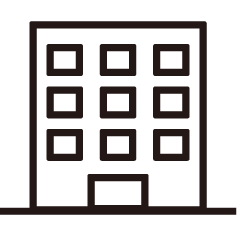404 Not Found
大手メーカーのNECパソコンでも、使用中に何らかの理由でキーボードが反応しなくなることがあります。
この記事では、キーボードで不具合が生じる事例と、その対処法について詳しく解説しています。
NECパソコンを利用している方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- NECのキーボードが反応しなくなる事例
- NECのキーボードで不具合が起きたときの対処法
NECパソコンでキーボードが反応しない事例と対処法

ここでは、NECパソコンでキーボードが反応しなかったり、正しく入力できなかったりする場合の原因と対処法を10個紹介しています。
キーボードで不具合が起きている方は、当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
すべてのキーが反応しない
NECパソコンでキーボードがまったく反応しない場合、さまざまな原因が考えられます。
パソコンの設定に問題があるケースやキーボードが故障しているケースなど事例は多岐にわたるため、状況を切り分けて判断する必要があります。
以下で紹介するトラブルも参考にしながら、原因に応じた対処方法を確認しましょう。
一部のキーのみ反応しない
一部のキーのみ押しても反応しない場合、物理的な不具合かパソコン側の設定のどちらかが原因と考えられます。
設定の見直しやパソコンの再起動を行っても改善しない場合は、そのキーのみ故障している可能性が高いでしょう。
また、キーボードの裏側にホコリが溜まっていると接触が悪くなりやすいため、定期的に掃除してホコリを取り除くことが大切です。
キーを長押ししないと反応しない
キーを長押ししないと入力ができない場合、フィルターキー機能が設定されている可能性があります。
フィルターキー機能とは誤入力を防ぐための機能で、キーが連続して押されると入力が無効になる・反応が遅くなるといった効果が付与されます。
以下の手順を参考に、フィルターキー機能を「無効」に変更してください。
【フィルターキー機能を無効にする手順】
- 「スタート」をクリックし、「設定」アイコン -「設定」を選択する。
- 設定メニューから「簡単操作」を選択する。
- 画面左側から「キーボード」を選択し、「フィルターキー機能の使用」をオフにする。
参考:Windows 10でキーを押し続けないと文字を入力できない場合の対処方法
設定変更後、キーを長押ししなくても入力できるか確認してください。
テンキーが反応しない
テンキーで数字を入力できない場合、テンキーの入力機能がオフになっている可能性があります。
「Num Lock」キーを押して、ランプが点いていればテンキーでの数字入力が可能です。
もしテンキーがオンになっているのに反応しない場合は、マウスポインターの移動操作が割り当てられていることが考えられます。
以下の手順を参考に設定を変更してください。
【マウスキー機能を無効にする手順】
「スタート」をクリックし、「設定」を選択する。
画面左側から「アクセシビリティ」を選択し、「マウス」をクリックする。
「テンキーを使用してマウスポインターを移動する」をオンにする。
参考:Windows 11でキーボードのテンキーから数字が入力できない場合の対処方法
設定変更後、テンキー入力が正しくできるか確認してみましょう。
キーボードの配列どおりに入力できない
キーボードの配列どおりに文字や数字を入力できない場合、日本語以外のキーボードドライバーが設定されている可能性があります。
以下の手順に従って、日本語の標準ドライバーに更新を行ってください。
【キーボードドライバーを更新する手順
- 「スタート」を右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択する。
- 「キーボード」を展開し、キーボードドライバーをダブルクリックする
- 「ドライバー」タブを選択し、「ドライバーの更新」をクリックする。
- 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」をクリックする。
- 「コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します」をクリックする。
- 日本語の標準キーボードドライバーまたは初期設定時のキーボードドライバーを選択し、「次へ」をクリックする。
- 画面の指示に従って更新を行う。
参考:Windows 11でキーボードの配列通りに入力できない場合の対処方法
文字が上書きされる
キーボード入力で文字が上書きされる場合、「上書きモード」が有効になっていることが考えられます。
上書きモードのオン・オフは、「Insert」キーで切り替えが可能です。
「Insert」キーは知らない間に触ってしまうことがあるため、注意してください。
アルファベットキーを押しても数字が入力される
NECのノートパソコンでアルファベットキーを押しても数字が入力される場合、NumLock機能が有効になっていることが考えられます。
この状態だと、一部のアルファベットキーがテンキーとして動作してしまいます。
「NumLock」キーを押して機能を無効にし、アルファベットを入力できるか確認してください。
アルファベットが大文字で入力される
何もしていないのにアルファベットが大文字で入力される場合、CapsLock機能が有効になっていることが考えられます。
「Shift」キーを押しながら「CapsLock」キーを押して、CapsLock機能を無効化してください。
なお、CapsLock機能のオン・オフは、キーボードのランプまたは言語バーの表示で確認することが可能です。
日本語入力ができない
日本語でのキーボード入力ができない場合、入力モードや入力言語が日本語以外に設定されている可能性があります。
以下の記事を参考に、設定の見直しを行ってください。
設定変更後、キーボードで正しく日本語入力ができるか確認してみましょう。
ワイヤレスキーボードが反応しない
NECパソコンでワイヤレスキーボードが反応しない場合、何らかの原因でキーボード操作が正しく認識されていない可能性があります。
接続に一時的な不具合が起きていることも考えられるため、まずは再接続を試してみるとよいでしょう。
それでも症状が改善しない場合は、以下の記事を参考に利用環境や設定の見直しを行ってください。
参考:Windows 11でワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスが正常に動作しない場合の対処方法
NECパソコンでキーボードの不具合が解消しないときは?

上記の対処法を行ってもキーボードが反応しない場合、パソコンの設定以外に問題があることが考えられます。
ここでは、具体的な対処法を3つ紹介します。
パソコンを再起動する
キーボードが反応しない場合、まずはパソコンの再起動を試してみるとよいでしょう。
パソコンを再起動することで使用中のメモリがリセットされるため、一時的な不具合であれば改善できることがあります。
再起動を行っても症状が改善しない場合は別の方法を実施してください。
放電処置を行う
パソコンを長時間連続して使用していると、帯電によってキーボードの動作に不具合が生じることがあります。
以下の手順を参考に、パソコンの放電処置を行ってください。
【NECパソコンを放電する手順(バッテリーを取り外せない場合)】
- パソコンを完全にシャットダウンさせる。
- すべての周辺機器を取り外す。
- 本体にACアダプターを接続する。
- 電源ボタンを20秒間長押しし、バッテリ充電ランプが点滅したら指を離す。
- ACアダプターを取り外す。
- 再度ACアダプターを接続し、パソコンの電源を入れる。
【NECパソコンを放電する手順(バッテリーを取り外せる場合)】
- ディスク・USBメモリ・SDカードなどをすべて取り出し、パソコンを完全にシャットダウンさせる。
- 周辺機器・ケーブル・バッテリーをすべて取り外す。
- そのまま90秒以上放置する。
- バッテリー・電源ケーブル・マウス・キーボードを接続し、パソコンの電源を入れる。
キーボードを掃除する
キーボードを掃除することでホコリやゴミがなくなり、反応が復活することがあります。
ダスターで目に見える汚れを払ってから、小型ノズルの掃除機やダストブロワーなどで隙間部分に溜まっているホコリなどを取り除きましょう。
分解して掃除することも可能ですが、故障につながる恐れもあるため作業は慎重に行ってください。
キーボードを修理する
ここまで紹介した方法を試してもキーボードが反応しない場合、物理的に故障していることが考えられます。
キーボードの修理は公式の修理サービスや専門の修理業者などで受け付けているため、一度見積もりを出してもらうとよいでしょう。
ただし、キーボードの型式や状態によっては、新しい機器に買い替えたほうが安く済む場合があります。
まとめ:キーボードが反応しない原因を見つけよう

NECパソコンでキーボードが反応しない場合、原因としてさまざまな要素が考えられます。
不具合の内容によって適切な対処法が異なるため、状況を切り分けながら原因を探っていくことが大切です。
また、キーボードを乱雑に扱ったり、強い衝撃を与えたりすると物理的な故障を引き起こす恐れがあります。
キーボードが使えなくなるだけでなく修理や買い替えに費用がかかるため、取り扱いには十分に注意しましょう。
今回の記事もぜひ参考にしてくださいね。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
NECのパソコンを使っていると、突然パソコンの画面が固まって、マウスやキーボードでの操作ができなくなるフリーズが起こることがあります。
フリーズの原因はさまざまですが、原因に合わせて適切に対処することで比較的簡単に直るケースも多いです。この記事では、NECのパソコンがフリーズする原因や対処法、強制終了する方法を詳しく解説します。
NECのパソコンがフリーズしたら、この記事を参考に対処してみてください。
【この記事でわかること】
- パソコンがフリーズしたらしばらく待ってみよう
- パソコンがフリーズする原因はさまざま
- パソコンがフリーズしたら再起動や強制終了などを実行する
NECパソコンがフリーズした?まずは状況を確認する

パソコンのフリーズとは、マウスやキーボード操作でも反応せず、画面が真っ暗のままになる症状のことを言います。
NECのパソコンがフリーズすると、さまざまなボタンを押したり、電源を切ったりするかもしれません。しかし、強制的に電源をシャットダウンすると、システムに不具合が生じたり、パーツが破損したりと、パソコンの故障に繋がる可能性があります。
状況によっては、フリーズではない可能性もあります。まずは落ち着いて、NECのパソコンをチェックしましょう。
しばらく時間を置く
容量が大きいファイルをダウンロードする、容量が大きいファイルを開くなど、パソコンの処理に時間がかかる作業をしている場合は、一時的にフリーズしたようにパソコンの動きが重くなることがあります。
この場合、処理に時間がかかっているだけであれば、時間が経てば再び動作を再開します。およそ5~10分経っても、NECのパソコンに動きがない場合は、フリーズしていると考えましょう。
アクセスランプを確認する
アクセスランプが点灯、点滅している場合は、ハードディスクやブルーレイディスクなどが動作しており、データの読み書きをしている状態です。
アクセスランプ点灯中に強制終了や電源を切ると、データが消失する可能性もあるため、ランプが消えるまでしばらく待ちましょう。
アクセスランプが点灯している場合はフリーズしているのではなく、データの読み込みに時間がかかっている可能性が高いです。しばらく待ってから、再度パソコンを操作してみましょう。
マウスやキーボードの周辺機器を確認する
パソコンがフリーズした場合には、マウスやキーボードなどの周辺機器も確認しましょう。マウスやキーボード操作ができない場合は、充電や電池が切れて、操作できない可能性があります。電池交換や充電してから、再度操作してみましょう。
また、ワイヤレスキーボードやマウスは、一定時間操作しないと、スリープ状態になる場合があります。通常はクリックやボタン操作などでスリープから復帰しますが、なんらかの原因により再開できないことがあります。
充電などに問題がない場合は、マウスやキーボードなど周辺機器のUSB受信器を接続しなおすのもおすすめです。NECのパソコンがフリーズしたように見えても、パソコン本体の問題ではなく周辺機器の接続の問題の可能性もあるため、1つ1つ、冷静に確認しましょう。
パソコンのキーボードがおかしい場合の対処法は、下記記事でも詳しく紹介しています。
キーボードがおかしいときはどうする?状況別にすぐできる対処法を解説>>
NECのパソコンがフリーズする原因
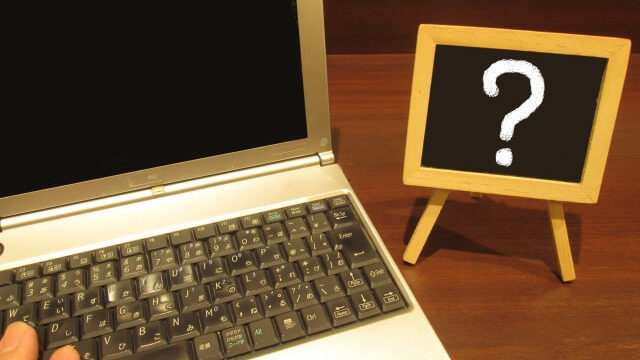
NECのパソコンがフリーズする原因は、主に次の6つが考えられます。
- 熱暴走
- ハードディスクの故障
- パソコンのメモリ不足
- システムの不具合
- 常駐プログラムが多い
- ウイルス(マルウェア)感染
それぞれの原因について、詳しく解説します。NECのパソコンがフリーズする原因を知り、対策していきましょう。
熱暴走
パソコンは非常に熱に弱く、本体が高温になると熱暴走を起こします。通常は、ファンによってパソコン内部の温度上昇を抑えています。しかし、直射日光があたる場所や、ファンの排気口をふさぐ場所にパソコンを置いたり、パソコン内部にホコリが溜まっていたりすると、排熱処理が追いつかなくなり、熱暴走を起こします。熱暴走を起こすと、パソコンは頻繁にフリーズするようになります。
室温が高い場合はエアコンの効いた涼しい部屋でパソコンを使う、ホコリが溜まっている場合は掃除をするなどの熱暴走対策が必要です。熱暴走を起こすと、内部パーツを破損する原因にもなるため、内部に熱がこもらないように対策することが重要です。
ハードディスクの故障
ハードディスクが寿命を迎えると、次第に動きが遅くなり、頻繁にフリーズするようになります。ハードディスクの寿命は3~5年程度と言われており、5年程度使用している場合は、ハードディスクの寿命を疑いましょう。
特に「カチカチ」「カタカタ」など異音がする場合は、ハードディスクが破損している可能性も高いです。ハードディスクを故障したまま使い続けると、症状がどんどん悪化し、最終的にパソコンが完全に故障します。ハードディスクの故障の場合は修理や交換がおすすめです。
HDDの異音については、下記記事でも詳しく紹介しています。
HDDから異音がする!カチカチなど音の種類と対処方法を解説>>
パソコンのメモリ不足
パソコンのメモリとは、パソコン使用中の作業スペースのようなものです。メモリは4GB、8GBなどと表記され、大きいほど一度に複数の作業を同時におこなえます。
メモリの容量が足りなくなると、一度に複数のデータを処理できなくなり、処理速度が追いつかず、パソコンがフリーズしたり、重くなったりします。
メモリ不足は、「タスクマネージャー」の「パフォーマンス」から確認可能。メモリを70~80%使用している場合はメモリ不足でフリーズしている可能性が高いです。メモリ不足でNECのパソコンがフリーズする場合は、データの整理やメモリの増設が有効です。複数のタブを開いて作業する機会が多い場合は、最低でも8GBのメモリが必要です。
頻繁にフリーズする場合は、パソコンのメモリ使用量や容量を確認しましょう。
アプリの不具合
特定のアプリを使用した場合にフリーズする場合は、アプリの不具合の可能性があります。アプリが不具合を起こすと、「応答していません」とメッセージが表示されることがあります。
アプリのバージョンが古い場合は、アプリのバグが修正されていない可能性も。フリーズが頻繁に起こるなどトラブルの原因となるため、最新版のアプリを使用しましょう。
システムの不具合
Windows Updateの失敗などによって更新プログラムが多く溜まっている場合は、システムの不具合によってフリーズしているケースもあります。
更新プログラムが溜まったままの場合、Windows Updateが失敗しやすくなり、再試行を続けることにより、パソコンの動作が不安定になりフリーズが起こりやすくなります。
ウイルス(マルウェア)感染
パソコンがウイルス感染を起こした場合、頻繁にフリーズするようになります。例えば、「パソコンを高速化します。」「この番号に電話してください。」などの表示が出続ける場合などは、ウイルス感染の可能性が高いでしょう。
ウイルスに感染するのは、ソフトのインストール時やメールに添付されたURLをクリックした時などです。特定の動作をした後にフリーズが頻発するようになった場合はウイルス感染を疑いましょう。
タスクマネージャーで不具合の原因となっているソフトを探すことも可能です。身に覚えのないソフトがあれば、アンインストールしましょう。
パソコンがウイルス感染した場合の対処法は、下記記事でも詳しく紹介しています。
常駐プログラムが多い
常駐プログラムとは、パソコンの裏で稼働し続けているソフトのことです。セキュリティソフトやアプリの更新プログラムなどがあり、パソコンを起動すると動き始めます。
常に動き続けているため、プログラムが多いほどパソコンに負荷がかかります。常駐プログラムは不要なものは無効にできます。時々設定を見直し、不要なものは無効にするのがおすすめです。
NECパソコンがフリーズした場合の対処法
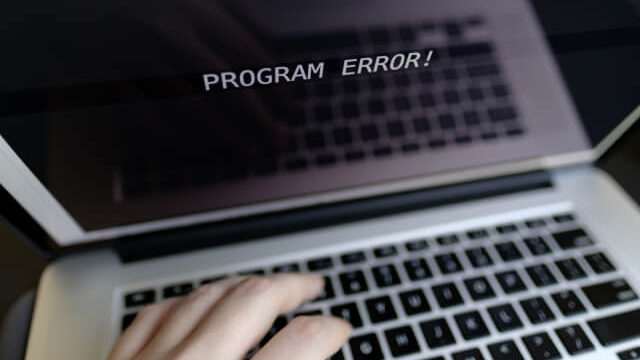
ここからは、NECのパソコンがフリーズした場合の対処法を紹介します。
まず、パソコンがフリーズした場合は5~10分程度そのまま待ちましょう。ファイルのデータ容量が大きい場合などは処理に時間がかかるため、フリーズではない可能性も考えられるためです。
5~10分待ってもパソコンが反応しない場合は、フリーズしていると考えて、次の対処法を実行しましょう。
- 再起動する
- アプリケーションを強制終了する
- パソコンを強制終了する
- 放電する
- セーフモードで起動する
- 常駐ソフトを無効にする
- 高速スタートアップを無効にする
- WindowsUpdateを実行する
- 最新のデバイスドライバーをインストールする
- ウイルススキャンを実行する
- BIOSを初期化する
- システムの復元を実行する
- 初期化する
それぞれの対処法を順番に解説します。
再起動する
パソコンがフリーズしている場合は、再起動も有効です。再起動は、パソコンの動作が不安定になっている場合にパソコンの状態を保持せず起動するため、フリーズが改善する可能性があります。
マウス操作ができる場合は、通常通りスタートボタンから電源を選び、再起動を選択します。キーボード操作だけができる場合は、ショートカットキーで再起動しましょう。
【ショートカットキー】で強制終了する場合
- 「Alt」キーを押しながら「F4」キーを押す
- 「Windowsのシャットダウン」が表示される
- 「再起動」を選択
次の方法でも、強制終了できます。
- 「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Delete」キーを押す
- パソコン画面右下の電源アイコンを選択
- 「再起動」を選択
- 「Enter」を選択
これらの方法でも再起動できない場合は、サインアウトすることで、再起動できる場合があります。
- 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押す
- 「シャットダウンまたはサインアウト」から「サインアウト」をクリック
- ロック画面が表示される
- 画面上をクリック、もしくは「Enter」キーを押す
- サインイン画面が表示される
- 画面右下の「電源」マークをクリック
- 「再起動」を選択
以上で終了です。それでも再起動できない場合は、パソコンを強制終了してから再起動しましょう。
アプリケーションを強制終了する
アプリを実行中にフリーズした場合は、使用中のアプリを強制終了しましょう。閉じるボタンで終了できる場合は、通常の操作で終了するのがおすすめです。
強制終了するアプリで編集中のデータは保存できません。アプリが応答なしの場合でも、データ処理中の可能性があり、しばらく待つとフリーズが改善することがあります。しばらくフリーズが続く場合は、アプリの強制終了を実行しましょう。
- 「Ctrl」+「Alt」+「Delete」をクリック
- 表示された項目から「タスクマネージャーの起動」をクリック
- 「アプリケーション」タブからフリーズしているアプリを選び「タスクの終了」をクリック
以上で、実行中のアプリケーションを強制終了可能。アプリケーションを強制終了できない場合は、パソコン本体を強制終了します。
パソコンを強制終了する
パソコンがキーボード操作できる場合は、ショートカットキーもしくはメニューを表示して強制終了できます。
【メニューを使って強制終了する場合】
- 「Windows」キーを押しながら「x」キーをクリック
- キーボードの「矢印」キーで「シャットダウンまたはサインアウト」を選択
- 「Enter」キーを押す
- 表示された一覧から「シャットダウン」を選択
- 「Shift」キーを押しながら「Enter」キーを押す
【ショートカットキーで強制終了する場合】
- 「Alt」キーを押しながら「F4」キーを押す
- 「Windowsのシャットダウン」が表示される
- 「シャットダウン」を選択
次の方法でも、強制終了できます。
- 「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Delete」キーを押す
- パソコン画面右下の電源アイコンを選択
- 「シャットダウン」を選択
- 「Enter」を選択
参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 10でフリーズしたパソコンを強制終了する方法
キーボードもマウス操作もできない場合は、電源を押し続ければ強制終了できます。それでも強制終了できない場合は、電源アダプターを抜いて電力の供給を止めましょう。ただし、電源ボタンによる強制終了するは、ハードディスクやシステムファイルの破損などの影響を与える場合もあります。なるべく実行しないようにしましょう。
NECのパソコンを強制終了した後は、しばらく放電するのがおすすめです。
放電する
パソコンは電子機器のため、通常の使用でもパソコン内部には電気がたまります。パソコンの電源ユニットには、パソコンに安定した電力を供給するために電力をためるパーツである、コンデンサが搭載されています。
パソコンを長時間使用していると、コンデンサ周辺に電気がたまり、帯電が起こります。パソコン内部に帯電すると、突然電源が落ちる、画面が真っ暗になる、フリーズするなどの不具合が起こります。
パソコン内部の電力を放出すれば、フリーズが改善する可能性があります。以下の手順で、パソコンを放電しましょう。
- パソコンをシャットダウンする(正常にシャットダウンできない場合は強制終了する)
- 電源ケーブルやマウス、キーボードなどの周辺機器を取り外す。ノートパソコンの場合はバッテリーパックも取り外す。
- そのまま2〜3分放置する。
- 周辺機器や電源ケーブルなどを元通りに接続する
- パソコンを再起動する
以上で放電が完了します。
セーフモードで起動する
セーフモードとは、最小限のシステム構成でパソコンを起動することです。フリーズしている原因を切り分けできるため、Windowsの診断用の起動モードとして利用できます。パソコンがフリーズした場合も、原因が特定できる可能性があります。
NECのパソコンをセーフモードで起動するには、3つの方法があります。ここでは、Windows11の場合の方法を紹介します。Windows11で再起動する場合は、回復キーの入力を求められる場合があります。あらかじめ回復キーをメモしておくか、暗号化機能を無効にしてください。
【設定から起動する方法】
- 「スタート」から「設定」をクリック
- 「システム」から「回復」をクリック
- 「回復オプション」の「今すぐ再起動」をクリック
- 「デバイスを再起動するため作業内容を保存します」という画面が表示されたら「今すぐ再起動」をクリック
- しばらく待つ
- 「オプションの選択」から「トラブルシューティング」をクリック
- 「詳細オプション」をクリック
- 「スタートアップ設定」をクリック
- 「再起動」をクリック
- NECのロゴ画面が表示されるので画面が切り替わるまで待つ
- 「BitLocker」が表示されたらキーボードの「Enter」キーを押す
- 「このドライブの回復キーを入力してください」の欄にあらかじめメモした回復キーを入力
- キーボードの「4」キーを押し「セーフモードを有効にする」を選択
- サインインする
【システム構成から起動する方法】
- 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押す
- 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 「名前」ボックスに「msconfig」と入力して「OK」をクリック
- 「ブート」タブをクリック
- 「ブートオプション」欄の「セーフブート」にチェックを入れて「OK」をクリック
- 「システム構成の変更を有効にするには、再起動が必要な場合があります。」とメッセージが表示されたら「再起動」をクリック
- NECのロゴ画面でサインイン画面が表示されたらサインインする
【コマンドから起動する方法】
- 「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、表示された一覧から「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 「名前」ボックスに「shutdown /r /o /t 0」と入力し、「OK」をクリック
- 以降の手順は【設定から起動する方法】の「手順6」以降と同じ
以上、それぞれの手順が完了すると、デスクトップ画面が表示され、画面の四隅に「セーフモード」と表示されていれば、セーフモードで起動している状態です。
セーフモードで起動して問題が発生しない場合は、基本的な設定やドライバーなど基本的な構成には不具合がないことがわかります。
参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 11をセーフモードで起動する方法
常駐ソフトを無効にする
NECのパソコンがフリーズする原因には、常駐しているソフトが関係している場合もあります。常駐ソフトとは、パソコンと同時に起動するソフトやアプリのことです。常駐ソフトがフリーズする原因の可能性がある場合は、いったんすべて無効にして、1つ1つ有効にしてフリーズする原因になるソフトを探しましょう。
ただし、常駐ソフトをすべて無効にすると、セキュリティソフトも無効になり、ウイルス感染のリスクが高まります。LANケーブルや無線LAN接続を切断して、インターネット接続を切断し、元の状態に戻せるように、手動で復元ポイントを作成しておきましょう。ここでは、Windows11で常駐ソフトを無効にする方法を解説します。
【常駐ソフトをすべて無効にする方法】
- 「スタート」から「タスクマネージャー」をクリック
- 「スタートアップアプリ」タブをクリック
- 常駐ソフトの一覧が表示される
- 「状態」欄が「有効」になっているソフトをクリックして「無効化」をクリック
- すべてのソフトを無効にする
- パソコンを再起動する
参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 11で問題のある常駐ソフトを特定する方法
パソコンが再起動したら、再びタスクマネージャーを開き、無効化にしたアプリを順番に有効化して、再起動を繰り返します。パソコンが再起動したら状態を確認し、フリーズする原因となる常駐ソフトを特定しましょう。
高速スタートアップを無効にする
高速スタートアップとは、パソコンの起動を高速化するために、シャットダウン時にメモリやCPUの状態を保存しておく機能のことです。パソコンが高速で起動できる反面、正常に起動できないなどトラブルの原因となることも多いです。
無効にしても、起動に時間がかかることの他にデメリットはないため、無効にするのがおすすめです。パソコンが正常に操作できる場合は、スタートから操作しましょう。
- 「スタート」右クリックし「電源オプション」をクリック
- 「電源とスリープ」が表示されるので「電源の追加設定」をクリック
- 「電源オプション」が表示されるので「電源ボタンの動作の選択」をクリック
- 「システム設定」が表示されるので「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック
- 「シャットダウン設定」にある「高速スタートアップを有効にする(推奨)」をクリックしチェックを外す
- 「変更の保存」ボタンをクリック
以上で高速スタートアップが無効になります。NECのパソコンがフリーズして、正常の操作ができない場合は、次の手順を試してください。
- パソコンの電源を切る
- パソコンの電源を入れてNECのロゴが表示されたら「F2」キーを何回か押す
- 「BIOSセットアップユーティリティ」が表示される
- キーボードの矢印キーで「Exit(終了)」を選択(Enterを押さずに次の手順へ)
- 矢印キーで「HDD Recovery(HDDリカバリー)」を選択して「Enter」キーを押す
- 「Execute HDD Recovery(HDDリカバリーを実行しますか)」が表示される
- 「Yes(はい)」を選択し「Enter」キーを押す
- NECのロゴ画面が表示されたら画面が切り替わるまで待つ
- 「オプションの選択」が表示されたら「PCの電源を切る」をクリック
以上で完了です。次回パソコンの電源を入れる際には、高速スタートアップが無効の状態で起動します。
参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 11で高速スタートアップを無効にする方法
Windows Updateを実行する
Windowsのシステムに不具合が起こると、頻繁にフリーズすることがあり、Windows Updateを実行することで不具合が修正できる場合があります。
Windows Updateはインストールするプログラムや環境によって時間がかかる場合もあります。パソコンを使用しない時間に実行しましょう。
- 作業中のソフトやアプリをすべて終了する
- 「スタート」から「設定」をクリック
- 「Windows Update」をクリック
- 表示された一覧から「更新プログラムのチェック」をクリック
- 「更新プログラムを確認しています…」というメッセージが表示されたらしばらく待つ
- 更新プログラムがあれば「今すぐインストール」をクリック
- インストールが完了すると「最新の状態です」と表示される
以上でWindowsが最新の状態になります。「更新の履歴」を確認すれば、更新プログラムが正常にインストールされていることを確認できます。
参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 11のWindows Updateを手動で行う方法
最新のデバイスドライバーをインストールする
パソコン内部の装置や、外部に接続されているマウスやキーボードなどの周辺機器のドライバーの不具合でパソコンがフリーズしている可能性があります。最新バージョンに更新することで、フリーズが解消する場合もあります。
ここでは、Windows11のディスクドライバーをインターネットから検索して最新バージョンに更新する方法を紹介します。
- 「スタート」から「設定」をクリック
- 「システム」から「バージョン情報」をクリック
- 「関連」から「デバイスマネージャー」をクリック
- 目的のデバイス名をダブルクリック
- 表示されたデバイスドライバーを右クリック
- 「ドライバーの更新」をクリック
- 「ドライバーを自動的に検索」をクリック
- オンラインでドライバーを検索し最新のドライバーが見つかれば自動でダウンロードとインストールがおこなわれる
- 正常に更新されたら「閉じる」をクリック
参考: NEC LAVIE公式サイト Windows 11でデバイスドライバーを最新バージョンに更新する方法
以上でドライバーの更新は終了です。マウスやキーボード、ディスプレイなど、周辺機器のドライバーを更新し、フリーズが直るかを確認しましょう。
ウイルススキャンを実行する
NECのパソコンが頻繁にフリーズする場合は、ウイルス感染も考えられます。
Windowsには、ウイルス対策ソフト「Windows Defender」が最初から備わっています。通常は有効ですが、他のウイルス対策ソフトを導入している場合は、自動で無効になります。「Windows Defender」でスキャンする場合は、他のウイルス対策ソフトをアンインストールして、有効にしてから実行しましょう。
- 「Windows」キーを選択
- 「Windowsセキュリティ」をクリック
- 「ウイルスと脅威の防止」をクリック
- 「スキャンのオプション」をクリック
- 「フルスキャン」をクリック
- 「今すぐスキャン」をクリック
パソコン全体をスキャンする場合は、ウイルススキャンに1時間以上かかる場合があります。スキャン実行中は、パソコンを使用できなくなるため時間に余裕を持って実行しましょう。
BIOSを初期化する
BIOSとはパソコンを起動したときに最初に起動するプログラムのことで、マウス、キーボード、CPU、メモリなどのハードウェアの管理や制御をします。
BIOSを初期化すると、ハードウェアの構成が工場出荷状態に戻ります。ハードウェアの構成とは、パソコン本体の設定や情報の確認、電源や起動方法の設定、セキュリティやパスワード、周辺機器の接続設定など。
BIOSの初期化によって、フリーズなどの不具合が解消する可能性があります。なお、ハードディスクを初期化するものではないため、データは削除されません。
- パソコンの電源を切る
- NECのロゴが表示されたら、「F2」キーを押す
- 「BIOSセットアップユーティリティ」が起動する
- キーボードの「F9」キーを押す
- 「Load Optimized Defaults?(デフォルト値をロードしますか?)」というメッセージが表示される
- 矢印キーで「Yes(はい)」を選択し「Enter」キーを押す
- 「F10」キーを押す
- 「Save configuration and reset?(設定の変更を保存して終了しますか?)」というメッセージが表示される
- 矢印キーで「Yes(はい)」を選択し「Enter」キーを押す
- Windowsが起動する
参考: NEC LAVIE公式サイト Windows 11でBIOSを初期化する(パソコン購入時の状態に戻す)方法
BIOSを初期化しても、フリーズが直らない場合もあります。その場合は、システムの復元やパソコン本体の初期化を検討しましょう。
システムの復元を実行する
システムの復元を実行すれば、パソコンを不具合のない状態まで戻すことができます。ただし、以下の場合はシステムの復元を実行できません。
- 正常な状態のパソコンの復元ポイントが作成されていない
- ハードディスクの容量が128GB以下の場合
システムの復元には時間がかかるため、時間に余裕があるときに実行しましょう。ノートパソコンの場合は、ACアダプターを接続して実行しましょう。
- パソコンの電源を切る
- NECのロゴが表示されたら、「F2」キーを押す
- 「BIOSセットアップユーティリティ」が起動する
- 矢印キーで「Exit(終了)」を選択(Enterは押さない)
- 矢印キーで「HDD Recovery(HDDリカバリー)」を選択し「Enter」キーを押す
- 「Execute HDD Recovery(HDDリカバリーを実行しますか?)」が表示されたら「Yes(はい)」を選択し「Enter」キーを押す
- NECのロゴが表示されたら画面が切り替わるまで待つ
- 「オプションの選択」から「トラブルシューティング」をクリック
- 「詳細オプション」をクリック
- 「システムの復元」をクリック
- 「次へ」をクリック
- 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します。」というメッセージが表示される
- 一覧から「復元ポイント」を選択して「次へ」をクリック
- 「影響を受けるプログラムの検出」をクリック
- 「削除されるプログラムとドライバー」や、システムの復元実行後に「復元が見込まれるプログラムとドライバー」を確認して、問題がなければ「閉じる」をクリック
- 「完了」をクリック
- メッセージを確認し「はい」をクリック
参考: NEC LAVIE公式サイト Windows 11でWindows(OS)が起動しない状態からシステムの復元を行う方法
システムの復元が完了すると、自動的にパソコンが再起動します。再起動後、システムの復元が正常に完了したことを確認できたら「閉じる」をクリックします。
初期化する
これまでの紹介した方法を試しても、NECのパソコンのフリーズが直らない場合は、パソコンを初期化しましょう。パソコンを初期化すると、工場出荷状態に戻るため不具合も解消する可能性が高いです。ただし、パソコン内のデータやインストールしたソフトやアプリなどは削除されます。アプリやソフト内のログインIDやパスワードも削除されるため、あらかじめデータのバックアップを取ったり、必要な情報をメモしたりしましょう。
周辺機器が接続されている場合はすべて取り外します。また、電源を接続し初期化中に電源が切れないようにしましょう。
- 「スタート」から「設定」をクリック
- 「Windows Update」の「その他のオプション」から「詳細オプション」をクリック
- 「追加オプション」から「回復」をクリック
- 「回復オプション」から「PCをリセットする」をクリック
- オプション選択画面で、「個人用ファイルを保持する」か「すべて削除する」を選んでクリック
- 「ローカル再インストール」をクリック
- 「設定の変更」をクリック
- 「プレインストールされていたアプリを復元しますか?」のメッセージが表示されたら「はい」「いいえ」のどちらかを選択
- 「確認」をクリックし「次へ」をクリック
- 内容を確認し「リセット」をクリック
参考: NEC LAVIE公式サイト Windows 11でハードディスク内のデータを使用して再セットアップを行う方法
個人用ファイルを保持すると個人用ファイルのデータを残して初期化できます。また、プレインストールされたアプリを復元しますか?で「はい」を選択すると、NECのパソコンに最初からインストールされていたアプリも復元できます。
「すべて削除する」を選ぶと、パソコン内のデータはすべて削除されます。さらに「データのクリーニングを実行しますか?」で「はい」を選択すると、ドライブのクリーンアップも実行されます。パソコンを売却する場合や譲渡する場合は選択しましょう。
NECのパソコンが頻繁にフリーズする場合は買い替えも検討

すべての対処法を実行してもNECのパソコンが頻繁にフリーズする場合は、故障も考えられます。例えばハードディスクの寿命は3~5年。そのため5年程度使用したパソコンは、不具合が起こりやすくなります。
寿命を迎えたパソコンは、頻繁にフリーズしたり、突然パソコンが落ちたりと、さまざまな不具合が起こり、最終的には完全に故障します。パソコンが完全に故障すると、保存していたデータの復元などが難しくなるため、完全に故障する前に買い替えるのがおすすめです。
古いパソコンはパソコン廃棄.comのようなサービスを利用すると、無料でパソコンを処分できます。段ボール箱にパソコンを詰めて着払いで発送するだけで、簡単にパソコンを処分可能。
故障したパソコンでも問題ありません。パソコン内のデータも無料で安全に消去してくれるため、安心して処分できます。
まとめ:NECのパソコンがフリーズしたら適切な対処法で解決できる

NECのパソコンがフリーズしたら、すぐに対処法を試すのではなく、しばらく待ってみましょう。重いデータやソフトをインストールしている場合は、処理に時間がかかっている可能性もあります。ハードディスクのアクセスランプを確認し、点灯していないことを確認することが大切です。
パソコンがフリーズする原因はさまざまですが、適切に対処することで改善する場合もあります。しかし、パソコンの寿命などでフリーズが頻発している場合は解決が難しいこともあり、何度もパソコンがフリーズする場合は買い替えがおすすめです。
パソコン廃棄.comでは古くなったパソコンを無料で処分できます。申し込みも不要で、古くなったパソコンを箱詰めして発送するだけと手続きも簡単です。何度もフリーズするパソコンを使い続けていると、フリーズの対処に時間がかかってしまいます。新しいパソコンで、快適な作業環境を手に入れましょう。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
家のアンペア数のオーバーや、落雷などが原因で停電し、パソコンが突然シャットダウンすることがあります。
ノートパソコンであれば停電の影響は受けないものの、コンセントで給電するデスクトップパソコンは、停電の被害を大きく受けてしまいます。
場合によっては、パソコンが上手く起動起動しなかったり、データが消去したりするケースもあり、停電には注意したいものです。
しかし、なかにはたかが停電と思っている方もいるでしょう。
そこでこの記事では
- 停電でパソコンが受ける影響
- パソコンの停電対策
を徹底解説します。
停電でパソコンが受ける影響
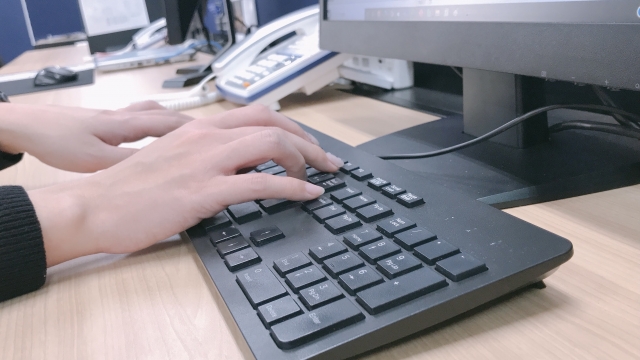
停電が起こると、パソコンはさまざまな影響を受けます。
具体的な影響としては、下記の4つです。
- 作業中のデータが消える
- 起動できなくなる可能性がある
- ハードディスクが壊れる
- 周辺機器に異常が発生する
ここでは、それぞれの原因を紹介します。
作業中のデータが消える
WordやExcel、クラウド上で作業をしているときに急に停電すると、正常に保存されず作業途中のデータが消えてしまいます。
ソフトによっては停電直前のデータを自動保存できる機能もあるものの、作業中のデータが全て消えてしまう可能性は高いです。
とくに仕事のデータが消えると大きな影響が出るため、本記事で紹介する停電対策はしっかりと行いたいものです。
起動できなくなる可能性がある
急な停電はOSを起動するためのデータを壊すことがあり、そうなるとOSの起動ができなくなります。
そうなるとパソコン自体が起動できなくなってしまい、作業ができません。
また、普段使用しているソフトのデータが破損する可能性もあり、破損するとソフトが使えなくなってしまいます。
しっかりと対策をして、パソコンが故障しないようにしましょう。
ハードディスクが壊れる
パソコンの起動中に突然停電が起こると、ハードディスク内の磁気ディスクに傷がついて壊れる恐れがあります。
ハードディスクに傷がつくと読み取りができなくなり、保存されているデータが失われてしまいます。
仕事用のパソコンや大事なデータを保存している場合は、要注意です。
ハードディスクの復旧を初心者が行うのは難しく、すぐさまパソコン業者に依頼する必要があります。
周辺機器に異常が発生する
急な停電によって影響を受けるのはパソコン本体だけではありません。パソコンに接続している周辺機器など、電源プラグを挿して使用している機器は停電による影響を受ける可能性があります。
例えば、モデム・ルーターなどの機器が壊れてしまうとインターネットに接続できなくなります。
停電時のパソコンへの悪影響を防ぐ方法

停電をするのを防ぐのは難しいものの、事前に対策をしておくことでパソコンへの悪影響を防ぐことができます。
具体的な対策方法としては、下記の6つです。
- パソコンの電源を切る
- コンセントを抜いておく
- 作業途中にデータを保存する
- 使わないときは電源を切る
- UPS(無停電電源装置)を利用する
- データのバックアップをする
ここでは、それぞれの対策方法について詳しくご紹介します。
パソコンの電源を切る
もしも落雷による影響、計画的に停電されると知っている場合は、パソコンの電源を落としておきましょう。
パソコンの電源を落としておくことで、停電したとしてもデータの消失やハードディスクへのダメージを押さえることができます。
最も簡単にできるうえ、効果的な対策方法です。
コンセントを抜いておく
心配な方は、念のためコンセントも抜いておきましょう。
基本的にはパソコンの電源を切るだけで十分対策できるものの、停電から復旧時には強い電気が流れ、内部のパーツがダメージを受ける可能性があります。
さらに安全性を確保したいときは、ルーターやモデムといった外部機器のコンセントも同じように抜いておきましょう。
作業途中にデータを保存する
いつ停電するか予想できない、もしくは作業を中断することができない場合は、作業途中にこまめにデータを保存するようにしましょう。
多くのアプリには自動保存できる機能もありますが、心配な方は念のためこまめに保存しておきましょう。
使わないときは電源を切る
長期間パソコンを使用している方、特にリモートワークのように自宅で仕事をしている方は、パソコンをつけっぱなしの方が多いのではないでしょうか?
電源を入れている間に停電が起こる可能性もあるため、使わないときは電源を切っておきましょう。
UPS(無停電電源装置)を利用する
停電によるパソコンの故障・データの損失を防ぐにはUPS(無停電電源装置)の利用がおすすめです。
USPとはパソコンが停電によって供給されなくなると、代わりに供給をしてくれる装置のことです。
USPには大容量のバッテリーが内蔵されているため、停電が起きてもパソコンの電源を供給できる仕組みとなっています。
これによって停電が起きてもパソコンを使い続けることができ、しっかりとデータの入力・保存を行ってから作業を修了できます。
突然の停電によって、ハードディスクが壊れるといった不安もありません。
実際、USPは多くの企業で導入されています。
しかし、なかには一般家庭で利用できるUPSも登場しており、お手頃な値段で購入できるため、災害時のために購入してみるのもおすすめです。
なお、USPには3つの種類があります。
3つに分けてそれぞれの種類をご紹介します。
常時商用給電方式
USPの中でも最も一般的な給電方式が、「常時商用給電方式」です。
常時商用給電方式は通常時は商用電源を用いてパソコンに電源を供給し、停電時は自動で内蔵バッテリーの出力に切り替えられます。
切替時に停電が起こるものの、パソコンに影響はありません。
値段は1万円前後〜2万円前後で購入できます。
このくらいの価格帯であれば、家庭用としても購入がしやすいのではないでしょうか。
常時インバータ給電方式
常時インバータ給電方式とは、常にインバーター(直流電流を交流電流に変換する装置)を通してパソコンに電源を供給するものです。
常時商用給電方式とは異なり、バッテリーの出力を切り替える際の停電が起こりません。
ただし、上記でも述べたように切替時の停電が起こってもパソコンに大きな影響はないため、家庭で使う分にはそこまでこだわらなくてよいでしょう。
そもそも常時インバーター給電方式は性能も高いことから、値段も30,000円〜数十万円と非常に幅広くいうえ、価格は高めです。
高いスペックを求めている方にはおすすめできますが、予算が限られている方は他の方式を検討してみましょう。
ラインインタラクティブ方式
ラインインタラクティブ方式とは、普段は商用電源を用いてパソコンに電源を供給して、停電時にバッテリー電源から電力を供給します。
ラインインタラクティブ方式の最大の特徴として、トランスが備われているため、電圧調整ができ安定性に優れています。
停電切替時に瞬電を伴うもののの、パソコンに大きな影響はないため不安を抱く必要はありません。
価格は安いもので20,000円から3万円前後、高価なものになると数十万円になるのものもあります。
3種類のなかで最も手が届きやすい物が多いため、家庭用としてもおすすめです。
1,000VA程度の容量があれば、パソコンは10分から20分程度稼働できるため、その間に保存作業やシャットダウンをできるでしょう。
データのバックアップをする
重要なファイルをパソコンに保存している場合は、データのバックアップをしておきましょう。
バックアップを取ってデータを安全な場所に保管しておくことで、停電時以外のトラブルが起きても安心です。
パソコンに大事なデータがある方は、定期的にバックアップすることをおすすめします。


監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
会社はチームで共同作業をする機会が多くあり、そのときに便利なのがNASです。
NASはNetwork Attached Storageの略称で、複数人で同時に使用できる外付けのハードディスクです。
無線でも有線でも接続でき、データ共有が非常に簡単にできるようになります。
そんな便利なNASですが、突然使えなくなるケースが多々あります。
そこでこの記事では
- NASに接続できないときに見られる症状
- NASに接続できない主な原因
- NASに接続できない時の対処法
を徹底解説します。
NASが接続できないと悩んでいるときはぜひ参照にしてください。
NASの基礎知識

まずは、NASがどういったものなのか、下記の2つに分けて基本的なことを押さえておきましょう。
- NASとは?
- NASとHDDとの違い
それぞれの基礎知識をご紹介します。
NASとは?
NASはNetwork Attached Storageの略称で、NAS=ナスと呼ばれます。
NASはネットワークに直接接続できる外付けハードディスクで、複数のパソコンやスマートフォンで接続・共有ができます。
複数人で接続・共有ができることから、チームでの作業に非常に役立ち、多くの会社で利用されています。
NASとHDDとの違い
NASもハードディスクのではあるものの、こちらは1対複数です。
異なるデバイスでもファイルの共有やデータの保存ができ、ファイルサーバーのように使用もできます。
一方のハードディスクは、1対1で接続するものとなっています。
さらにNASは会社で使用されるのが一般的で、自宅では使用されません。
自宅ではハードディスクの使用が一般的です。
NASに接続できないときに見られる症状

NASに接続できないときに見られる症状は、下記の3つです。
- フォルダにアクセスできない
- エラーコードが表示されない
- NASが起動しない
「アクセスが拒否されました」「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」といった言葉が表示されている場合は、NASに問題が起きている可能性があります。
また、NASにエラーコードが表示されたり、起動しなかったりするのも、NASに問題がある証拠です。
このような表情が見られた場合は、自分で直そうとせず業者に依頼しましょう。
自分で直そうとするとデータを失ったり、故障したりする原因となるため、注意してください。
NASに接続できない主な原因

NASに接続できない主な原因は、以下の4つです。
- ネットワーク上の接続エラー
- NAS内のHDDやSSDの故障
- NASの故障
- アクセス権限の設定
ここでは、接続できない主な原因を紹介します。
ネットワーク上の接続エラー
ネットワーク上の設定でNASの接続ができないケースがあります。
具体的には「パブリックネットワーク」(ネットワーク上の他の機器からの通信を遮断)になったり、ファイアウォールが有効になっていたりすることが原因です。
有線接続の場合は、ケーブルが故障していて接続エラーになっている可能性もあります。
なお、パブリックネットワークになっている場合は、プライベートネットワークに変更することで解消されるケースがあります。
NAS内のHDDやSSDの故障
NAS内のHDDやSSDの故障が原因で、接続エラーが起きている可能性があります。
HDDやSSDの故障といっても、物理障害と論理障害の2つがあります。
論理障害は、ウイルスへの感染や誤作動によるデータの削除といったファイルシステムが破損した状態です。
物理障害とは強い衝撃や水没、経年劣化などが原因で起こります。
理論障害と物理障害はどちらも違う原因で起こるものの、似ている症状が多く、知識のない初心者が見極めるのは困難です。
安全にデータを取り出したい場合は、専門業者への依頼をおすすめします。
NASの故障
NASの共有フォルダにアクセスできないときは、NASが故障している可能性があります。
とはいっても、NASの内部HDD、SSDドライブに不具合は生じていないため、修理をすれば問題なく動きます。
また、HDDやSSDのファイルシステムも破損している可能性も0ではありません。
故障原因を探るときや、データを確実に復旧させたいときは、専門業者に依頼しましょう。
アクセス権限の設定
アクセスができない場合は、アクセス権限が設定されていない可能性があります。
管理者側からアクセス権限が付与されていない、許可されていない場合は共有フォルダにアクセスできません。
アクセス権限の付与がされているか、確認してみましょう。
NASに接続できない時の対処法

NASに接続できないときの対処法として、下記の4つが挙げられます。
- 接続しているパソコンの台数の見直し
- ネットワーク設定の見直し
- パソコン・NASの再起動
- 専門業者への相談
ここでは、それぞれの対処法を詳しく紹介します。
接続しているパソコンの台数の見直し
NASには接続できるパソコンの台数に上限があります。
前提として、同時接続できる台数はNASが家庭用か法人用かによって異なります。
家庭用であれば10人未満となっていますが、法人向けの場合は100人ほどの接続ができるNASもあり、メーカーや機器によっても大きく異なり、一概にはいえません。
また、上限を下回っていても、データ活用によってうまく接続できないケースがあります。
まずは導入しているNASの推奨人数を確認して、そこから接続しているパソコンの台数を減らしてみましょう。
ネットワーク設定の見直し
NASに接続できない原因でも述べたように、ネットワーク設定がパブリックネットワークになっていると接続できないケースがあります。
これは、パブリックネットワークになっているとセキュリティの問題でNASがアクセスできなくなるためです。
プライベっとネットワークにして、接続を試してみましょう。
パソコン・NASの再起動
パソコン・NASの再起動で直るケースがあります。
ただし、NASは何度も再起動を行っているとHDDの破損箇所が拡大する恐れがあるため、繰り返さないようにしてください。
また、ハードディスクの破損を考えると、事前にデータのバックアップを行ってから再起動をするのが安全です。
専門業者への相談
NASのトラブル解決には高い技術力と豊富な知識が求められるため、困ったら専門業者へ相談しましょう。
自力で解決しようと試行錯誤をしても、かえって悪化する可能性があります。
少しでもわからないと思ったら、自分で直そうと思わずに専門業者に相談をして下さい。
少しでもおかしいと思ったら専門業者に相談をしよう
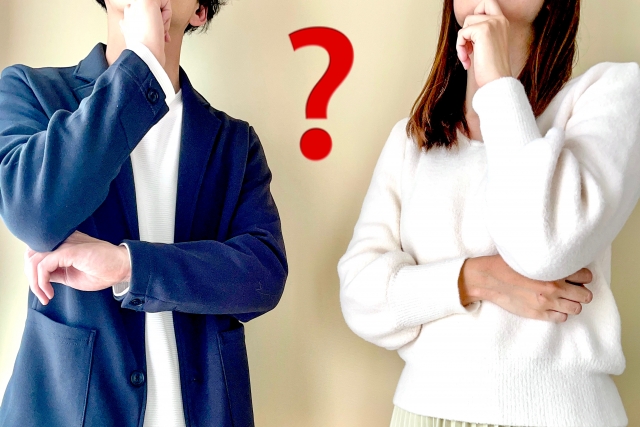
NASの寿命はメーカーや機種によって異なるものの、5年から10年が目安だといわれています。
そのため5年以上経過しているNASAの場合はいつ壊れてもおかしくありません。
また、日頃の扱いが丁寧ではないと、その分壊れる可能性も高くなります。
もしもNASに異常が見られたら、自分で対処しようとせずにすぐに専門業者へ相談しましょう。


監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Macのキーボードが故障した際、どのように修理を行えばいいか迷う方は多いのではないでしょうか。
この記事では、Macのキーボードの修理方法や注意点について解説しています。
Macのパソコンを使用している方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- Macのキーボードの修理方法
- Macのキーボードを修理に出す際の注意点
Macのキーボードを修理する方法

Macのキーボードは自力での修理が難しいため、故障した場合はプロに依頼するのが一般的です。
ここでは、修理の依頼先を4つ紹介します。
Apple Store直営店に持ち込む
Apple社が運営する直営店では、Macのキーボードの修理を受け付けています。
Apple Store直営店ではApple製品の販売から修理まで一貫して行っており、2022年11月現在、日本国内で合計10店舗展開しています。
Apple Store直営店にキーボードの修理を依頼する際は、Apple公式サイトから事前に予約したうえで機器の持ち込みが必要です。
ただし、店舗数が限られているため予約が取りづらい場合があります。
Apple正規サービスプロバイダに持ち込む
Apple正規サービスプロバイダとは、Apple公認の修理サービス店です。
Apple正規サービスプロバイダにMacのキーボードを持ち込むことで、Apple社でトレーニングを受けた技術者による純正パーツを使用した修理が受けられます。
Apple正規サービスプロバイダは全国で展開しているため、近くにApple Store直営店がない場合でも利用しやすい点がメリットです。
店舗によっては事前予約が必要になりますので、あらかじめ公式サイトなどを確認しておきましょう。
Appleリペアセンターに配送修理を依頼する
Appleリペアセンターではオンラインまたは電話で配送修理を依頼でき、Apple指定の配送業者に自宅まで集荷に来てもらえます。
お店にキーボードを持ち込む必要がないことから、近くにApple Store直営店やApple正規サービスプロバイダがない場合や予定が合わない方におすすめです。
ただし、持ち込みによる修理よりも時間がかかるケースが多いため、急ぎの場合は別の方法を利用するのがよいでしょう。
専門の修理業者へ依頼する
民間のパソコン修理専門業者でも、Macのキーボードの修理を受け付けている場合があります。
民間の修理業者はApple Store直営店やApple正規サービスプロバイダと比べて修理費用が安く済むケースが多く、業者によっては即日修理を行っている点が魅力的です。
ただし、純正パーツを使用しないため、Appleの保証が適用されなくなる可能性がある点に注意してください。
もともと保証期間外のキーボードが故障した場合や、できるだけ早く直してほしい場合におすすめです。
Macのキーボードを修理する前に確認すべきポイント

ここでは、Macのキーボードを修理に出す前に確認しておくべきポイントを3つ紹介します。
場合によっては修理が不要になるケースもあるため、以下の内容を必ずチェックするようにしてください。
パソコンを再起動する
キーボードに不具合があるように見えても、実際はキーボード以外で問題が起きているケースがあります。
原因がはっきりわからないときは、まずはMac本体の再起動を試してみましょう。
これでトラブルが解消された場合、一時的な問題が発生していたか、キーボード以外に不具合が生じていることが考えられます。
MacOSのバージョンを確認する
MacOSを最新バージョンに更新することで、キーボードの不具合が解消される場合があります。
修理に出す前に、以下の手順に従ってOSのアップデートを行ってください。
【macOSをアップデートする手順】
- アップルメニューから「システム設定」を選択する。
- 「一般」をクリックし、「ソフトウェアアップデート」を選択する。
- 新しいソフトウェアが見つかった場合は、画面の案内に従ってインストールを実行する。
参考:Mac の macOS をアップデートする – Apple サポート (日本)
データのバックアップを取る
キーボードをMac本体ごと修理に出す場合は、事前にデータのバックアップを取っておくとよいでしょう。
Macのバックアップ手段は、Time Machineという内蔵アプリを利用する方法と、iCloudを利用する方法の2種類あります。
バックアップがあれば、万が一修理中にデータが消えてしまった場合でも安心です。
修理費用が高額になりやすいキーボードの故障内容

キーボードの故障内容によっては、通常よりも修理費用が高くなる場合があります。
ここでは、代表的な事例を3つ紹介します。
キートップが外れた
経年劣化やキーボードに強い衝撃を与えてキートップが外れてしまった場合は、基本的にはそのパーツのみ交換を行います。
しかし、修理店によっては部品在庫を用意していないことも多く、キーボード1台分の費用を請求されるケースがあります。
また、部品取り寄せのために時間がかかる場合があるため、急いでいる場合は注意してください。
チャタリングが発生した
チャタリングとは、「一度キーを押しただけで複数回入力される」といった症状を引き起こす電気的な振動現象のことです。
特定のキーでチャタリングが発生した場合、すべてのキーで同じ症状が発生する恐れがあります。
そのため、問題が起きたキーだけでなく、キーボード全体の洗浄修理が必要です。
キーボードに液体をこぼした
キーボードの上に水・お茶・ジュース・お酒などの液体をこぼした際は、修理について特に注意しなければいけません。
ただの水であれば自然乾燥によってキーボードが復活する可能性がありますが、水以外の糖分を多く含んだ液体がキーボードにかかった場合、ロジックボードにまで影響を及ぼすことが考えられます。
その結果、キーボード交換だけでは症状を改善できないケースも多く、Mac本体の修理が必要になることがあります。
まとめ:キーボードの修理はプロに任せよう

この記事では、Macのキーボードの修理について解説しました。
故障したキーボードを自分で直そうとするとかえって症状を悪化させる恐れがあるため、専門業者に依頼するのがおすすめです。
Apple保証期間中の場合や純正パーツにこだわりがある場合は、Appleが提供している修理サービスを利用するとよいでしょう。
今回の記事もぜひ参考にしてくださいね。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。
Macで不具合が起きたとき、リカバリーモードを利用することで症状を改善できる場合があります。
しかし、何らかの原因でリカバリーモードが起動できず、お困りの方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、Macでリカバリーモードが起動しないときの対処法を解説しています。
Macをお使いの方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- Macのリカバリーモードを起動する方法
- Macのリカバリーモードが起動しないときの対処法
Macのリカバリーモードとは?

Macのリカバリーモードとは、Macに内蔵されているOS復元システムを指します。
リカバリーモードでは、MacOSの再インストール・ハードディスクの修復・バックアップからのデータ復元などの実施が可能です。
本体が正常に起動しない・再起動を繰り返す・画面が何度もフリーズするといった不具合を解消できるため、Macの問題を自己解決するのに役立ちます。
Macでリカバリーモードを起動する方法

Macでリカバリーモードを起動する方法は以下のとおりです。
モデルによって操作方法が異なるため、お使いのパソコンにあわせて操作を実施してください。
【Appleシリコン搭載のMacモデル】
- Macの電源が完全に切れていることを確認し、電源ボタンを長押しする。
- 「オプション」が表示されたら、電源ボタンから指を離して「オプション」を選択する。
- 「続ける」をクリックする。
- ユーザーを選択してパスワードを入力する。
参考:macOS を再インストールする方法 – Apple サポート (日本)
【Intel搭載のMacモデル】
- Macの電源ボタンを押して電源を入れ、その直後に「command 」キーと「R」キーを同時に長押しする。
- Appleロゴが表示されたらボタンから手を離す。
- ユーザーを選択してパスワードを入力する。
参考:macOS を再インストールする方法 – Apple サポート (日本)
Macでリカバリーモードが起動しないときの対処法

上記の手順を実施しても、何らかの理由でリカバリーモードを起動できない場合があります。
ここでは、その際の対処法を6つ紹介します。
キーボードの状態を確認する
外部キーボードを使用している場合、キーボードが正しく認識されていないことが原因でリカバリーモードが起動しないことがあります。
キーボードのケーブルを抜き差しして接続し直したり、正常に動作する別の機器と交換したりするなどしてキーボードの状態を確認しておきましょう。
キーボードに不具合がなければ、本体側に何かしらの問題が起きていると考えられます。
起動できるインストーラーを使用する
Macのリカバリパーティションは2011年から搭載されているため、コンピューターがあまりに古い場合はリカバリーモードを起動できません。
その場合、付属のリカバリーディスクを使用するか、起動可能なインストーラーを作成して使用する必要があります。
インストーラーの作成方法は以下の記事を参考にしてください。
参考:macOS の起動可能なインストーラを作成する – Apple サポート (日本)
起動可能なインストーラーを作成したら、Mac App StoreにアクセスしてMacOSの更新を行いましょう。
SMCをリセットする
リカバリーモードが起動しない場合、SMCをリセットすることで不具合が解消される場合があります。
SMC(システム管理コントローラ)とは、パソコンの起動・バッテリーなど、コンピューターの電源に関する機能を管理するシステムを指します。
SMCをリセットする手順は以下のとおりです。
【SMCをリセットする手順】
- Macの電源を切る。
- 電源が完全に切れたことを確認したら、「control」キーと「option」キーと「shift」キー+電源ボタンを同時に7秒間押す。
- 7秒後、Macの電源を入れ直す。
セーフモードで起動する
セーフモードで起動することで、リカバリーモードの起動を妨げる原因を突き止めたり、ドライブの不具合を修復したりすることができます。
セーフモードの起動方法は以下のとおりです。
【Appleシリコン搭載のMacモデル】
- アップルメニューを開き、「システム終了」を選択する。
- システムが完全に終了したことを確認できたら、電源ボタンを押す。
- 起動音が聞こえたらShiftキーを押し、そのまま「セーフモードで続ける」をクリックする。
- コンピューターが自動的に再起動されるため、ログイン画面のメニューバーに「セーフブート」が表示されているのを確認する。
参考:Macをセーフモードで起動する – Apple サポート (日本)
【Intel搭載のMacモデル】
Macを起動したら、すぐにShiftキーを長押しし、ログインウインドウが表示されたら放す。
Macにログインする。ログイン画面のメニューバーに「セーフブート」が表示されているのを確認する。(再度ログインを求められる場合もある。
参考:Macをセーフモードで起動する – Apple サポート (日本)
セーフモードの起動後はいったんパソコンの電源を切り、リカバリーモードを起動できるか確認してください。
Time Machineバックアップで復元する
TimeMachineにバックアップデータが保存されていれば、リカバリーモードを起動できない場合でもMacOSの復元が可能です。
以下の手順に従って、TimeMachineを操作してください。
【TimeMachineからMacOSを復元する手順】
- Macの電源を切り、TimeMachineバックアップドライブを接続する。
- 電源ボタンを押したら、すぐに「Option」キーを長押しする。
- Startup Managerが表示されたらキーから手を離す。
- バックアップドライブを選択し、「戻る」をクリックする。
- バックアップを選択して復元を行う。
Mac Internetリカバリーを使用する
リカバリーパーティションが破損している場合、Mac Internet Recoveryを使用してMacOSの再インストールを行いましょう。
Mac Internet Recoveryの操作手順は以下のとおりです。
【Mac Internet RecoveryでMacOSを再インストールする方法】
- Macの電源が完全に切れていることを確認して、電源ボタンと「Command」キーと「Option」と「R」キーを同時に長押しする。
- 画面に回転する地球儀が表示されたら、キーから指を離す。
- OS Xユーティリティインターフェースが表示されたら、「macOSを再インストール」をクリックする。
まとめ:適切な対処でデータを守ろう

この記事では、Macでリカバリーモードが起動しない際の対処法について解説しました。
リカバリーモードではパソコンの不具合の解消やOSの復元などを行えますが、リカバリーモードが起動しない場合、本体が故障していることも考えられます。
対処を誤ると大切なデータが消えてしまう恐れがあるため、上記の方法を参考にしながら慎重に対応を行ってください。
また、日頃から定期的にバックアップを取っておくことをおすすめします。
今回の記事もぜひ参考にしてください。

監修者/前田 知伸
富士通を経て、リブート㈱代表取締役。パソコンリサイクル業15年目。国内外のIT資格を保有。NHKなど出演実績有り。