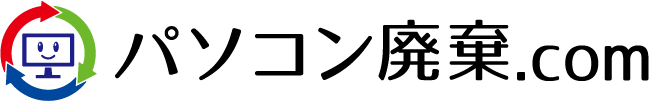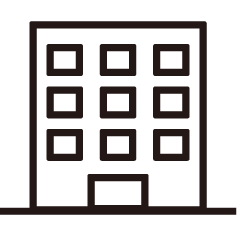404 Not Found
「スマホがフリーズした!直し方を知りたい」
「スマホがフリーズする原因を知りたい」
「フリーズしないようにする方法を知りたい」
ある日突然スマホがフリーズ!皆さんも一度は経験があるのではないでしょうか?この記事では、iPhone・Androidがフリーズする原因と直し方・予防法について解説します。
フリーズする要因は複数あり、状況に応じ適切な対処をするのが得策です。この記事を読めば、自分でフリーズを解消できるようになります。
フリーズのパターン5つ【iPhone・Android共通】

フリーズするタイミングがわかっていれば、おおまかな原因を推測できます。
①たまにフリーズ
この場合、原因は一時的なものです。アプリをたくさん立ち上げすぎた、高負荷なアプリを使用したなどのケースが該当します。
スマホの処理が追いついていないだけですので、負荷を下げれば解消できる可能性があります。
②特定のサイトでフリーズ
この場合、サイト側の応答が遅延しているだけかもしれません。他のWebサイトでもフリーズするか確認してみるとよいでしょう。
③特定のアプリでフリーズ
この場合、おそらくアプリに問題・バグがあります。また、アプリのキャッシュがたまり過ぎて動作が遅くなる場合もあります。
④あるアプリをインストール後にフリーズ
この場合、アンインストールすれば解消されますが、アプリのレビュー等で同じ症状が報告されていないかチェックしましょう。
⑤頻繁にフリーズ(数分おきなど)
この場合、慢性的なトラブルが生じている可能性があります。後述するバージョンアップ・ストレージの空き容量確保などの対策を実施してください。
フリーズする原因8つ【iPhone・Android共通】

慌てて対処せずに、まずは考えられる原因を把握しましょう。多くの場合、以下8つのどれかに当てはまります。
①充電不足
端末の電圧が低下すると、タッチパネルの反応が鈍くなるためフリーズしたと勘違いしてしまうことがあります。
まずはきちんと充電されているか確認しましょう。
②スマホの性能不足(CPU・RAM)
以下のような場合、スマホには大きな負荷が掛かります。
- 3Dゲームや実況配信
- 高画質の動画再生
- 複数アプリの同時立ち上げ
これらの場合、CPU処理能力の限界を超えてしまうことがあります。
また、CPUが使用するRAM(メモリ)の空き容量も不足するためスマホ全体の処理が遅延します。
③アプリケーションのバグ
App Store・Google Playからダウンロードできるアプリは、審査を経て公開されています。それでもソフトにバグ(欠陥)はつきもので、度々問題が報告されています。
この場合、後述のアンインストール・バージョンアップのどちらかの対策を取りましょう。
④OSとアプリのバージョンが古い
OSとアプリのバージョンアップでは、過去の不具合が修正されていることがあります。そのため、バージョンが古いままだとトラブルの原因となります。
⑤ストレージ不足(ROM)
ストレージの空き容量が不足していると一時的にRAMが代用されるため、RAM不足からスマホの処理が遅くなります。これにより、画面がカクカクしたりフリーズにつながったりします。
⑥ウイルスに感染
ウイルスに感染すると、スマホはフリーズなどの異常動作を繰り返します。後述の対策で直らない場合、感染が疑われますのでウイルス駆除・スマホ初期化などが必要です。
⑦本体の温度上昇による熱暴走
高負荷アプリの長時間使用・炎天下での使用などでスマホが高温になることがあります。一般的に本体温度が35℃を超えると、フリーズなどのトラブルが発生します。
高温になった場合は使用を中断し、温度が下がるのを待ちましょう。
⑧ハードウェア故障
劣化や衝撃等によるハード故障が原因の可能性もあります。また新品でも運悪く、初期不良の端末に当たってしまうことがあります。この場合、修理・交換が必要です。
フリーズの直し方7つ【iPhone・Androidそれぞれの手順】

まずは「①充電する」を確認しましょう。その後、以下の順番でひとつずつ確認してください。
フリーズしたまま操作できない場合
→「⑦強制再起動」の後②~⑥を確認
操作できる場合
→②~⑥を確認
①充電する
基本的なことですがバッテリー残量を確認し、必要であれば充電をしましょう。
②再起動する
再起動することでスマホのRAMがリフレッシュされます。アプリのバグによるメモリリーク(RAMの解放もれ)なども解消されます。
iPhoneの手順
モデルごとに手順が異なります。下記のAppleサポートページでご確認ください。
Appleサポートページ「iPhone を再起動する」
Androidの手順
機種により手順が異なりますが、基本的には以下の手順で再起動できます。
- 電源ボタン長押し
- 「再起動」アイコンをタップ
- 確認画面で「再起動」アイコンを再度タップ
③アプリ全てを強制終了
起動したままのバックグラウンドアプリが、通信や高負荷の処理を実行している可能性があります。下記の手順で全てのアプリを強制終了し、フリーズが解消されるか確認しましょう。
iPhoneの手順
モデルごとに手順が異なります。下記のAppleサポートページでご確認ください。
Appleサポートページ「iPhone や iPod touch で App を終了する方法」
Androidの手順
機種により手順が異なりますが、基本的には以下の手順で再起動できます。
画面下に「<」「□」「|||」ボタンがある場合
- 「|||」ボタンをタップ
- 画面下部「全て閉じる」ボタンをタップ(※)
画面下に「<」「□」「|||」ボタンがない場合
- 画面下から画面中央まで、上にスワイプ
- 「すべてクリア」ボタンをタップ(※)
※アプリを上にスワイプすると、ひとつずつ終了できます。
④フリーズするアプリのアンインストール
怪しいアプリが特定できている場合、そのアプリをアンインストールしてフリーズが解消されるか確認しましょう。
iPhoneの手順
下記Appleサポートページの手順でアンインストールできます。
- AppをiPhoneから削除する(iOS16・15・14)
- AppをiPhoneから削除する(iOS13・12)
Androidの手順
下記Google Playヘルプの手順でアンインストールできます。
Google Playヘルプ「Android で使用していないアプリを削除、無効化、管理する」
⑤OSとアプリを最新バージョンにする
OSとアプリを最新バージョンにすると、バグ修正や性能改善が反映されるためフリーズが解消されるかもしれません。
iPhoneの手順
どのモデルも、下記Appleサポートページの手順でアップデートできます。
Appleサポートページ
- iPhone や iPad をアップデートする(iOSのアップデート)
- Apple 製デバイスで App を手動でアップデートする方法(アプリのアップデート)
Androidの手順
機種により違いはありますが、基本的には下記Androidヘルプの手順でアップデートできます。
- Android のバージョンを確認して更新する(Android OSのアップデート)
- Android で Play ストアとアプリを更新する方法(アプリのアップデート)
⑥ストレージの空き容量を増やす
空き容量を無理に増やす必要はありません。下記手順で現在の使用済み容量を確認してから行ってください。
iPhoneの手順
どのモデルも、下記Appleサポートページの手順で確認できます。
Androidの手順
機種により異なりますが、基本的には以下の手順で確認できます。
- 「設定アプリ」をタップ
- 「ストレージ」または「バッテリーとデバイスケア(Galaxyの場合)」をタップ
iPhone・Android共に、データ(アプリ・画像等)を削除するか、クラウド等に移動すると空き容量を増やせます。
⑦スマホの強制再起動(電源を落とせない・再起動できない場合)
フリーズして操作不能の場合、下記の手順でスマホを強制再起動してください。
iPhoneの手順
下記Appleサポートページから、自分のiPhoneモデルに合った手順を実行してください。
| iPhoneのモデル | 強制再起動 |
|---|---|
| iOS16対応モデル | 手順 |
| iOS15対応モデル | 手順 |
| iOS14対応モデル | 手順 |
| iOS13対応モデル | 手順 |
| iOS12対応モデル | 手順 |
Androidの手順
機種ごとに異なるため、ここでは代表的な機種での手順をご紹介します。
AQUOS
- 電源ボタンを8秒長押し
- 振動したら指を離す
Galaxy
- 「電源ボタン」と「音量ダウンボタン」を同時に7秒長押し
OPPO
- 「電源ボタン」と「音量アップボタン」を同時に10秒長押し
Xperia
- 「電源ボタン」と「音量アップボタン」を同時に8秒長押し
- 3回振動したら指を離す
フリーズさせないための上手な使い方

以下の点に注意して使用すれば、フリーズ頻度を低く抑えることができます。
- こまめな充電
- 定期的に再起動
- 不要なアプリは終了させる
- OSとアプリを最新のバージョンに保つ
- 不要データは削除
- 発熱したら使用を控える
- 性能不足なら高性能機種への買い替えも検討
それでもフリーズしてしまう場合

以上の対処を行ってもフリーズしてしまう場合、修理・処分を検討しましょう。
修理に出す
修理に出す方法は大きく3種類です。
- メーカーの修理サービス
- キャリアの修理サービス
- 民間の修理店
ネット検索すれば、店舗や依頼方法が確認できます。費用や期間が異なりますので、比較検討すると良いでしょう。
まとめ:スマホがフリーズしても慌てず対処しよう!
今回は、iPhone・Androidがフリーズする原因と対処法・予防法について解説しました。
- フリーズの原因は複数あるので、ひとつひとつ確認
- 適切に対処・予防を行えばフリーズする頻度を抑えられる
- それでも直らない場合は、修理・処分も検討
スマホはこまめにケアをすれば、フリーズせず安定して動作します。日頃からバージョンアップなどを心がけ、長く使用できるよう心掛けましょう。

監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
Galaxyの機種変更や買い替え時には、データ移行が必要になるケースも多いでしょう。データ移行をスムーズに行うためには、正しい手順を理解しておくことが大切です。誤った手順で操作を行うと、データが破損したり、消えたりしてしまう可能性があるからです。
そこで今回は、Galaxyのデータ移行方法についてご紹介します。移行前にやっておくべきことについても解説しますので、「Galaxyにデータ移行したい」または「Galaxyからデータを移行したい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事でわかること】
- Galaxyにデータを移行する方法
- データ移行前にやっておくべきこと
- Galaxyからデータを移行する方法
Galaxyへデータを移行する方法

Galaxyへデータを移行する方法には、次の5つがあります。
- Smart Switchを利用する(おすすめ!)
- Googleアカウントを利用する
- Galaxyアカウントを利用する
- 外部ストレージを利用する
- 各キャリアのデータ移行サービスを利用する
この中では、Smart Switchを使う方法がおすすめです。それぞれの手順や注意点について、1つずつ説明していきます。
Smart Switchを利用する(おすすめ!)
Galaxyの移行では、Smart Switchの利用がおすすめです。Smart Switchとは、Galaxyを製造しているサムスン電子が提供している機種変更アプリのことです。
簡単な操作でデータ移行できるのと、キャリアを問わずiPhoneやAndoroidのどちらにも対応しているところがメリットといえます。
Smart Switchを利用する際は、次の5つをおさえておきましょう。
- Smart Switchで移行できるもの
- Smart Switchの対応端末
- Androidから移行する場合
- iPhoneから移行する場合
- フィーチャーフォンから移行する場合
順番に解説していきます。
Smart Switchで移行できるもの
Smart Switchを使って、移行できるデータは次のとおりです。
- 連絡先
- 画像
- 動画
- 音楽
- ドキュメント
- アプリ(※1)
- ホーム画面(※2)
- 設定(※2)
※1:フィーチャーフォンからの移行はできません。
※2:iPhoneからの移行はできません。
Smart Switchや他の方法でも、移行できないデータがあります。次のアプリを利用されている方は、手動でのデータ引継ぎをしてください。
<Smart Switchでデータ移行できないアプリ>
- LINEアプリのアカウント情報とトーク履歴
- おサイフケータイ
- ゲームアプリ
Smart Switchの対応端末
Smart Switchアプリのサポート対応端末は、次のとおりです。
- Android 端末:Android 4.3 以上を搭載している端末
- iOS 端末:iOS 5.0 以上を搭載している端末
Galaxy端末同士のデータ移行でも、Androidのバージョンによっては対応していないことがありますので、注意しましょう。
また、iOS 端末に、Smart Switch アプリはインストールできません。あらかじめ iCloud 上にデータのバックアップを作成して、新しいGalaxy端末にSmart Switchをインストールして復元する手順となります。
Androidから移行する場合
Android端末からGalaxyにデータを移行する場合、次の2つの方法があります。
- ワイヤレス接続
- 有線接続
手軽にできるおすすめの方法は、ワイヤレス接続です。ただし、ワイヤレスの場合は、有線接続より時間がかかることがあります。
移行するデータが多いときは、有線接続をしてください。その際、スマホ同士の接続には「OTG変換アダプター」が必要となります。
<ワイヤレス接続でデータ移行>
まず、ワイヤレス接続して、データ移行する手順を解説します。
- 旧端末、Galaxy(新端末)の両方でSmart Switchを起動する
- 旧端末で「接続方法の選択」画面が表示されたら「ワイヤレス」を選択する
- Galaxyで「データの受信」を選択→端末の選択で「Galaxy/Android」を選択
- Galaxyで「接続方法を確認」画面が表示されたら「ワイヤレス」を選択する
- Galaxyで「接続方法を確認」画面が表示
- 旧端末で「接続への招待」が表示されたら接続元を確認し「同意する」をタップ
- 転送データの検索が100%まで完了すると「転送するデータを選択」画面が表示される
- 転送したいデータを選択して「次へ」をタップ
- データのコピーが実行される
完了画面が表示されたら、旧端末とGalaxyでチェックボタンを押してアプリを終了すれば、データの移行作業は完了です。
<有線接続でデータ移行>
次に、有線接続で移行する手順を解説します。作業の前にOTG変換アダプターを準備しておきましょう。
- 旧端末とGalaxy(新端末)の両方でSmart Switchを起動する
- 旧端末とGalaxyをケーブルで接続する(Galaxy側にOTG変換アダプタをつかう)
- 「送信するコンテンツを選択」から移行データを選択して「転送」をタップ
- データの移行が終わったら「完了」をタップ
iPhoneから移行する場合
iPhoneからGalaxyにデータ移行する方法は、次の2つです。
- iCloudを利用する(Wi-Fi接続)
- Lightningケーブルを使う(有線接続)
手軽にできるのは、iCloudを利用する方法です。あらかじめ、iCloud上に旧端末のデータのバックアップを取っておいてください。
有線接続の場合は、「OTG変換アダプター」が必要です。一部のGalaxyには同梱されていますが、付属していない場合は、別途用意してください。
<iCloudでデータ移行>
iPhoneからGalaxyへデータ移行する場合は、まずiPhoneのバックアップを取りましょう。バックアップ手順は次のとおりです。
- 「設定」→「ユーザー名」をタップ
- 「iCloud」→「iCloudバックアップ」をタップ
- 「このiPhoneをバックアップ」をオンにする
バックアップができたら、次の手順でデータを移行します。
なお、iCloudにサインインするためのApple ID(またはメールアドレス)とパスワードが必要となりますので、あらかじめ準備しておいてください。
- 新しい端末(Galaxy)でSmart Switchを起動する
- 規約を確認して同意、許可を選択する
- 「データを受信」を選択する
- 古い端末の種類は「iPhone/iPad」を選択する
- 一番下に表示される「代わりにiCloudからデータを取得」をタップする
- iCloudに登録したApple IDでサインインする
- iPhoneに送信された認証コードを、Galaxyに入力する
- 転送データの検索後、転送するデータの選択画面が表示される
- 必要なデータにチェックを入れて「次へ」
- コピーが開始する
コピーが完了したら「完了」ボタンをチェックして終了です。
<有線接続でデータ移行>
iPhoneからGalaxyに、ケーブルを使ってデータ移行する手順は、次のとおりです。
- 新しい端末(Galaxy)でSmart Switchを起動する
- iPhoneとGalaxyをケーブルで接続する(Galaxy側にOTG変換アダプタをつかう)
- 「このコンピュータを信頼しますか?」と表示されたら「信頼」をタップ
- 「送信するコンテンツを選択」から移行データを選択して「転送」をタップ
- データの移行が終わったら「完了」をタップ
フィーチャーフォンから移行する場合
スマホ以外のフィーチャーフォンの場合は、microSDカードを使ってGalaxyにデータを移行します。新しくmicroSDカードを購入する際は、キャリアのホームページ等で自分の使用している機種に対応した製品を購入してください。
なお、初めてmicroSDカードを利用するときは、フォーマットが必要となります。
フィーチャーフォンから移行する手順は、次のとおりです。
- GalaxyにmicroSDカードを挿入する
- Smart Switchを起動して、画面右上のSDアイコンをタップ
- 「復元」をタップ
- 「フィーチャーフォンのメディア/ファイル」をタップ
- 「送信するコンテンツを選択」から移行データを選択して「復元」をタップ
- データの移行が終わったら「完了」をタップ
Googleアカウントを利用する
Googleアカウントを使って、Googleドライブにデータを保存し、新しいスマホにデータを移行することもできます。既にアカウントがあるなら、手軽にできる方法です。
ほとんどのデータは自動バックアップされますが、一部のデータはバックアップ対象外です。画像、動画、音楽などのメディアファイルは、自動移行できないため、注意しましょう。
また、Googleドライブ上の保存領域となる「Google One」では、無料で使える容量が15GBとなっており、それ以上の容量になるとバックアップができません。この場合は、パソコンへのデータ退避や、別のクラウドストレージを利用するなどの方法を検討してください。
Galaxyアカウントを利用する
Galaxyアカウントを利用して、データを移行することもできます。Galaxyアカウントがあれば、Galaxyクラウドのバックアップと復元機能が使えます。
「自動バックアップ」をオンにして旧端末でバックアップを取得し、新端末でGalaxyアカウントでログインすれば、データの復元ができるでしょう。
Galaxyアカウントで、バックアップや復元ができる主な項目は、次のとおりです。
- 電話
- メッセージ
- 連絡先(本体に保存)
- カレンダー(本体に保存)
- 着信音(標準の着信音を除く)
- Wi-Fi 設定
- ペアリングされた Bluetooth デバイス
- ホーム画面のレイアウト、壁紙(標準の壁紙を除く)
- アプリ(インストールファイルと Galaxy のアプリ設定)
- 録音した音声ファイル
参考:Galaxyクラウドにデータをバックアップまたは復元する方法
外部ストレージを利用する
PCなどの外部ストレージを使って、データを移行する方法もあります。Smart Switchを使ってバックアップデータをPCに保存し、そのデータを新しい端末へ移行します。
この方法では、外部ストレージが必要となり、また、PCを経由してデータ移行しなくてはなりません。少し手間がかかるため、他の方法を利用することをおすすめします。
各キャリアのデータ移行サービスを利用する
データの移行作業に不安がある方は、各キャリアのデータ移行サービスを利用しましょう。専門スタッフに相談しながら進められるため、安心してデータ移行ができます。
ただし、店舗の混雑具合や、端末の保存容量によっては時間がかかることがあります。また異なるキャリア間の場合は、対応できないことがありますので注意してください。
Galaxyへデータを移行する前にやっておくべきこと

データ移行前にやっておくべきことをご紹介します。正常にデータ移行するためにも、しっかりチェックしておいてください。
スマホを充電する
まずは、しっかりスマホを充電しておきましょう。データの移行には、想定以上に時間がかかる場合もあります。また、途中で充電切れになると、正常にデータ移行できず、データが消失してしまうかもしれません。
フル充電か、最低でも、70%以上は充電しておくようにしてください。
OSを最新版にアップデートしておく
スマホのOSは、最新版にアップデートしておきましょう。これは、旧端末と新端末でOSのバージョンに差があると、うまくデータ移行できないことがあるからです。
毎回アップデートする手間を省くには、自動アップデートにしておくのがおすすめです。ウイルスなどの脅威から守るためにも、スマホのOSは常に最新にしておきましょう。
Googleアカウントの情報を控えておく
GoogleアカウントのログインIDとパスワードは、あらかじめメモしておいてください。新しいスマホにデータを移行する際、Googleアカウントでログインする必要があります。
データ移行中、Googleアカウントにログインできないと、元のデータが復元できない可能性があります。スムーズに移行作業をするためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。
個別にデータ移行すべきもの
次の3種類のアプリは、自動でデータ引き継ぎができないため、手動での作業が必要です。
これらのアプリのデータは、個別にバックアップを取ってから移行しましょう。
- LINE
- 電子マネー
- ゲームアプリ
1つずつ解説していきます。
LINE
LINEアプリでは、「引き継ぎ」機能を使ってデータを移行します。引き継ぎ前に次の3つを確認しておいてください。
- LINEのバージョンを最新にする
- スマホのOSバージョンを確認する
- LINEアプリのトーク履歴のバックアップ日付が最新になっているか確認する
引き継ぎできるデータは、スマホのOSやLINEアプリのバージョンによって異なります。旧端末が手元にある場合は、QRコードを使ってアカウントを引き継ぐのがおすすめです。QRコードを使った手順は、次のとおりです。
- 新端末でLINEアプリを開き「ログイン」
- 「QRコードでログイン」をタップ
- 「QRコードをスキャン」をタップ
- 旧端末で「ホーム」→「かんたん引き継ぎQRコード」をタップ
- QRコードが表示されたら、新端末でスキャンし「次へ」をタップする
- 同じOS間の移行でバックアップが完了している場合→新端末で「トーク履歴を復元」をタップ
- 異なるOS間の移行、またはバックアップを作成していない場合→「トーク履歴を復元せずに続行」をタップ(直近14日間のトーク履歴が復元)
以上で、引き継ぎ作業は完了です。
LINEバージョンによっては「バックアップ用のPINコード」が設定できます。PINコードを使うと、端末の故障や紛失時にデータの引き継ぎがスムーズになりますので、あらかじめ設定しておくとよいでしょう。
電子マネー
おサイフケータイなどの電子マネーは、データ移行前に残高を預けておかなくてはなりません。移行前に必ず実施しましょう。
手順は次のとおりです。
- 旧端末で、電子マネーのサイトにアクセス
- 残高をサービス事業者のサーバーに預ける
- 新端末でアプリにログインし、サーバーから預けたデータを受け取る
これらの手順を踏まないと、残高が移行できなかったり、チャージ済みのお金が利用できなくなったりすることがあります。電子マネーを利用している方は、各アプリのサポートサイトも参考にしながら、手続きしましょう。
ゲームアプリ
ゲームアプリは、データが保存されている場所によって対応方法が異なります。
アプリの保存方法は、次の2つのパターンがあります。
- ゲームデータがクラウド上に保存されている
- ゲームデータの一部がスマホに保存されている
ゲームデータがクラウド上に保存されている場合は、自分でデータ移行する必要はありません。新端末にゲームアプリをインストールして、データを読み込めばゲームが再開できます。
ただし、ゲームにログインするIDとパスワードが必要ですので、事前にメモするなどして控えておきましょう。
ゲームデータの一部がスマホに保存されている場合は、事前に旧端末でバックアップを取らなくてはなりません。旧端末でクラウド上のゲームサーバーにデータをバックアップし、新端末でログインしてデータを引き継ぐといった作業が必要です。
この場合も、ゲームにログインするIDとパスワードが必要ですので、あらかじめ確認しておきましょう。
各ゲームアプリの運営会社によって、データ移行手順が異なります。サポートページなどを参照し、指定された方法でデータを移行するのがおすすめです。
Galaxyからデータを移行する方法

ここでは、Galaxyから別のスマホへデータを移行する方法をご紹介します。AndroidとiPhoneの2つに分けて、移行手順を説明しますので参考にしてみてください。
Androidへ移行する場合
Galaxyから、Android端末へデータを移行する場合は、Googleアカウントを使いましょう。Googleアカウントのバックアップ機能を使うと簡単です。
手順は、次のとおりです。
- 旧端末で「システム」→「バックアップと復元」を開く
- 「自動バックアップ」と「自動復元」をオンにする
- 新端末でGoogleアカウントを使ってログインする
- 自動で復元される
Googleアカウントで自動的に復元できるデータは、次のとおりです。
- アプリデータ
- 連絡先
- Googleカレンダー
- SMS
- Wi-Fiネットワークとパスワード
- 壁紙
- Gmailの設定
- ディスプレイの設定
- 言語と入力
新しいスマホに移行アプリがあるかを、チェックするのがおすすめです。新端末に、Smart Switchのような機種変更用アプリがあれば、スムーズにデータ移行できるでしょう。
iPhoneへ移行する場合
GalaxyからiPhoneへデータ移行する場合は、「Move to iOS」を利用しましょう。ワイヤレス接続でデータ移行ができる便利なアプリです。
移行可能なデータは、次のとおりです。
- 連絡先
- Googleアカウント
- メッセージ(SMS)
- カレンダー
- 写真や動画
- ブラウザのブックマーク
- 一部のアプリ(iPhoneとAndroidに対応しているもの)
旧端末(Galaxy)で、Wi-Fi接続が有効になっているかを確認してから作業しましょう。またGalaxyに、「iOSに移行」アプリを入れておく必要がありますので、事前にインストールしておいてください。
GalaxyからiPhoneへデータ移行する手順は、次の通りです。
- 新しい端末(iPhone)の電源を入れてGalaxyに近づけます。
- 「クイック設定」画面で「手動で設定」をタップ
- 「Android からデータを移行」をタップ
- 旧端末で「iOSに移行」アプリを開く
- iPhoneで「Android から移行」画面が表示されたら「続ける」をタップ
- 10桁または6桁の数字が表示されるまで待つ
- 旧端末に、iPhoneで表示されたコードを入力する
- 「データを転送」画面で転送するコンテンツを選択し「続ける」をタップ
- 状況を表すバーが最後に進むまで待つ
- バーが最後まで進んだら旧端末で「完了」をタップ
- iPhoneで「続ける」をタップ
- iPhoneでiOSの設定をする
データの転送時は、Galaxy側で転送完了が表示されても、そのままにしておきましょう。進捗を表すバーが最後まで進み、転送が完了するまでは、2台のスマホを近づけたままにしておいてください。
なお、転送がすべて終わるまで時間がかかることがあります。
参考:Android から iPhone、iPad、iPod touch に移行する – Appleサポート
まとめ:Galaxyへのデータ移行はSmart Switchが便利!データ移行前の準備も忘れずに!
Galaxyのデータ移行は、Smart Switchの利用がおすすめです。Smart Switchを使えば、安全かつスムーズにデータ移行ができるでしょう。
データ移行前には、個別に作業が必要なアプリがあります。事前にしっかり確認して、準備してからデータ移行を始めてください。事前の準備を行っておけば、データ移行に失敗することがありません。
なお、スマホの買い替えなどで古い端末が不要になった場合は、安全に処分しなければなりません。そんな時は「パソコン処分.com」の利用が便利です。
費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。ただ不要になったスマホを梱包して送付するだけで処分できます。24時間365日いつでもお送りいただけますので、ぜひご利用ください。

監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。
Windows11のPCに不具合が生じたとき、何をやってもうまくいかないということがありませんか?
そんなときは初期化することで改善できることがあります。
この記事では
- Windows11のPCを初期化のメリットとデメリット
- Windows11のPCを初期化する方法
- Windows11のPCを初期化する前の注意点
- Windows11のPCを初期化できないときの対処法
について解説します。

PCを初期化するメリット

Windows11を初期化するメリットは以下の通りです。
- 処理速度の向上
- ウイルス除去
- 個人情報流出の防止
処理速度の向上
PCを初期化すると処理速度が上がります。
PCは使用に伴い様々なデータが溜まっていきますが、それらはスムーズな動作を妨げることもあります。
初期化することで溜まった不要なデータを消去することで動作が軽くなります。
ウイルス除去
PCの初期化はウイルス感染した場合にも有効です。
ウイルスソフトで特定できなかった場合にはウイルス除去の最後の手段となります。
個人情報流出の防止
PCを処分したり誰かに譲る場合は初期化することで個人情報を削除することが出来ます。
初期化するデメリット

初期化をデメリットは以下の通りです。
- バックアップしないとデータが戻せない
- 作業が長時間する場合がある
バックアップしていないデータは消える
当然ですが、初期化をするとデータは全て失われます。
バックアップを忘れてしまった場合は元に戻すことができないので注意しましょう。
作業が長時間に及ぶこともある
通常初期化は30分程度で終わりますが、PCのスペックによっては数時間かかることもあります。
初期化後の設定等も含めて、時間に余裕があるときに初期化するようにしましょう。
Windows11の初期化方法
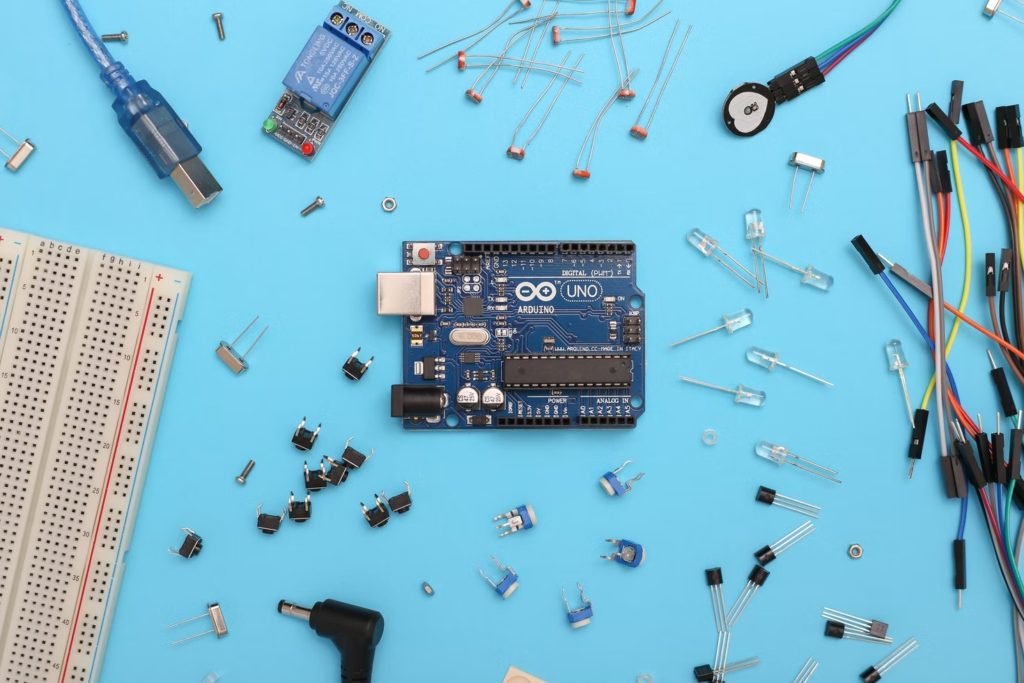
Windows11のPCを初期化には以下の2種類があります。
- 個人用ファイルを保持する
- 全て削除する
それぞれの方法を解説していきます。
個人用ファイルを保持する
個人用ファイルを保持して初期化する場合は以下の手順で行います。
- スタートボタンから「設定」をクリック
- システムの中の「回復」をクリック
- 「このPCをリセットする」をクリック
- 「個人用ファイルを保持する」をクリック
- Windowsの再インストール方法を「クラウド」か「ローカル」から選択
- 追加の設定でダウンロードするかしないかを選択
- このPCをリセットする準備が出来ましたと表示されたら「リセット」をクリック
- 削除されるアプリを確認
- リセットをクリック
- そのまま待つ
全て削除する
全て削除する場合は以下の手順で行います。
- スタートボタンから「設定」をクリック
- システムの中の「回復」をクリック
- 「このPCをリセットする」をクリック
- 「すべて削除する」をクリック
- Windowsの再インストール方法を「クラウド」か「ローカル」から選択
- 追加の設定でクリーニングするかしないかを選択
- データのクリーニングを実行すれば完全にデータを削除できる
- このPCをリセットする準備が出来ましたと表示されたら「リセット」をクリック
- そのまま待つ
Windows11を初期化する際の注意点

Windows11のPCを初期化するときの注意点は以下のものがあります。
- 十分な時間を確保する
- 消えてしまうデータや設定を確認
- 必要なデータはバックアップを取る
- Microsoftのメールアドレス、パスワードや各種設定をメモしておく
- Microsoftアカウントでの注意事項
- BitLockerドライブの暗号化
十分な時間を確保する
PCの初期化はPCのスペックにもよりますが、かなり時間がかかることもあります。
急ぎPCを使う予定がある場合は初期化は避け、時間に余裕があるときにしましょう。
思わぬトラブルなどが発生することも加味して半日ぐらいは見ておいた方が無難です。
初期化の種類を確認する
Windows11の初期化には2種類あり、
- 個人用ファイルを保持する
- すべて削除する
があります。
個人用のデータや設定を残したい場合は【個人用ファイルを保持する】を選びましょう。
必要なデータのバックアップを取る
初期化すれば当然データは消えてしまうので、大切な写真やファイルなどはUSBや外付けのストレージに保存しておきましょう。
このときにウイルスチェックを怠らないように注意が必要です。
ウイルスに感染したデータを初期化後のPCに戻せばそのままウイルスも侵入してしまいます。
Windows11のPCを初期化できない時の対処法
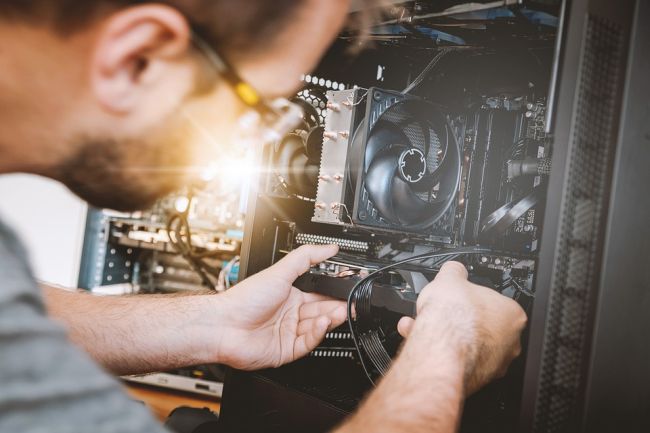
Windows11のPCを初期化できないときは以下の対策が有効です。
- 初期化に必要ない周辺機器を外す
- 自信がないときは業者へ依頼
周辺機器を外す
PCに接続されているプリンターなどの周辺機器は全て外しておきましょう。
接続しているままで初期化を始めると、デバイスドライバー関連で不具合が発生することがあります。
不具合が原因で初期化ができないこともありますので、初期化に必要なキーボードやマウスなどの周辺機器以外はすべて外して初期化を始めましょう。
自信がない場合は業者へ依頼
初期化は手順を誤ると大切なデータが消えてしまう可能性があります。
自分で初期化する自信がなかったり、PCの操作に苦手意識がある場合は無理に作業をせず、業者に依頼しましょう。


監修者/前野 哲宏
フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。